

唐澤久美子(からさわ・くみこ)1959年横浜市生まれ。東京女子医科大学卒業。同大放射線医学講座講師、順天堂大学医学部放射線医学講座助教授、放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院治療課第三治療室長などを経て、2015年から東京女子医科大学教授・講座主任、2018年4月から医学部長。
東京女子医科大学 医学部長
放射線腫瘍学講座教授・講座主任
唐澤久美子/㊦
母校・東京女子医科大学の放射線腫瘍学の主任教授として、診療、研究、教育に追われていた唐澤久美子は、自分が専門とする乳がん(ステージ2)を自ら発見した。これから、どのような治療が行われるかについては、誰より熟知していた。
家族歴から、いずれ発病するだろうと予想していたので、事実を淡々と受け入れた。もし、乳がん患者になったら、自分が関わっている重粒子線の臨床試験に参加したいと思っていた。しかし、既にがんが直径2cm以上になっていたため、臨床試験の組み入れ基準から外れていたことをとても残念だと感じる余裕もあった。
かくなる上は、ガイドラインに沿った標準的な治療を受けるしかない。乳がんに多様なサブタイプがある中で、唐澤は、ルミナルBタイプで、HER2遺伝子検査では陰性だった。女性ホルモン(エストロゲン)受容体への感受性があるためホルモン療法が有効で、がん細胞の増殖力が高いことから抗がん剤治療の併用も推奨されている。
唐澤は子供の頃から薬に対してアレルギーが出やすい体質で、抗生物質、消炎鎮痛剤など様々な薬で頻繁に副作用を体験していた。また、CT検査の造影剤でショックを起こしたり、抗ヒスタミン薬の影響が強く出てフラフラになってしまったりという経験もあった。
手術に先立ち、がんを縮小させるための化学療法を行い、パクリタキセルの週1回投与が開始された。薬剤過敏性のアレルギー症状が出やすい薬で、投与直前に抗ヒスタミン薬を内服しステロイドを注射する前処置を行う。その治療だけでも耐え切れなさそうだった。案の上、初回から皮疹と倦怠感に見舞われた。皮膚科医の診立てでは、薬疹であることは間違いなさそうで、2回目の投与後には全身を皮疹が襲った。
自ら使って分かった薬の重篤な副作用
そこで、副作用が少し違うとされるドセタキセルに切り換えることになった。しかし、副作用はむしろ増幅された。激しい神経障害が生じ、夜寝られないほどの痛みに襲われた。それを押して、何とか地方で行われた学会に出席したものの、翌日から激しい下痢が生じた。
これらの薬の臨床試験に関わっていたので予備知識はあったが、いざ自分が使ってみると、患者を担当した際には経験のない重篤な副作用だった。激しい下痢と腹痛で食事を取ることもままならず、やむなく入院。骨髄抑制が起こり、好中球は300/μL台にまで落ち込んだ。さらに大腸のCT画像から憩室炎が起きていることも分かり、抗がん剤の継続は無理だと中止することになった。
1週間の入院で、何とか仕事に復帰できるまで回復した。「標準治療と言っても、そこから外れるケースもあり、腫瘍内科医によるきめ細かい対応が必要だと思い知らされた。人生で最も過酷な1週間だった」
3週目には、副作用で体中の毛が抜け始めた。数カ月辛抱すれば、元の通りになることは分かっていたし、抜けたまつ毛が目に入る痛みなどはあったが、頭髪はかつらでしのげば良いと思っていた。しかし、どうしても他人の見た目を意識してしまう。かつらを付けている人がすぐ分かるようになったことは、患者に共感できるという点ではメリットになった。また、自費の遺伝子検査はもちろんのこと、かつら代を含めて、予想以上に、がん治療にはお金がかかることも痛感した。
化学療法を初めてから4週間後、最寄りの大学病院で乳房温存手術を受けた。術中の迅速病理検査で切除断端にがん細胞が見つかったため、追加切除が行われた。さらに、センチネルリンパ節生検では、直径1mm以下ながらリンパ節への転移も判明した。入院期間は5日で、退院翌日から職場に復帰した。
部下である教室員達には、自分が乳がんを患っていることを伝えていた。2回の入院はいずれもごく短期間だったが、診療日には代診をしてもらう必要もあった。臨床経験を積み、がんという病態を理解している医師であれば、冷静に受け止めるだろう。しかし、学生達には、がんだと告げていない。まだ、医学知識のレベルが不十分なところには動揺を与えまいという配慮からだ。
退院後、補助化学療法としてカペシタビン、ホルモン療法としてアロマターゼ阻害薬の内服が始まった。カペシタビンの副作用には、赤みなどの皮膚症状が出る「手足症候群」があり、生命に関わるようなものではないが、生活の質(QOL)を低下させる。薬に弱い唐澤は、1週間の服薬を終えた直後から、手指をクリームでケアしても皮が剥けてしまい、パソコンのキーボードを打つにも痛みに悩まされるようになった。家事も手袋をはめなくてはできない。休薬の1週間が明ける頃にようやく回復するということを繰り返している。これが2年間続くことになる。
教科書では得られない診療に生かせる知識
日本癌治療学会では、手足症候群のマニュアルを作成しているが、身をもって体験した唐澤はその内容が全く不十分だと感じた。そこで自ら志願して、改訂の委員を務めている。
一方のホルモン療法は、抗がん剤に比べて、比較的副作用が少ない治療として知られるが、服薬後は、これまで経験したことのない疲労感に襲われた。こちらは薬を切り替えて継続中だ。
乳がんは女性の10人に1人が罹患するがんで、ステージ1であれば5年相対生存率は99%以上、ステージ2でも95%以上である。これらの補助療法が、その確率を上昇させるとしてもごくわずかだ。そこで、副作用がつらいと感じれば、数日間休薬してみるなど、柔軟に対応するようにしている。
患者にはあえて自分のがんについて伝えることはしないが、「私と同じ薬飲んでいますね」と見抜かれて、親近感を感じてもらえる場合もある。専門医でありながら、自らがんになって初めて分かったことは数多くある。教科書だけでは決して得られない、診療にフィードバックできる知識だ。
まず、自覚症状は、自分にしか分からないということ。特に痛みについて、医師は、検査して異常がなければ、「痛みがあるはずはないから大丈夫」と考えがちだ。しかし、実際に患者は痛みを抱えており、医師はもっと謙虚に患者の言葉に耳を傾けるべきだとの思いを強くした。
また、がんを特別視する日本の風潮には不満がある。日本人の2人に1人ががんに罹る。自分のように、治療しながら仕事をしている人も大勢いるし、もっと死亡率の高い病気はたくさんある。「がんは、特別な病気ではない。小学生から、自分の体や病気について、もっと実質的なことを学ぶべき。保健体育の教育課程に組み込んだ方がいい」。
2018年4月からは医学部長に就任し、多忙さにも拍車が掛かっているが、誠心誠意取り組んでいる。がん体験は確実に人生をステップアップさせている。「医師は病気になってみないと駄目。がん治療医が、がんになるのは決して悪いことばかりではないと、心から思っている」(敬称略)
【聞き手・構成/ジャーナリスト・塚崎朝子】


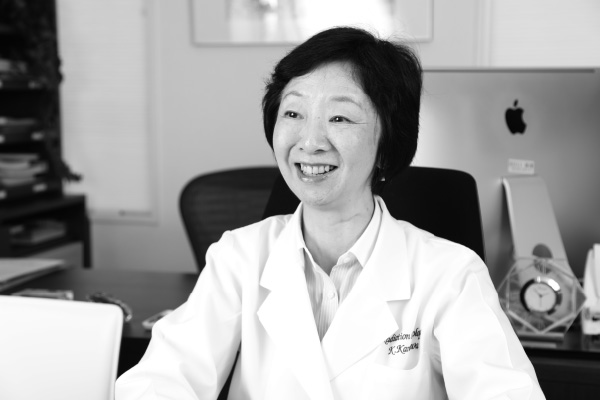

LEAVE A REPLY