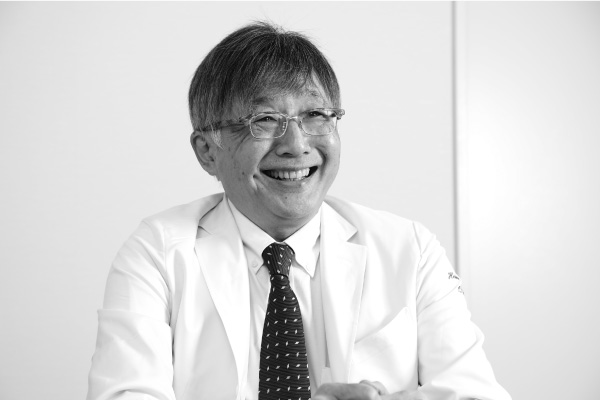
髙橋 修(たかはし・おさむ)1953年東京都生まれ。千葉大医学部卒業。同学部附属病院第一外科、住友重機健保組合浦賀病院外科医長、平和病院外科医長、同病院理事・副院長などを経て、2000年同病院理事長・院長(17年名誉院長)。16年横浜市立大学臨床教授。
医療法人平和会
平和病院(神奈川県横浜市)理事長
髙橋修/㊤
「がんは人生のスケジュールを全く狂わせてしまう。この先、こうしようと思っていたのが、出来るかどうか分からなくなる」。2004年、理事長・院長になって4年目、51歳の働き盛りで肺がんを発症し、13年が経過しても、がんの闘病は、人生で最重量級の出来事だ。
医師は、体が資本。40歳を過ぎてから毎年、1991年に消化器外科の医長として平和病院に赴任してからは自院で、年1回定期的にCT検査を受けていた。当時は紙カルテ、検査のオーダリングも紙で、例年は腹部だけを丸で囲んでいたのが、その年は、なぜか胸部も含めていた。
定期検査の撮像写真に疑惑の陰影
画像検査の結果は、放射線科の専門医が読影して所見を記す。今年も何もないだろうと高をくくってはいたが、早く所見を見たい思いにも駆られる。所見の文章はソフトだったが、内容は衝撃的だった。「悪性を否定する根拠はない」。撮像写真を見ると、胸部に白い陰影があった。大きくはなかったが、正常ではない。自覚症状はなかった。30代頃まで飲酒時に2〜3本たばこを吸うことはあったが、喫煙歴は浅かった。
自分のこととなると、医師らしくない楽観論に逃げ込みかけた。「大きな病巣でない。1カ月後に検査したら、消えているのではないか」。一方で、居ても立ってもいられず、仲間の医師達に相談した。千葉大学の後輩である私大生理学教授は、言葉を濁した。日産厚生会玉川病院の気胸センターには、千葉大の1年後輩の栗原正利がおり、勧められて来院すると、病状が容易ならざるものであることを念押しされた。
そこで、気管支鏡検査をしてもらうことにした。粘膜が赤味を帯びていた個所から細胞を採取したが、悪性細胞は見つからなかった。しかし、不気味なCT画像が依然としてそこにあった。
「がんかもしれない」と思った時に、髙橋の胸に去来したのは、高校時代に他界した父のことだ。両親は共に勤務医で、自分と同じ消化器外科医だった父は、武蔵野赤十字病院副院長だった。髙橋が小学校低学年の頃から胃の肉腫を患い、闘病しながら仕事を続けていた。父と遊んだ経験はほとんどない。ただ、執刀する前日の父がトレーシングペーパーに解剖図を丁寧に写し取って手術を予習していた姿が記憶にある。
父の時代には、がんを告知することは一般的ではなかった。専門医である父が、自分のX線写真から病名を見抜いてしまうことを避けるため、別の患者の画像に父の名が付け替えられていたと、後から聞かされた。胃潰瘍だと偽って何度か手術をしたが、父は帰らぬ人となった。
父の死で据えた「三つの目標」
髙橋が高校2年の年、8歳下の妹は小学生だった。父ががんで亡くなった時、髙橋は三つの目標を据えた。母親より絶対に先に死んではならない、自分が父を亡くした歳(17歳)に息子がなるまでは生きしよう、そして、父の寿命が尽きた55歳を超えて生きよう──。
しかし、黄信号が灯った。がんであれば、父と似た運命を辿るかもしれない。高橋の娘は15歳、息子は9歳だった。母は耳鼻科医だったので、父亡き後の生活にも家族は苦労することなく、自分は医学部に進ませてもらえた。一方、高橋の妻は元看護師だが、長らく仕事に就いていない。望む教育を子供達に受けさせられるだろうか。
3カ月後に病巣が広がっていないという保証はない。栗橋に「今なら、負担が小さい胸腔鏡で出来る」と告げられたことにも、背中を押された。妻、そして現役の耳鼻科医だった母に、「がんらしいから手術を受ける。病理診断で何もなければ、それでハッピーだから」と伝えた。限りなくグレーな状態に、決着を付けたかった。
診断を付けてくれた栗原に執刀を委ねかったが、感情が入るから出来ないと固辞された。その代わり、“自分が手術を受ける時に頼みたい第一人者”として、国立病院機構神奈川病院(秦野市)の加勢田靜を紹介された。理事長の立場で、近隣の病院に入り、余計な憶測や気遣いを生じさせるのは避けたかったので、程よい距離感だと思えた。病院の幹部会で病状を率直に語り、イントラネットの掲示板で病気療養する旨を職員達に伝えた。
家庭内には、自分の想像以上に重苦しい空気が漂っていた。高橋は自分のことで精一杯で、家族のことまで気遣う余裕はなかった。「明日入院するの? がんじゃないの?」の娘の一言に、不意を突かれ「そうかもな」と答えた。しばらくの沈黙の後、娘は、「なぜ知らせてくれなかったの」と号泣した。つられて、息子も大泣きした。
手術前日、妻と連れ立って1時間、乗り付けない電車に揺られた。「ああ、明日手術をするのは、この車内で俺だけだろうな。最も不幸な人間だ」。とことん卑屈になった。手術は、子供時代の小指の骨折を除けば初めての体験だ。
ごく早期の胸腔鏡下手術で、手術時間は1時間ほどと聞かされていた。術中に、採取した実際の組織を迅速病理診断にかけて、がんであれば周辺のリンパ節郭清まで念入りに行う手はずだった。ところが、2時間が過ぎ、3時間が過ぎても、手術が終わる気配はなかった。麻酔をかけられたままの髙橋は意識がないため、その異常事態を知る由もないのだが、待合室の妻と母は青ざめていた。
5時間が経つ頃、やっと手術台から解放された。実は、迅速細胞診を行うための機械が故障してしまい、がんの確定診断を付けられなかったと、麻酔から覚醒した後に報告を受けた。それでも、がんであることを前提として、患部のある右肺下葉を多めに切除し、リンパ節も郭清した。肺を出すための傷跡は予想以上に大きかったが、1週間経って退院の日を迎えた。術後の抗がん剤治療については、主治医から勧められなかった。必要ないのか聞いたところ、「様子を見ましょう」と言われ、結局、抗がん剤治療はしていない。
病理診断の結果は出ておらず、白黒付かないままの退院だった。抜糸は先だったが、傷跡が大きいので、その処置は自院でしてもらうことにした。外科に「これから行くから、処置を頼む」と告げた。
退院後の最初の外来でも、病理診断の結果は出ておらず、それから3日、病院からの書面と電話で伝えられた。ステージ1aの正真正銘の肺がんだったが、リンパ節にも胸膜にも転移は認められず、“取り切れた”という診断結果だった。 (敬称略)
【聞き手・構成/ジャーナリスト・塚崎朝子】




LEAVE A REPLY