排泄予測、介護ケアのアドバイスから 医療・介護の情報共有、過剰医療の把握まで
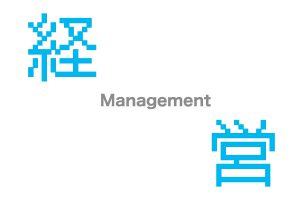 地域包括ケアシステムで推進されている在宅医療。医療・介護間のスムーズな連携を実現するには、患者情報の共有ネットワークの構築や、効率的な医療サービスの提供などが求められる。その要となるのがICT(情報技術)の活用だ。その現状と展望を紹介するシンポジウム「『在宅医療×テクノロジー』の“今”をつかみ“未来”をつくる〜超高齢社会を支える在宅医療にイノベーションは起こせるか?〜」が4月22日、医師専用サイトを運営するメドピアの主催で、都内で開かれた。
地域包括ケアシステムで推進されている在宅医療。医療・介護間のスムーズな連携を実現するには、患者情報の共有ネットワークの構築や、効率的な医療サービスの提供などが求められる。その要となるのがICT(情報技術)の活用だ。その現状と展望を紹介するシンポジウム「『在宅医療×テクノロジー』の“今”をつかみ“未来”をつくる〜超高齢社会を支える在宅医療にイノベーションは起こせるか?〜」が4月22日、医師専用サイトを運営するメドピアの主催で、都内で開かれた。
AIがケアの良しあしを自動判定
最初に登壇したのは、元リクルートAI研究所所長で、静岡大教授らが設立したITベンチャー「デジタルセンセーション」取締役COO(最高執行責任者)の石山洸氏。「AI(人工知能)はデータを学習することで様々な予測を可能にし、その予測内容に合わせて自動的にオペレーション出来るようになる。また、AIは自動化が難しい領域にも活用出来る。それが介護の現場だ」と述べる。
具体例として挙げたのが、介護作業の様子を動画に撮ってAIのサーバに送ると、動作のポイントに赤点でチェックが入り、介護者にフィードバックされるシステム。石山氏は「AIが介護者の習熟をサポートするのだが、電子レンジ並みに誰でも簡単に扱えるため、『レンジでチンする人工知能』」と言っている」とユーモアを交えて話す。
また、石山氏は「ユマニチュード®」と呼ぶ認知症ケアの手法に注目する。これは介護において効果的な見つめ方や触れ方などの動作を指す。通常介護とユマニチュードの映像や脳の状態に関するデータをAIで調べると、ユマニチュードを適用した時間は被介護者の脳が活性化していた。石山氏はAIがケアの良しあしを自動判定、より良いケアを介護者に教えるシステム作りを目指している。
「領域間が連携する場合、AIが中核となって様々なデータを集めて因果関係を分析出来る。ビッグデータの活用には可能性がある」と述べた。
次に、トリプル・ダブリュー・ジャパン代表取締役の中西敦士氏が、自社で開発した排泄予知ウェアラブル「DFree」について述べた。DFreeは経済産業省主催の「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2017」でグランプリを獲得している。
DFreeは、被介護者の排泄のタイミングを予測するデバイス。恥骨の上2㎝に付ける超音波センサーが膀胱の膨らみや萎みをとらえて情報をクラウドに上げ、あと何分で排泄するかをスマートデバイスで知らせるというもの。
実証実験では、DFreeの装着により、被介護者の昼間のトイレ誘導回数が22回から4回に減ったり、被介護者1人当たりの介護時間が30%(人件費換算で月額3万円)減少したり、おむつやパッドの使用量が減少し、購入費用が平均1万3000円から7000円へと半減したという。
中西氏は「現在は30カ国以上から『すぐに使いたい』という問い合わせがある」とニーズの大きさを話す。そして、「介護には主なケアとして排泄、入浴、食事があるが、排泄ケアはとても大事であるものの、難しい。タイミングが分かりづらく、認知症でそれを伝えられない人もいる」と言う。
中西氏は「病院や施設から家に帰ると、生活の質は一気に低下する。排泄環境が悪くなると、悪臭で人が寄り付かなくなる。生活の質を自治体、家族、介護者、通信会社などと下支え出来ればと考えている。排泄以外にも体内の変化を検知することで、様々な生体状態を予測するサービスに繋げていきたい」と今後の展望を述べた。
現場のニーズにマッチしていない面も
続いて、宮城県と首都圏で在宅診療所を開業、地域医療に取り組む医療法人社団やまと理事長の佑輔氏が医療現場の実状について話した。田上氏は出身の東京大学医学部附属病院の医師だったが、東日本大震災の被災地でのボランティア活動を機に宮城県登米市と都内に在宅診療所を設立した。
田上氏は「テクノロジーが医療を追い越している。デバイスやサービスなどと言われるが、いざ使おうとすると、なかなか使えない。使える人が少ないし、テクノロジーを使わなければいけないほど、現場は困っていない気がする」と需給のミスマッチを指摘する。
「医療におけるAIは、情報量が多ければいいというものではない。精度が求められる。他の領域なら費用対効果やビジネスの継続性が大事だろうが、医療は個々の人体に対する治療で成果を出さなければならない」と話す。
そして、宮城県と首都圏の診療所で医師の工面をしているだけに、テクノロジーは医療者の働き方や、医師という医療資源の最適化に活用できる点を指摘する。
田上氏は「在宅診療と言っても、家族の在り方が異なる地方と都市では、アプローチも異なる。宮城では医療と介護と生活を見る。どう食べて、どう排泄して、どう寝て、どう動くかを見て、何が必要かを判断する。生活まで見るとなると、顔の見える関係が重要となる」と述べ、「これからの医療・介護は全員参加の時代。患者、家族、医療者、介護者、そしてテクノロジーも関与出来る地域を作ることを考えている」と述べた。
最後に、厚生労働省医系技官として医療政策づくりに取り組み、現在は日本医療政策機構理事で、「みいクリニック代々木」院長として医療の現場にも関わる宮田俊男氏が登壇した。
宮田氏は、在宅医療を行っている自院で行った遠隔医療モニタリングの例を挙げ、「患者がタブレットを利用して入力したバイタルデータなどを、医師が医療機関や外出先で参照することで、問診や診察の効率化を図れる」と述べた。
また、国民個人レベルでのポータルな情報基盤を整備することで、国民がOTC薬(大衆薬)を活用したセルフメディケーション(軽度な身体の不調は自分で手当てすること)を支援し、ICTの活用で薬剤費を抑制する視点を説明した。
宮田氏は「テクノロジーを入れていかないと、地域包括ケアの実現は難しい。在宅の現場では様々な情報を関係付けなければいけないからだ。キーワードは健康寿命をいかに伸ばすか。人間は死ぬまでに約3000万円の医療費を使うというが、そのうち半分以上を70歳以上になってから使っている。ここに、どうメスを入れるかだ」と問題提起した。
また、「健康保険法などの改正で、国保加入者の健康状態をスコアリング出来るようになった。それを活用して、国は生活支援や介護予防を推し進めようとしている。来年度は診療報酬と介護報酬の同時改定がある。6年に1度のことで、官僚目線からすると、医療と介護を連携させる大きなチャンス」と言う。
先進事例として埼玉県を挙げ、健康医療データを自治体が把握して、健康に不安のある市民には医療機関の受診を勧めているという。「マイナンバーが普及すれば、医療等ID、医療介護のデータを乗せようという話が出ている。それによって、医療の質の改善と過剰医療の削減を目指している」と話した。


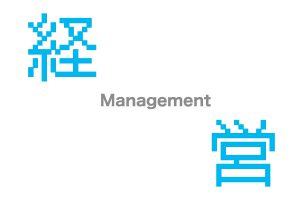
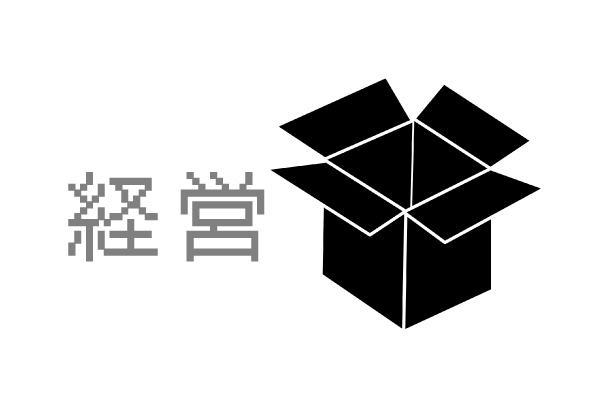
LEAVE A REPLY