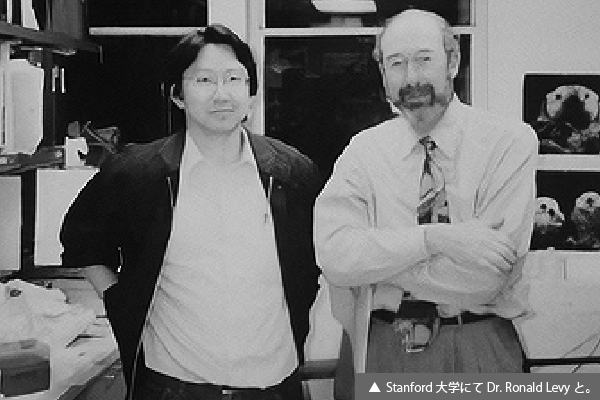
塚本 眞(つかもと•まこと)
医療法人直源会 相模原南病院 相模原南病院介護医療院 院長
留学先: スタンフォード大学メディカルセンター 腫瘍科(1997年4月〜99年3月)アメリカ国立衛生研究所 免疫研究室(99年4月〜2002年3月)
苦しかったStanfordの2年間
私は1997年に米国Stanford大学、99年にアメリカ国立衛生研究所(NIH:National Institutes of Health)に留学しました。
一般には留学は人生の最盛期ですが、私にとってStanfordの2年間は苦労ばかりの黒歴史だった、と今まで思っていました。教授であるDr. Ronald Levyは、B細胞リンパ腫の革新的な抗体薬Rituximabの開発者です。本薬剤は後に癌領域のみならず、膨大な種類の抗体治療薬の爆発的開発の端緒でありノーベル賞級の成果です。私はRituximabが世に出た97年に渡米し、その標的分子CD20への免疫誘導を研究しました。今振り返れば、自分は幸運であり期待されていたと思いますが、当時はそんな風に思えませんでした。
癌免疫の研究へ
学生時代から、フレミングのペニシリン発見や丸山ワクチンなど癌の治療と免疫の研究に興味がありました。在籍した千葉大学医学部第2内科の吉田尚教授に相談し、国立がんセンター研究所分子腫瘍学部(寺田雅昭所長、後の総長)で研究の機会を頂きました。そこでは当時流行りの遺伝子治療の研究に着手し、リポソーム含有遺伝子を妊娠マウス母体へ静脈注射し胎仔への遺伝子導入に成功し、95年Nature Genetics誌に発表しました。
この論文の反響は大きく、イタリアと米国のGordon Research Conferencesに招待される程で、寺田所長は私に研究続行を期待しましたが、私は癌免疫を研究したいと思いました。
当時の癌研究と言えば分子生物学であり、癌の免疫療法など異端で、91年にBoonが癌抗原を発見したものの、がんセンターに免疫研究の場はありませんでした。今でこそ癌治療における免疫の重要性を疑う者はいませんが、90年代に本流の癌研究者から後ろ指を指され、自分のやっていることは本当に意味があるのだろうか、と不安を抱きながら研究を行って来た者から見れば隔世の感があります。
Levy研究室にて
GM-CSF(顆粒状マクロファージコロニー刺激因子)を付けた抗体をマウスリンパ腫治療に用いた興味深い論文をNature誌で読み、著者のDr. Levyに留学希望の手紙を出して受け入れられました。Levy研究室については、過去在籍した先生や留学した先輩から「Stanfordは天国みたいな所だ」と聞いていました。
Levyは無駄が嫌いで“Is it worth to do? It’s time consuming. Money spending.”とよく口にしていました。彼は徹底したユダヤ人臨床医だったと思います。Levy研究室では多くの貴重な出会いがありました。特に現在Foggia大学教授のArcangelo Lisoは、人懐っこいイタリア人で、彼の友人達も皆温かくとても癒されました。
私が所属したLevy研究室は、彼のwifeであるShoshanaの研究室と部屋と機器を共用し、技術員含め総勢15人位と小規模でした。機器は古く遠心機は70年代製で音がうるさくてかないませんでした。研究テーマはLevyが研究費を獲得した課題を各々に割り当て、私のテーマはマウスとヒトのCD20を発現するbaculovirusやadenovirusやDNAワクチンを作成してマウスに投与し、CD20に対する能動免疫を誘導する、というものでした。結果は自己抗原であるCD20への能動免疫が殆ど得られず、努力が実りませんでした。免疫学が分かるにつれ暗い予感がしたものの、他の事を始める資金は無さそうでした。
当時のLevy研究室は国立がんセンター研究所分子腫瘍学部に比べみすぼらしく、70年代製の大音量遠心機が壊れた時、やれやれこれで新品が入ると喜んでいたら、しばらくして同じ遠心機を修理して持って来たので心底がっかりしました。分子腫瘍学部は資金豊富で機器も最新でしたが、Levy研究室はそうではなく、免疫研究で頻用のFACS装置は1台で、扱える技師は1人のためいちいち予約が必要でした。後にLevy研究室を逃げ出してNIHに行きましたが、NIHでは24時間自分でFACS装置を使え、研究環境も雲泥の差でした。Levy研究室では実験中にいきなり誰かが歌い出し誕生日サプライズが始まったり、太った掃除のおばさんが集中している時に急に話しかけてきたり、落ち着いて研究できる環境ではありませんでした。帰国後、東京大学血液内科出身で有隣病院院長の橋本康男先生から「Levyの所は論文が出ない事で有名だよ。ハハハハ」と言われました。
NIHのGermain研究室へ
渡米後間もない5月、Stanford大学の脇道で停車中に追突されむち打ちになりました。首が痛み街の整形外科を訪れましたが、受付で保険証を見せるとこの保険では診られないと門前払いを食らい、適切な初期治療が受けられませんでした。このことで私は日本の医療制度と国民皆保険制度の熱烈な信奉者となりました。
Levy研究室では、むち打ちと事故後対応をしながらの留学生活となりました。西海岸は雨が少なく殺伐とした風景が多く、肝心の研究成果もぱっとせず鬱々とした毎日でした。そんな中で迎えた98年に研究会で東海岸を訪れ、久々にこんもりした森を見る機会に恵まれ心豊かになりました。その後思いがけず日本学術振興会から海外特別研究員採用の通知が来たので、この機に東海岸に移り研究を続けるべく八方手を尽くし、千葉大学免疫研究室の齊藤隆教授の助けでNIHのGermain研究室に移ることになりました。
Ronald LevyとRituximab〜Stanfordを振り返って
Dr. Levyは自らベンチャーを興しそこでRituximabを開発しましたが、私は今まで彼が中心的な開発者だとは思わず、どこかの企業が開発し、臨床試験を行って名を挙げただけだと思っていました。彼がRituximabについて語ったのは研究開始の時だけで、自慢することもありませんでした。Levyのポスドクは皆成果が今一つでしたが、一方でバースデイサプライズをしたり、皆を家に招いたりと不満をそらす努力を怠りませんでした。
Levyはいい人で、研究室を離れる時には一緒に写真を撮り、"Keep in touch.”と言ってくれました。LevyのRituximab開発の成功は多様な人々との関係性の中から生まれたと思います。Stanford大学の研究室は彼のほんの一部で、ベッドサイドで患者を診る日常があり、周辺のシリコンバレーがベンチャーを創始させ、多くの人々との議論の中でRituximabが生まれたのだと思います。彼1人では、今も患者別に作成する抗イディオタイプ抗体療法にこだわり、Rituximab開発にまでは至らなかったと思います。
NIHでは、ビザの期限の為に志半ばで帰国したので、当時はStanfordの2年間が無駄に思えました。しかし、あれから20年以上が経ち、Dr. Levyの業績の偉大さが客観的に理解できる今となっては、自分が理想としていた「研究する医師」であるRonald Levyと人生の一時期を共にしたことは夢のようです。諸先輩に聞いた「Stanfordは天国みたいな所だ」という言葉を思い出すと共に、いつか再訪する日を持ち望んでいます。




LEAVE A REPLY