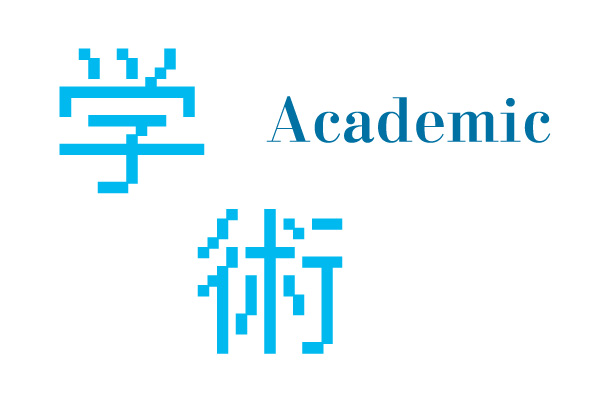
患者主体の医療への転換や精密医療の大衆化を目標に
医療分野でのDX(デジタルトランスフォーメーション)が議論される様になり、国も電子カルテの導入や医療情報のデータベース化の推進に力を入れている。しかし、日本は他の分野と同様、医療分野でもデジタル化やIT化が他の先進国に比べて遅れており、どのようにしてデジタル化を進めるかという議論ばかりで、DXによってどのような医療環境が実現するのかといった将来像の議論が殆ど行われていないのが実情だ。その間、米国等の先進国では、ITによって医療環境は大きく変化している。
感染症対策の最前線で「鉛筆書きにFAX」
実際に新型コロナウイルス対策を検討する現場でも日本のIT活用の遅れが露呈し、迅速な対応の妨げになったという。依然として医療事務の効率化や利便性の向上といった観点のみで語られがちな医療DXの推進の為、具体的な医療の未来像が求められている。
国の医療DX推進本部では内閣官房や総務省、厚生労働省、デジタル庁等が医療DXの基盤整備に関する議論を進めているが、テーマは全国医療情報プラットフォームや電子カルテの標準化、診療報酬改定への対応等が中心となっている。医療DX後の将来像について、マイナンバーカードの活用やパーソナルヘルスレコード(PHR)を用いた民間サービスの展開等も挙げられているが、具体的な議論が進んでいるとは言い難い。
こうした中、特定非営利活動法人地域医療・介護研究会JAPAN(LMC)が2023年1月21日に京都で開催した第9回研究集会で、医療DXに詳しい東京医科歯科大学の田中博名誉教授が講演。医療DX先進国で進む医療現場の変化について紹介した。
研究集会では、田中名誉教授に先立って、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の会長を務めた尾身茂氏が講演。コロナ対策を検討する中で感じた日本のIT化、デジタル化の遅れについて語った。
尾身氏によると、日本で新型ウイルス感染症患者が出た当初、大学教授等の専門家は厚生労働省の会議室に集められ、IT機器もデータも不十分な状態の中、手弁当で検討に当たった。スタッフの人員も十分でなく、教授らは自分の教室の研究生や大学の学生を集め、普段は大学の運動部の部室の様な場所でデータの分析を行っていたという。
一方、隣国の韓国ではIT機器やweb会議システム等が揃った緊急対策センターで対策に当たっており、態勢には雲泥の差が有った。韓国はかつてのSARSやMARSといった感染症で痛手を受けており、感染症対策でもIT化を進めた結果、日本よりも優れた体制を構築している。尾身氏は「こうした体制の違いが、日本のコロナ対策の課題を象徴している」と指摘。「日本はAIどころか、IT化も不十分で、紙に鉛筆でデータを書き込みFAXで送っていた。これが海外との大きな違いだ」と現状を嘆いた。
実際、感染初期の段階では、保健所の職員が患者らから聞き取りをしているにも拘わらず、他の自治体と情報共有がされず、厚労省にも情報が届かないという状況が続いた。その結果、感染症の研究者は新聞やテレビで報道される情報を収集し、分析するという手法を余儀なくされた。こうした状況について尾身氏は「感染症との戦いで最大の武器はデータだ」とIT環境の整備の重要性を訴えた。
ITやAIの活用で患者主体への医療へ転換
田中名誉教授の講演では「医療DX —現状と将来—」と題して、世界的な医療DXの流れや現状が紹介された。田中氏は、ウェアラブルセンサーによる生理データの蓄積や、医療情報の電子化によるリアルワールドデータの大量集積によってビッグデータ医療の時代が到来したと指摘。医療界に於けるビッグデータやAIの活用は一時的なブームではなく、抗生物質の登場や分子治療医学の発展に続く医療の第3次革命であり、医療の在り方や医学研究の進め方を根本的に変えて行くとした。
具体的な流れとして、田中氏は患者中心的医療から患者主体の医療(Person-Centred Care:PCC)への転換を挙げた。米国では患者自身がデータや情報を収集するという運動が広がり、病気の治療の場が病院ではなく、日常生活圏に移りつつあるという。PCCには、ウェアラブルセンサー等を活用して患者本人が自分のデータを収集する「モバイルヘルス」と、患者らがWeb上にコミュニティを作り病気や治療法に関する情報を集める「患者集団SNS」という2つの流れが有る。Apple Watchといったウェアラブル端末の登場で、誰でも気軽に心拍数や血圧等のデータを連続的に計測出来る様になったが、日々の生活の記録や計測データを健康管理に活用しようという取り組みは意外に古く、1970年代からクオンティファイドセルフ運動として米国西海岸を中心に広まっていた。それが今は治療医学へと発展し、情報端末を利用した「情報による治療」が医療現場に取り入れられる迄になった。
数十万人参加の患者コミュニティSNSも誕生
情報端末の活用は特に生活習慣病に効果が有るとされ、米WellDoc社が開発した糖尿病患者向けの自己管理アプリ「BlueStar」が有名だ。糖尿病患者の血糖値や血圧、服薬状況、体調等を記録すれば、収集したデータをAIが解析するアプリで、患者はリアルタイムで自分に合ったアドバイスを得られる他、データは主治医とも共有される。2010年にはFDA(米食品医薬品局)から医療機器としての承認も受けている。他にも米国では多くのデジタルアプリがFDAの承認を受けており、糖尿病等の慢性疾患の他、ADHDの改善等メンタルヘルス患者向けのアプリも開発されている。
もう1つの流れである患者集団SNSは、患者や家族らによるSNS上のコミュニティで、代表的なものとして米国のPatientsLikeMe(PLM)が挙げられる。PLMはもともと3人兄弟が作ったALS患者のコミュニティで、兄弟の1人がALSを発症した為、病気の進行を遅らせようと情報収集を始めたのが切っ掛けだった。最初は個人的に情報を収集するだけだったが、05年に多くのALS患者と情報を共有しようとコミュニティを立ち上げた。PLMは急速に拡大し、今はALSに留まらず2800以上の疾患を持つ85万人以上が参加する世界最大の患者コミュニティとなり、デジタル健康管理プラットフォームともなっている。収集された膨大なデータは研究にも活用され、100本以上の論文も発表されている。
こうした患者コミュニティは米国で患者の支持を集め、大学や公的機関のデータベースよりもコミュニティのデータベースの方が信頼される傾向も見られるようになった。
地域でも受けられる精密医療の実現を目指せ
PCCは、従来の通院治療よりも効果的だとする研究成果も発表されている。月1回、従来の通院治療を受けた高血圧患者よりもセルフモニタリングで治療を行った患者の方が血圧低下の効果が良好だったという報告も有る。
更に、電子カルテを活用した治療も米国では進んでおり、がん治療に特化したゲノムカルテである「がん医療用電子カルテ」も使われている。米国にはCommunity Oncologyと呼ばれるがん治療体制が有り、専門医が居る大病院から離れた地域では、診療所に居る地域腫瘍医が大病院や医療関連企業の支援を受けながら、大病院に通えない患者の治療に当たっている。
この様に、地域の小さな医療機関の医師であっても、電子カルテを基に専門病院からのサポートを受ければ、最先端のがん治療が可能になり、患者のカルテ情報はがん治療のリアルワールドデータとして蓄積される事になる。
田中氏はこうした米国の先進事例を紹介した上で、日本でもITやデジタル技術の活用によって地域の診療所でも最先端の医療が受けられる精密医療の大衆化が、DXの目標ではないかと講演を締め括った。



LEAVE A REPLY