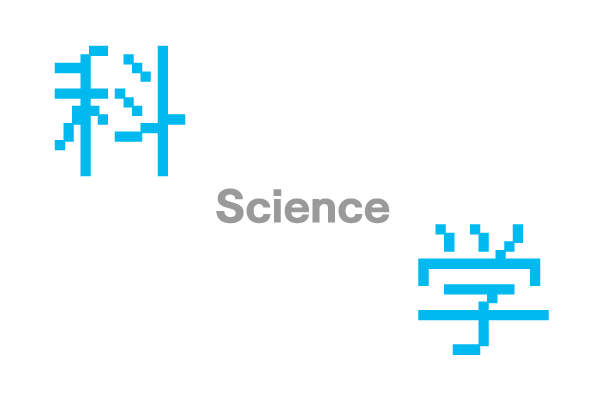
難治性潰瘍治療への応用・展開の第一歩
2022年7月、東京医科歯科大学は、炎症性腸疾患(IBD)の1つである潰瘍性大腸炎の難治性潰瘍の修復を目指して、自家腸上皮オルガノイド移植治療の第1例目を実施した事を発表した。同大は、潰瘍性大腸炎・クローン病先端医療センター(IBDセンター)を擁する日本のIBD治療のメッカである。「オルガノイド」とは、試験管の中で幹細胞から作製する、言わばミニチュアの臓器で、立体的な構造の細胞が形成される。この治療は、IBDに対してオルガノイドを用いた世界初の再生医療(移植医療)として、難治性潰瘍を伴う他の消化管難病(クローン病等)への応用・展開が期待されている。
現代人に急増する炎症性腸疾患(IBD)
IBDは、アレルギー疾患と同様、現代人に急増している。潰瘍性大腸炎とクローン病という病気を併せた呼称で、日本では14年時点で潰瘍性大腸炎が18万人、クローン病が4万人を超え、合計で約22万人以上と推計されている。年間の新規発症者数は、潰瘍性大腸炎が1万人を超え、2000年頃と比べ2倍以上に増加している。
潰瘍性大腸炎、クローン病では、腸や大腸等の消化管の粘膜にびらん(潰瘍)を生じる。主たる症状に下痢や血便、腹痛、発熱、貧血等があり、多様な合併症が発現する事もある。寛解と再燃を繰り返し、厚生労働省の特定疾患(難病)にも指定されている。IBDは自己免疫疾患ではないが、免疫系の過剰な反応が原因だとされている。
人体で最大の免疫器官である腸は、食物や腸内細菌等生体に有益なものを含めて、常時様々な抗原に曝されている為、免疫系は有益な異物に過度に反応する事がない様、制御されている。だがIBDは、自己の腸内細菌に対しても過剰な反応を起こしてしまう免疫系の異常によって発症するのではないかと考えられている。
現在の所IBDは、免疫調整薬、ステロイド剤、抗TNF-α抗体に代表される抗体医薬(生物学的製剤)等を用いて免疫系を抑制する事で症状を抑えられるケースが大半である。かつてのIBD治療では、例えば下痢等、症状が出現してから対症的に投薬がなされていた。しかしIBDは慢性疾患であり、粘膜レベルで炎症が認められなくなる「粘膜治癒」の状態を維持し続けなくてはならない。高血圧患者が降圧薬を使用し続けるのと同じく、IBDの患者も断薬や減薬する事なく服薬を続ける事が重要なのである。現在は薬物の選択肢も広がり、09年にメサラジン(アサコール®)が国内でも承認され、多様なレベルでの腸管免疫応答を選択的に調節出来る様になった。
進化し、多様化する病症評価と治療法
一方で、内視鏡技術の発展と普及もIBD治療の進歩に貢献している。粘膜における炎症の状態が臨床症状とは乖離している事や、粘膜治癒が再燃率や手術率の低下という長期予後の改善と相関する事が明らかになった。大腸や小腸の粘膜治癒を、内視鏡、カプセル内視鏡、MRエンテログラフィー等の検査を駆使し評価する事が、IBDの治療目標として認識される様になったのだ。欧米では診断時にしか内視鏡検査を実施しないが、日本では頻繁に検査を行って評価する事が粘膜治癒を目指す切っ掛けとなったとされる。
又、IBD治療には外科手術もあり、重症者に対しては、根治術として米国等で一時盛んに行われていた。潰瘍を生じる大腸を摘出し、肛門を一部残して小腸と繋ぐもので、大腸が無くなれば潰瘍が起きる恐れはない。但し1日の排便が頻回となり、患者が不自由を強いられる事から、現在は米国でも薬物治療が全盛となっている。
一方、薬物療法によっても完全な粘膜治癒に至らず、難治潰瘍病変が残存する症例は少なからずあり、国内で約1万人いるとされる。完全寛解が難しいという点ではIBDは難治疾患であり、新規治療法の開発が待望されていた。東京医科歯科大の今回の治療は、IBD患者から採取した腸上皮幹細胞を体外で培養・増殖させ、オルガノイドを作製し、内視鏡を介して大腸の粘膜に移植する事で粘膜上皮の再生を促す。
この治療は、10年に及ぶ研究成果が結実したものだ。同大では先ず、体外で幹細胞を培養する「自家腸上皮オルガノイド」を樹立した。その後、培養腸管上皮オルガノイドの移植により、潰瘍が修復・再生する事を確認した。潰瘍性病変を持つモデルマウスに対し、体外で培養した腸管上皮オルガノイドを肛門から移植すると、オルガノイドがホストの潰瘍部位に生着して上皮組織を再生し、潰瘍治癒が促進される効果が示された。マウスの腸の働きが正常化し、体重が回復したという。この移植細胞は、マウス胎児の小腸オルガノイドや、成体マウスの小腸上皮オルガノイド等、異所の細胞でも有効だった。
この為、ヒトの場合には、IBD患者の健常部位の腸から上皮細胞を採取して、オルガノイドとして増殖させ、患者自身の潰瘍・粘膜傷害部位に供給し、上皮のバリア機能にする事が検討された。自家移植である事から、拒絶反応が起きない利点も大きい。
臨床研究の1例目では、患者の腸から取った組織を約1カ月間培養し、腸の上皮細胞の機能や構造を持つ、直径約0.1〜0.2mmの球状のオルガノイドを作製した。患者の直腸に出来た潰瘍の陥没箇所にこのオルガノイドを移植し、被覆シートで覆った。このシートは、約1週間で体に吸収される生分解性材料である。4週間後と8週間後に安全性を確認する検査を行い、最長1年程度経過を観察する。1年半かけて計8例の実施を目指している。今回の臨床研究の主たる目的である安全性が確認されれば、治療効果を確かめる次の段階に進む予定だ。
期待される機能性腸疾患の克服
余談だが、IBDでは、連続在任期間が歴代最長を達成し、先頃、凶弾に倒れた安倍晋三•元首相が、10代から潰瘍性大腸炎の持病を抱えており、07年9月、更には20年9月にも、その増悪を理由に自ら辞任している。かつてはストレスがIBD発症·悪化のトリガーになるともされていたが、現在では、それは否定され、免疫系の関与が重要になっている。
米国ではジョン·F·ケネディ・第35代アメリカ合衆国大統領が潰瘍性大腸炎を患い、その先代のドワイト·D·アイゼンハワー·第34代大統領はクローン病で2度の手術を受けていた。この為IBDは、“大統領病”等と称される事もある程だが、ありふれた病だと言う事も出来る。腸疾患の原因について明確なエビデンスは無いが、食生活が関与しているとされ、従来から欧米に非常に多かった。IBDや大腸がんは、欧米に比べて日本人には少なかったが、近年は、日本だけでなく韓国や中国でも急増している。米国のIBD患者数は300万人超とされるが、日本は欧州諸国を抜いて、世界第2位の患者数である。
消化器領域の研究と言えば、最近までは胃と肝臓が花形であった。半世紀の間に、B型肝炎ウイルス研究(1976年)、ヘリコバクター・ピロリの発見(2005年)が、ノーベル賞の受賞対象となった。胃がんの原因となるピロリ菌は駆逐されつつあり、ウイルス性肝炎も根治の時代を迎えている。胃がんと肝臓がんは減少傾向にある。消化器分野では、大腸がんと炎症性腸疾患に代表される、機能性腸疾患の時代が到来している。前述した通り、腸は免疫の関与が大きく、リンパ球の約6割、T細胞の8割が存在する等、“第2の脳”とも称される複雑な臓器である事から、克服は一筋縄ではいかない。日本発の治療が、世界の患者に貢献する事を期待したい。



LEAVE A REPLY