
生体ドナーに負担生じるが、遺伝的親子関係は保たれる
子宮移植は、子宮を欠損した不妊女性が出産するための技術で、国内での実施例はまだない。今年7月、日本医学会の検討委員会が条件付きで、子宮移植の実施を容認するとの報告書をまとめた。報告書は実施の条件として、当事者に危険性を十分に説明する事、自由な意思に基づいて移植を実施する事等を挙げている。子宮移植は生殖補助技術であり、その目的は、ドナーから提供された子宮を移植されたレシピエントが妊娠・出産により子どもを得る事である。子宮移植の歴史を振り返り、課題と展望を考察したい。
具体的な手順としては、まず夫婦の受精卵を事前に凍結保存しておく。その後、ドナーから提供された子宮をレシピエントに移植するが、この際卵巣は移植しない。移植後は免疫抑制薬の服用が必須となる。レシピエントの子宮の生着を確認した後、夫婦の受精卵を子宮に戻す胚移植を行う。これで妊娠に至った場合には、厳重に妊娠を管理して帝王切開で出産する事になる。出産後に子宮を摘出すると、一時的な臓器移植で済み、以後は免疫抑制薬を中止出来る。医学的リスクとして、拒絶反応に加え、感染や血栓形成等がある。
子宮移植の適応となるレシピエントは子宮性不妊となった女性で、日本では生殖年齢(20〜40歳)の患者が6万〜7万人いると推定されている。子宮性不妊は大きく先天性と後天性に大別され、先天性のものとして、ロキタンスキー症候群(MRKH症候群)、子宮低形成、子宮奇形等がある。
MRKH症候群は女児の4500人に1人の頻度で見られる。散発性だが、一部の遺伝子異常も報告されている。女性内性器へと発達するミュラー管が発達異常を起こし、子宮が欠損するが、卵巣・卵管は形成されている。
後天的な子宮性不妊には、子宮悪性腫瘍に加え、子宮筋腫や子宮腺筋症等の良性疾患、産後の大量出血等で子宮摘出を余儀なくされたケース、子宮内の高度癒着により妊孕性を失ったケース等がある。若年層における子宮頸がんが増加しており、生殖年齢で子宮を摘出されるケースもある。
ドナーには患者の女性親族を想定
子宮を提供するドナーには生体ドナーと、脳死や心停止に陥った死体ドナーがある。しかし、日本の「臓器の移植に関する法律(臓器移植法)」には子宮に関する規定がなく、脳死判定を受けたドナーからの移植は対象外で、法改正がない限り実施は困難である。
生体ドナーは日本移植学会倫理指針に則り、親族に限定される。すなわち6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者を指し、親族以外の第三者からの臓器提供は原則として許可されていない。これらの背景を踏まえると、国内で子宮移植が臨床応用される場合、ドナーには母親や姉などの親族が想定される。
さて、臨床としての子宮移植は、世界で初めて2000年にサウジアラビアで実施されたが、血栓が形成された事で移植した子宮は摘出された。11年にトルコで行われた子宮移植では、妊娠にまで至ったが初期流産となった。初めて出産にまで至ったのは14年のスウェーデン・ヨーテボリ大学の症例で、17年には米国ベイラー大学でも出産例が報告された。スウェーデンの症例ではドナーの手術時間が10時間近くにも及んだが、米国のチームは子宮静脈に替えて卵巣静脈を活用する術式によって簡略化を図り、これを5時間ほどに短縮した。
ドナーの手術をより安全に非侵襲的に実施するための技術の改善は世界中で進められている。中国ではドナーの負担を軽減するためロボット支援下のドナー手術が行われ、19年には出産に漕ぎ付けている。
セルビアで18年に実施された子宮移植は、一卵性双生児をドナーとレシピエントとしており、免疫抑制薬なしに出産に至った。インドでは同年、世界で初めて腹腔鏡によるドナー手術が行われ、出産が報告されている。これらはいずれも生体ドナーによるものだが、ブラジルでは17年、世界で初めて脳死ドナーからの子宮移植後の出産が報告されている。死体ドナーではドナーのリスクは回避出来るものの、計画的に手術を行えない。臓器虚血に伴う虚血再灌流障害といったデメリットもあるため、海外の子宮移植では生体ドナーからの臓器提供が先行している。
報告書によると、今年3月までに世界16カ国19施設で85例(生体ドナー63例、脳死ドナー22例)の子宮移植が実施され、うち妊娠確認は70例、出産は40例(生体ドナー32例、脳死ドナー8例)である。
日本では09年から、慶應義塾大学において産婦人科の木須伊織氏を中心に研究を行っており、霊長類であるカニクイザルで世界で初めて他家子宮移植後の妊娠が報告された。今回の報告書を受けて、国内初の子宮移植の臨床研究の実施計画を同大学の倫理委員会に申請する方針とされる。先天的に子宮のないロキタンスキー症候群の女性をレシピエントに、ドナーには患者の母親や姉等の親族を想定している。
費用は合計2000万円超
子宮性の不妊に対しては、従来から代理母による懐胎・出産、里親、養子縁組等の適応がされてきた。更に子宮移植が技術的に進歩し、実現可能な医療に近づいた事で、患者の選択肢が増えるものと期待されている。しかし、倫理面を含めて、乗り越えなくてはならない壁がまだいくつもある。例えば、子宮移植は生命に直接関わる移植医療ではないのにもかかわらず、生体ドナーに生じる負担が許容されるかという問題点がある。
子宮が臓器移植法に定められている他の臓器(心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球)と異なるのは、生命に関わる臓器ではないという点だ。このため子宮移植はQOLの向上のための臓器移植だと解釈されている。生命に関わる臓器移植では、時として重篤な合併症や免疫抑制薬の服用に関連するリスクを賭しても、救命のために臓器移植が実施される。
一方、QOLの向上を目的に、こうしたリスクを冒す必要があるのか、そもそも許容されるのかという議論がある。海外では、QOLの向上を目的に手、腕、喉頭、顔面、腹壁等の移植が実施されている。また、効果の高い人工透析やインスリン治療が普及したにもかかわらず、それらの治療を避ける目的で、腎臓や膵臓の移植が実施されているといった反論も出来よう。
費用については、出産後の移植子宮摘出までを含めると、合計2000万円を超えるとされるが、その負担も課題になってくる。
他方、利点を考えてみる。1978年に世界で初の体外受精児が誕生して以降、この生殖技術は瞬く間に世界に広まる中で、様々な問題を提起してきた。例えば法的な問題では、子宮移植は第三者の卵子や精子は不要とする事が出来、戸籍上にも遺伝的な親子関係が保たれる事は利点となる。また、代理出産のように、他人に出産のリスクを負わせなくて済む。
日本では、第三者が関与する生殖補助技術の法整備が進んでいない。代理懐胎の法整備の動きが進めば、子宮移植の今後の在り方にも影響を与える事になるはずだ。技術と共に社会的動向を注視したい。


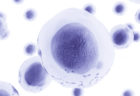

LEAVE A REPLY