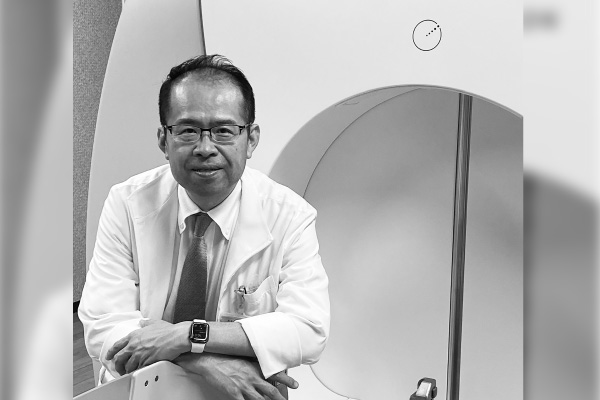

林 基弘(はやし・もとひろ)1965年東京都生まれ。91年群馬大学医学部卒業、東京女子医科大学脳神経外科入局。99年仏マルセイユ・ティモンヌ大学留学。2019年から現職。日本脳神経外科学会代議員、日仏医学会理事。
第43回
東京女子医科大学(東京都新宿区)
脳神経外科准教授
林 基弘/㊤
脳神経外科医でガンマナイフ(定位的放射線装置)治療の第一人者の林基弘は、医師として脂の乗った46歳で急性心筋梗塞を発症した。
前日の首のこりや大量の発汗から17時間経過
日曜は朝から愛犬と散歩して、学生時代から続けているテニスをした後、家でくつろいで過ごすのが定番だ。2012年4月1日も変わらずそう過ぎつつあったが、途中でまどろんでしまった。テレビで「笑点」を見ていた時だった、座布団を運ぶ場面だったはずが、CMに替わっていた。なぜかびっしょり汗をかき、左の首には鈍い重さがあった。一瞬意識を失っていたのだ。食欲もなかったが、いつも通り夕食を終えて床に就いた。
翌2日月曜の朝に目覚めると、首のこりは消え、違和感のみが残っていた。当時は自宅から大学まで3キロほどの道のりを自転車で通っていたが、新しい年度の初日で荷物が多かったため、タクシーを利用した。その日も、午後から2件のガンマナイフ治療を控えていた。
何とかガンマナイフ室まで辿り着いたが、そこで観念した。左の首のこりや発汗から、林は心臓に異変があるのではないかと疑っていた。不安が募り、循環器内科医で気の置けない同僚の山口淳一に電話をして、ガンマナイフ室まで来てもらった。林の父は17年前に心筋梗塞を発症しており、ステント手術を受けた。その後、内科でフォローアップを続けてくれていたのが山口でもあった。父親と同じ病であってほしくないという林の淡い期待は、あっさりと裏切られることになる。
狭心症の疑いがあると診断され、歩いて心電図室に向かった。心電図を見ると山口の顔つきが変わった。「下壁側壁に梗塞がある」。そのまま、緊急でカテーテル治療を受けなくてはならない。時計は10時を回っていた。前夜の発症から17時間が経過している。一刻の猶予もなかった。
林は1965年、東京都世田谷区に生まれた。父は会社員で、母方の先祖に医師がいた。陸軍軍医で、軍医総監だった森鷗外と良きライバルであったと、子どもの頃から聞かされていた。生来健康な子だったが、小学校2年生の時にアレルギー疾患に苦しんだ。全身に発疹が出たが原因がわからず、国立小児病院(現・国立成育医療研究センター)でサバとインフルエンザワクチン同時摂取によるアレルギーと突き止められた。何度も病院に通ううち、自分を治してくれる医師がとても頼もしく思えた。
中学・高校と進むうち、人に関わる仕事がしたいと、自然と医師になることを考えた。数学や物理が得意で医療機器を作る道にも関心があったが、1浪の末、群馬大学医学部に入学した。
大学では硬式テニス部に入り、こちらも全力投球した。5年生の時には、東日本医科学生総合体育大会に副主将として出場し銅メダルを得た。
専門として脳神経外科を選んだのは、シンプルながら奥深いことに魅せられたためだ。神経学的検査では、打腱器1つで様々な病態の診断が付けられる、いわば電気回路のようなもの。そのシステマティックな仕組みは、理数系の頭にピタッとはまった。心臓と並び、脳は人間にとってかけがえのない臓器でもあった。
学生実習で脳神経外科を回ると、意識がない状態で人工呼吸器につながれている患者にも大勢遭遇した。少し気が滅入ったが、入ってみると、家族や患者と話す時間は多く、人生の際にいる人を支える仕事に大きな意義を見出した。
1991年に医師になり東京女子医大に入局したのは、家から近いことに加え、男性医師は皆外様で学閥がないことも決め手となった。早くから執刀の機会も与えられ、手術の腕を磨いた。
3年目に転機が訪れた。92年に脳神経外科教授となった高倉公朋の英断で93年に脳神経センターにガンマナイフが導入され、その担当の一人に抜擢されたのだった。スウェーデン生まれのガンマナイフ治療は、放射線のガンマ線を脳の病変部に集中的に照射し、あたかも病変をナイフで切り取るかのように根治させる治療で、開頭手術が難しい部位にも威力を発揮する。頭部にフレームを装着させCTやMRIを撮影し、照射する位置を0.1mm単位で3次元的に定める。コンピューターで計算して病変だけに高いエネルギーの放射線が当たるよう照射計画を立てていく。
学生時代にガンマナイフの名前は聞いたことがあったが、当初の林はあまり関心がなかった。4年ほど、開頭手術と並行して、脳腫瘍や脳動静脈奇形の治療を1000例近くこなし、それなりに成果を挙げていたものの、ルーチン化した作業に興味を失いかけていた。次の教授の堀智勝はてんかんなどの機能性脳疾患を専門としており、林に新たな応用の可能性を探るように勧めた。林は国際学会に参加して、ガンマナイフをてんかんに応用した先駆者の話を聞き、開眼した。「自分にしかできない治療をしたいと思っていたが、求めている物に出会えた」。
機能性脳疾患への応用可能性に開眼し仏で修行
演者であるフランス・マルセイユの大学病院のレジス教授に猛アタックをかけ、毎日のように留学許可を願うメールを送った。99年に3カ月の短期留学が叶い、基礎から徹底的に学んだ。一旦帰国後、再渡仏要請でインターンとして戻り、2000年仏脳神経外科専門医師資格を取得。在仏中1日15時間の仕事も、フランス語が覚束ないこともはねのけ、患者に励まされつつ実践で腕を磨いた。
02年に帰国すると、外科手術の現場に戻ることをあえて拒否して、ガンマナイフに専念する道を望んだ。「異端児で生意気だった。“F1のマシン”があるのだから、F1ドライバーとして学んできたことを生かしたかった」。ガンマナイフの典型的な適応となる脳静動脈奇形や脳腫瘍だけでなく、学んできた機能性疾患なども自在に治療していた。2004年には三愛病院(さいたま市)にガンマナイフセンターを立ち上げ、週1回はそちらでも治療した。10年には世界脳神経外科学会連盟の定位放射線治療部門副会長に就任した。
それから2年。前年には45歳の誕生日を迎え、「医師人生の折り返し」と一念発起して、プライベートトレーニングで身体の引き締めに成功していた。喫煙歴はなく、飲酒もたしなむ程度。体力には自信があったが、国際学会会長選挙を控え心労が重なったことは間違いなかった。最終的にはそうしたストレスが、冠動脈のプラーク破綻の引き金となったとされる。人生初の大病に見舞われたが、“まな板の上の鯉”となる覚悟はできていた。命を預けてもよいと思える医師が目の前にいた。 (敬称略)




LEAVE A REPLY