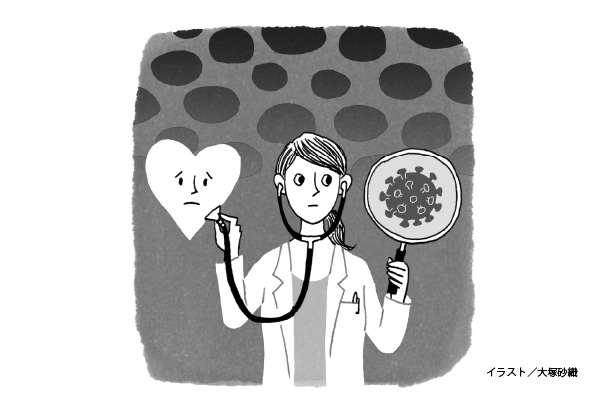
新型コロナウイルスの影響が日常生活にも及んでいる。私が臨床をしている病院では、小学校低学年の子どもを持つ看護師や事務職に一斉休校の措置で欠勤を余儀なくされる人が続出、病院機能にも影響が出ている。
一緒に働いている子育て中の看護師に聞くと、夏休みなどの通常の長期休暇の時は前もって実家に預ける、朝からスポーツ教室に行かせるなど、綿密なスケジュールを立ててしのいでいるのだそうだ。「児童館も閉館しているし、学童保育は午後からだし、まだ小学2年生なので1人で留守番はさせられないんですよ」と途方に暮れていた。
おそらく、これを読んでいるクリニックや病院の経営者、医師の中にも、同様の問題で頭を悩ませている人がいるだろう。感染対策としてはやむを得ないと思う一方で、「児童や生徒の発生は比較的少ない中、集団発生していない地域まで一律に休校するのが、果たして本当に感染拡大防止に効果的なのか」という疑問も残る。
医師専門サイト「m3.com」に政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で副座長を務める尾身茂氏(地域医療機能推進機構理事長)のインタビューが載っていたが、そこでは「専門家会議で学校休校について議論したことはない」という事実が明らかにされている。
尾身氏は、「専門家会議として、それを主な議題として議論したことはありません。ただし、専門家個人としてそれぞれの意見はあり、その思いを述べることは大事であり、それが透明性につながります。私自身は『何とかしたいという、安倍総理の気持ちの表われ』だと思います」と語り、疫学的・医学的な休校の効果についての質問には回答を避けた。
診察の場で患者の質問にどう答えるか
もちろん、本誌の読者の多くも医療の専門家であり、尾身氏の言うように「専門家個人としてそれぞれの意見」があるだろう。ただ問題は、患者さんに診察場面などで質問された時、どのように答えるかということだ。
私は精神科医なので、診察室にはうつ病やパニック症など、普段から不安、気持ちの落ち込み、発作の恐怖などを抱えている人がやって来る。その中には、今回の新型コロナウイルスの問題で症状が悪化し、身動きが取れなくなっている人もいる。
例えば、「自分も周りも汚れていて不潔だ」という強迫観念に支配され、手洗いや消毒を繰り返す強迫性障害の人達などは、いつも以上に洗浄を行い、ほとんど家から出られない制縛状態に陥っている。
さらに気になるのは、これまでは問題なかったのに、テレビなどで「正しい手洗いは20秒以上」などと言っているのを見て、何を触っても長時間、手を洗ったり、ビニール製の手袋を常時、装着するようになったりと、こちらから見ると適切な対策を通り越してほとんど強迫性障害のレベルに達している人だ。
「マスクが売り切れで買えない」となると、恐怖から居ても立ってもいられなくなり、ネットオークションで高額で購入しようとしたり、ドラッグストアで他の客と奪い合いをしたりしている人達も、強迫観念から合理的な判断ができなくなっているとしか思えない。
だから、どうしても臨床の場では「心配し過ぎなくても大丈夫ですよ」と患者を安心させるようなメッセージを発することが多い。
「こうやって通院するだけでコロナウイルスにかかってしまうのではないでしょうか。しばらく来たくないです」と語る統合失調症の患者には、外出を中止して感染を防ぐメリットより受診や服薬をやめてしまうことのデメリットが大きいことを鑑みて、「大丈夫ですよ。感染することはありません。来週も来てくださいね」と伝えるしかない。
エビデンス次第で方針変更する融通性を
ただ、この「大丈夫です」は疫学的、医学的なエビデンスに基づいての発言かというと、当然そんなことはない。今回のウイルスは感染力や発症から治癒までのプロセスもまだ十分にわからない「新型」なのだから、たとえ医者とはいえ、「そんなに手を洗い過ぎなくてもいいです」「感染しないので通院を続けてください」と断言できるほどの根拠は何もないのだ。
しかし、繰り返すように、感染のリスクを減らすために1日中、洗面所にこもって手を洗い続けたり、薬が切れても家にいて幻聴や妄想が再燃したりするのは、その人にとってあまりに損としか言いようがない。だから、こちらも少々言い過ぎかとは思いつつも、笑顔で「安心してください」「大丈夫です」と伝えないわけにはいかないのだ。
また、そういう時でも「今私は医学的根拠が乏しいことを言っているな」という自覚だけは忘れずにいたい。
そして、もしやはり「電車に乗るのは危険」というエビデンスが明らかになる、といったことがあれば、きちんと「この間は大丈夫と言いましたが、やっぱりしばらく通院の間隔は空けましょう」と方針を変更する融通性も大切だろう。一度言ったからには状況がどうなっても「大丈夫」と言い続けるというのは、医者としては極めて無責任な態度だ。
さらにもう1つお願いしたいのは、極端な考えを患者に伝えるのは控えてほしいということだ。例えば、ある人は診察室で、「この間、近所の内科を受診してコロナのことを先生に聞いたら、“あれはアメリカの生物兵器なんだよ”と教えてくれました。怖いです」と話した。「大丈夫ですよ」あるいは逆に「もう少し気をつけないと大変なことになりますよ」と少々大げさなもの言いをするのは、あくまで「患者にとって治療的効果がある場合に、きちんと自覚しながら」としたいものだ。
先の医者はジョークで言ったのか真剣にそう信じているのかはわからないが、一般の人々にとっては「あの先生も言った」というのは、本人が思っている以上に重みを持つ。今回のことは世界が直面する大きな試練だが、臨床医にとっては治療の場でのコミュニケーションについて考え直す機会になることは確かだ。




LEAVE A REPLY