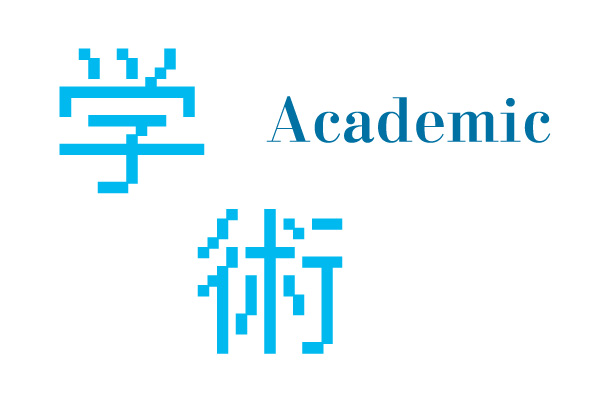
疾患修飾療法がもたらす治療の新たな選択肢
認知症治療は、新薬の登場により大きな進展を迎えている。嘗ては、対症療法で症状改善薬しかなかったが、特にアルツハイマー型認知症の治療に於いては疾患修飾療法(DMT)が登場して、進行を抑えるという新たな選択肢が生まれている。しかし、実臨床に効果的に導入するには、診断技術の向上や適切な患者選択が不可欠である。認知症治療の現状と最新の治療法について概説する。
DMTに掛かる期待は大きい
アルツハイマー型認知症を中心として、認知症の患者数は世界的に増加の一途を辿っている。とりわけ、日本では超高齢化の進行と共に、認知症患者の数は増え続け、2025年には約700万人に達すると予測され(厚生労働省、23年)、社会問題ともなっている。
しかし、従来の認知症の治療は対症療法が中心だった。日本で生まれた、エーザイの世界初の認知症治療薬ドネペジル(アリセプト)は、1996年に米国で、99年に日本で承認された。その後も、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬やNMDA受容体拮抗薬が登場したが、一時的に症状の改善が見られはしても、疾患の進行を抑制する根本的な治療法には至らなかった。
そうした中、DMTの時代が到来している。DMTは、アルツハイマー病の根本原因、すなわち主要な病理学的要因であるアミロイドβ(Aβ)やタウタンパクを標的とし、疾患の進行を遅らせる事を目的とした治療である。これに基づく新薬の登場により、治療選択肢が大きく広がりつつある。
アルツハイマー病でAβの蓄積を抑制する薬剤の代表例が、レカネマブとドナネマブである。レカネマブは、エーザイと米国のバイオジェンが共同開発した抗体医薬で、2週間毎に点滴投与する。米国食品医薬局(FDA)が2023年1月に迅速承認し、7月に通常承認した。日本では同年9月に承認され、12月に上市されている。適応は、早期アルツハイマー病で、軽度認知障害(MCI)及び軽度認知症を対象とする。臨床試験(Clarity AD試験)に於いては、病状の進行を約27%遅らせる事が確認されている。
現場では、適用対象の診断や副作用管理が課題になっている。副作用には、脳浮腫や脳出血等が見られ、一部の患者では重篤な影響も報告されている。又、薬価が高額である為、コストと医療保険制度との兼ね合いは大きな課題となっており、健康保険の適用範囲や、費用対効果に関する議論も続いている。
次にドナネマブは、米国イーライリリーが開発したアルツハイマー病治療薬で、Aβ抗体の一種である。作用機序は、レカネマブと同様に、Aβの蓄積の除去により、病気の進行を遅らせる事を目的としている。レカネマブと異なるのは、Aβの中でも沈着した凝集型(p3-amyloid)を主にターゲットとする点である。タウタンパクの蓄積が進行していない早期患者に於いても有効性が示されており、進行の抑制が期待される。
TRAILBLAZER-ALZ 2試験(第3相臨床試験)では、軽度認知障害(MCI)及び軽度認知症の患者を対象として、病状の進行を約35%遅らせる事が確認された。これは、レカネマブの27%を上回っている。もう1つの特長に、Aβが一定量減少した患者には、投与を中止出来る点が有る。レカネマブは2週間に1回の点滴投与を継続しなくてはならない。一方で、副作用の発生率は、脳浮腫24%、脳出血31%と、レカネマブ(13%と17%)よりも高めである。米国では 23年7月にFDAに申請されたが、追加データを求められ承認は24年である。日本でも、同9月に承認された。
これらの薬剤は、PETや髄液検査によるバイオマーカーが診断のゴールドスタンダードではあるが、日本の実臨床で広く普及しているとは言い難い。適切な患者を選択する事が極めて重要で、脳浮腫等の副作用管理も課題となっている。
エーザイではAβ産生抑制薬(BACE阻害薬)であるエレンベセスタットも治療薬として開発されていたが、有効性が不十分だとして23年に中止されている。
タウタンパクを標的とした治療薬も開発中である。タウ凝集体の形成を阻害する薬剤については、第2相・第3相試験が進行中であり、神経細胞死の抑制による認知機能低下の予防が期待されている。又、神経炎症を標的とした治療薬、神経炎症はアルツハイマー病の進行を加速させる要因となる事が知られている。この為、炎症性サイトカインを抑制する事で、神経細胞を保護する治療が模索されている。免疫調整薬を活用したアプローチが現在研究されており、将来的な治療選択肢の1つとして注目されている。
レビー小体型認知症にも新薬誕生の期待
アルツハイマー病、血管性認知症と並ぶ3大認知症の1つであるレビー小体型認知症(DLB)についても、研究が進んでいる。
DLBは、脳内にレビー小体という異常なタンパク質(α-シヌクレイン)が蓄積する事で発症する神経変性疾患である。主な特徴は、明確な幻覚、認知機能の変動、更に手足の震え(振戦)、筋肉のこわばり、歩行障害等、パーキンソン病に似た症状が出る。自律神経症状として、立ちくらみ、便秘、排尿障害、睡眠障害(レム睡眠行動異常症)等が現れる。認知症の周辺症状である妄想や興奮が見られる事が有るが、通常の抗精神病薬を使うと重篤な副作用(意識障害・運動障害)が発現する事が有る。
診断は、DATスキャンや臨床評価で行う。有効な根治療法は無く、対症療法が中心である。薬物療法として、認知機能の改善の為にドネペジル等のコリンエステラーゼ阻害薬、パーキンソン症状の改善にはレボドパ(L-DOPA)を、レム睡眠行動異常症にはクロナゼパムが有効とされる。アデュカヌマブやレカネマブの様なAβ抗体薬はDLBには効果は認められていない。現在、大阪大学ではDLBに対する新薬の開発を進めており、αシヌクレインを標的とした疾患修飾治療薬の治験が25年中にも開始される。この他、非薬物療法として、後述する生活環境の調整やリハビリテーションによる症状管理も重要である。
認知症克服へ広がる選択肢
認知症の克服を目指して、日本国内でも、あの手この手で最先端の研究が進められている。先ず、お家芸のiPS細胞を用いた再生医療で、京都大学iPS細胞研究所では、アルツハイマー病及びレビー小体型認知症の新たな治療法を模索している。理化学研究所では、タウタンパク蓄積を抑制する新薬の開発と創薬スクリーニングの高度化に力を入れた研究が進められている。東京大学医学部附属病院では、認知症・アルツハイマー病の予防・治療に向けた研究基金を創設しており、院長である田中栄氏らが、超早期診断の為の血液バイオマーカー開発を進めている。又、国立精神・神経医療研究センターでは、認知症の神経炎症メカニズムを解明し、免疫調整薬の開発を推進している。
これらに加え、非薬物療法の組み合わせも重要性を増すと考えられる。最新の研究で有効とされた非薬物療法には、リハビリテーションや音楽療法が有る。リハビリは、記憶訓練や注意力向上プログラムを通じて、認知機能の維持を目指す。音楽療法では、音楽を活用して感情を刺激し、認知機能や精神状態の改善を促すだけでなく、グループセッションを通じた社会的交流の活性化も期待される。更に、運動療法として有酸素運動やヨガが神経可塑性を促進し、認知症の進行を遅らせる可能性が示唆されている他、ダンスや太極拳等の複合的な動作を伴う運動が脳の活性化に有効であるとの報告も増えている。
近年は、デジタル療法(DTx)で、VR(仮想現実)技術や認知トレーニングアプリを活用し、脳の活性化を図る治療も進められている。特に、認知症やうつ病、慢性疼痛の治療に於いてVRを用いたリハビリテーションやデジタル認知行動療法(DCBT)が注目されており、個々の患者に最適化された治療プログラムの開発が進んでいる。
認知症治療は、新薬の登場も含め、今後ますます選択肢が広がる事が期待される。診断技術の向上は勿論の事、適切な患者選択、多職種連携は今迄以上に不可欠になる筈であり、医療・介護の連携を強化しながら、包括的な治療戦略が確立される道程を注視したい。



LEAVE A REPLY