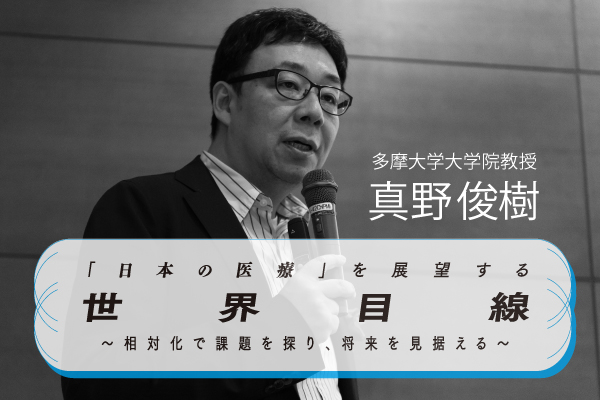
前回まで、シンガポールの様子を述べてきたが、今回は、韓国の医療や医療DXの様子を調査する機会をもったので報告する。ご存知のように韓国は、特殊出生率が1.0を切っており、2045年頃には日本以上に人口の高齢化が進むといった予測もある国である。また、1989年に日本を見習った国民皆保険制度を作っている国なので、株式会社としての病院経営ができないなど、日本に似通った、いわゆるユニバーサルヘルスカバレッジを持った国となっている。ただ、制度は国民性まで規定するのは難しいと思われる。今回以降、何回かに分けて韓国医療の状況を説明するが、今回はまず総論的にまとめておきたい。
韓国の医師給与
韓国の医師の給与は日本より高い。24年5月15日付のハンギョレ新聞によれば、クリニックに勤める医師の平均年収は、16年の2億1400万ウォン(1ウォンは24年10月では0.11円)から22年には3億4500万ウォンへと、年平均8.3%上昇した。一方、重症医療や救急医療を担う上級総合病院の医師の年収は、16年の1億5800万ウォンから22年の2億100万ウォンへと、年平均4.1%の上昇だった。開業医の中でも眼科医の年収が6億1500万ウォンで最も多かった。続いて整形外科が4億7100万ウォン、耳鼻咽喉科が4億1300万ウォン、麻酔科が3億9100万ウォンの順だった。
では、韓国の医師が日本より高収入である理由を分析してみよう。まず、国全体の経済状況、つまり国民1人あたりのGDPが日本と同等のレベルになってきており、急速に豊かな国になってきている現状がある。ついで医療産業として見ても、05年頃から医療ツーリズムを含めた「医療の産業化」に大きく舵を切っている。集約化も進んでおり、今回見学したサムスンメディカルセンターやソウル大学病院も2000ベッドクラスであった。関連病院も交えて治験にも積極的で、そちらからの収入も確保、さらに後述するように医療DXも進んでいる。また、そもそも混合診療の範囲が大きく、ブランド病院は高額な医療費を請求している。そして、ミクロでは、医師は、かなり長時間働いている。これは、OECD Health Statisticsのデータでの1ドクター当たりの外来患者数や平均在院日数の短さからも想像される。ちなみに人口あたり医師数は日本より少し少ない(図1)。
高齢化対応は遅れるが医療DXは進む
ただ、急速に高齢化が進んでおり、高齢化対策が必要だという点は、日本も同じである。しかしながら、高齢化対策においては、韓国は日本のように、施設から在宅へとかキュアからケアへ、といった方向性にはあまり向かっておらず、どちらかといえば、療養系の病院を増やすことで対応しているように見える。
実際、OECDのデータでも、世界のほとんどの国で病院の数が減っているのに対し、韓国は急速に病院の数を増やしており(図2)、その大半は療養型病院である。近年のコロナ禍以降、さすがに急速に増えた急性期病院数が減少しているという話であるが、日本のような地域包括ケアといった形での対応はあまり取られていないようである。
こういったことから、医師の「数」が必要となり、国は25年から医学部の定員を現在の3058人から5058人に増やす計画を発表した。ところが、研修医が今までの収入を得られなくなるのではないかということでストを起こし、一部の病院勤務医もそれに同調した。現在でも半年以上、ストを起こしている状態になっている。この辺りもはっきりとした国民性のなせる技だと思われるが、結果的には病床の稼働が減り、患者への手術が遅れるといったことで、患者が割を食っている状況である。
GR_韓国1-Part2
図1)OECD諸国に於ける人口1000人当たりの開業医数、2011年と21年(又は直近の年)
GR_韓国1-Part1
図2)OECD諸国に於ける病床数、2011年と21年(または直近の年)
しかし、医療DXの浸透は著しい。これは、病床規制がないために大病院がさらに増床したり、M&Aによって分院を積極的に作ったりしたことで収益が拡大し、IT投資を積極的に行っていることが原因である。実際、我々が訪問したサムスンメディカルセンターもソウル大学病院も、それぞれ2000ベッドとか1700ベッドの大きさであり、分院をいくつか所有している。
制度依存性
ここで少し、日本との差が起きた理由を考えてみよう。経済学に制度依存性という概念がある。制度依存性とは、社会の制度や仕組みが特定の行動や考え方を強く規定する状況や現象を指す。制度は法律、規制、社会的なルール、文化的慣習などを含み、人々の選択や行動、組織の運営方法を体系的に形作っている。このため、ある制度が一度確立されると、その制度が社会や個人の行動に与える影響が持続し、新しい制度が導入されたり、制度が改革されたりする場合に、既存の制度に依存する傾向が強くなる現象が起こる。
制度依存性の特徴をもう少し詳しく述べると下記のような概念がある。
パス・ディペンデンス(Path Dependence):制度依存性は「パス・ディペンデンス」とも関連する。これは、一度採用された制度が、その後の変化を制約し、新しい制度の導入を困難にすることを指す。過去の選択や出来事が現在の制度や政策の決定に影響を与え続けるため、最適な変化が妨げられることがある。例えば、医療制度や年金制度などの改革が難しい背景には、このパス・ディペンデンスが関わっている。
制度的慣性(Institutional Inertia):制度依存性により、既存の制度が長く維持される傾向がある。制度的慣性は、制度が変化しにくい理由の1つであり、社会の大部分が既存の制度に適応し、その制度を前提として行動している場合、改革には多くの抵抗が伴う。これにより、急激な改革ではなく、漸進的な変化が起こりやすくなる。
制度変更の困難さ:制度に依存している人々や組織は、その制度から利益を得ているため、制度変更に対して強く反対する傾向がある。例えば、既得権益を持つ団体や企業が制度改革を妨げることが一般的で、このため、制度の見直しや改革は長い時間と多大な労力を必要とする。
例として、医療制度や年金制度を挙げたが、労働市場も同じことが言える。労働市場における雇用保護規制や労働組合の制度も制度依存性の例で、既存の雇用形態や労働条件を保護するための制度は、雇用の柔軟性を阻害することがある。このため、労働市場改革が提案されても、制度の変更には強い抵抗が伴う。
制度依存性には利点もある。社会の安定性を保つ上で重要な役割を果たしており、日本の場合、世界有数の医療レベルの保持や、失業率の低さなどを実現している。その一方で課題もある。新しい技術や社会変化への対応が遅れ、非効率的な制度を温存する傾向があるため、社会の変革が起こりにくくなる。日本では制度依存性が強かった。しかし韓国ではそうでもないようだ。次号で韓国と日本の比較を詳しく行う。


LEAVE A REPLY