商業資本・外国資本による侵蝕の恐れ
産科診療所は、年5%以上の出生数減少という少子化の急加速や、大学病院等の産科病院の集約化・無痛分娩推進・働き方改革などの諸要因の狭間で、苦境に立たされている。このままの体制では、多くの産科診療所が廃院せざるをえなくなったり、商業資本(ひいては、外国資本)に買収されて吸収されてしまったりする恐れが顕著だと言ってよい。それらの資本の蠢動は、産科の周辺でもすでに見え隠れしている。
「産科医療」と同じ自由診療中心体制の「美容医療」は、すでに商業資本や外国資本に侵蝕され始めた。それらの資本は「営利」を追求するものであるために、時には極端なコストカット(人員、給与、医療安全対策の諸費用等)を伴い、その削減分を膨大な宣伝広告費用に回して、集客と売上げの増加につなげようとしている。それを「経営」と称する商売人(外国人も含む)によって、一部の「美容医療」が食い荒されつつあるように思う。とは言え、厚生労働省の地方厚生局が営利排除権限を有している保険診療とは異なり、自由診療がメインなので、「営利目的」禁止の観点からの規制をしにくい。
今現在、特に産科診療所は、経営が苦しくなっており、4割強が赤字とのことである(日医総研ワーキングペーパー「産科診療所の特別調査」2024年11月26日付)。地方部では「分娩の減少」、都市部では 「物価高騰、賃上げ等の医業費用の増加」などの要因から経営が悪化してしまった。
このままの状態が続けば、少なからぬ産科診療所は「商業資本」「外国資本」に足元を見られ、叩かれて買収されてしまうか、それとも、買収されるのを潔しとせず、もう諦めて廃院してしまうか、どちらかであろう。しかしながら、「美容」より遙かに「公共性」の高い「産科」が、そのようなことになってしまっては、妊産婦にとっても国家にとっても由々しき事態である。
「産科診療所」は社会のインフラにほかならない。かつて経済学者のヴェブレンや宇沢弘文が経営者の持つべき資質として「公益性」「職人気質」をも強調されていた。公共的なインフラである「産科診療所」は、「営利的な資本」によってではなく、公益目的で職人気質の「医師」によって経営されるべきである。この「営利性」排除の趣旨は、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の「健康保険事業の健全な運営」(第2条の4〜5)にもよく表わされていると言えよう。
とは言え、現在の自由診療体制のままでは過酷な過当競争にさらされ、挙句の果ては、営利的な資本に買収されてしまいかねない産科診療所を保護するための「営利性排除」の効果をも有する「正常分娩の保険化」への移行もしようとしないままで、ただ単に、「補助金を多くしろ」「出産育児一時金を増額しろ」と言うだけでは、(産科以外にも「公共性」の高い分野は、全国家的には多く存在するだけに)現実的ではないし、(自ら「身を切る改革」なども何もしないままでは)説得的でもない。
そこで、ここに2号に亘り「周産期医療体制の確保」の一環としての私的な政策提案として、「産科診療所の支援策」を提示することにする。
収益拡大策に関する私案
1.少子化対策により全国家的な出生数増加へ
真の少子化対策(注・「少子化社会」対策ではない)は、結婚・妊娠・「出産」・子供・子育てのすべての局面への支援策が出揃い、足並みを揃えて同時並行して進まなければ、実効性がない。「出産」の局面でも関係者皆が少子化対策に賛同し、「多様な市場ニーズに対応した新たな標準化戦略」の下で、「分娩介助の多様化と標準化(包括払い化)」等によって保険化(現物給付化)を推進していくべきである。
なお、ここに言う「分娩介助の多様化」とは、正常分娩における分娩介助本体を指す。今までは、分娩介助本体はパターナリズム的に画一化したままで、附帯サービスである特別室・特別食・アロマセラピーなどにばかり多様化を進めようとしていた。これは、方向性が違う。あくまでも正常分娩の分娩介助の「本体」にこそ、「(質的な)多様化」と「標準化(包括払い化)」を施さなければならない。こうしてこそ、真に、少子化対策の実効性が生じるのである。マクロでの出生数の増加こそが、すなわち、市場拡大、収益拡大につながることであろう。
2.良質な出産ケアと助産師の力で多子化へ
重要なのは、「多子化戦略」のあり方である。少しでも多くの夫婦に1〜2人の子を生んでもらうことを重視する政策ではない。多くの子を生みたい夫婦に、3人以上の子を生んでもらうことを重視する政策である。これを「多子化戦略」と呼ぶ。つまり、「リピート客(常連客)」を育てる方策であるから、「次子出生意欲」を高めることこそが肝要である。「より良い出産ケア」を目指し、「出産ケアの質」を改善しなければならない。具体的には、内診や会陰切開は最小限にし、無痛分娩もできるだけ控え目にし、吸引分娩・鉗子分娩や帝王切開への誘導をしないように心掛けるべきであろう。
また、産科診療所では出産ケアの多くは助産師によってなされている。ほとんどタスクシフトをしていると言ってもよいぐらいであろう。つまり、現在の「分娩料」(注・出産育児一時金の専用請求書の書式上の概念。医師・助産師の技術料及び分娩時の看護・介助科)の多くは「助産師の活躍」によって獲得されていると言ってもよい。いつも個々の医療行為ごとの「出来高払い」として認識している産婦人科医のイメージでは、なかなか上手く把握できないのかも知れないけれども、その点がまさに重要なポイントである。
そのような個々の行為の積み上げといった量的な観点ではなく、連続した不可分一体の一連の助産行為を質的な観点でとらえて「包括払い」としつつ、より良い出産ケアに対して質的向上の評価として加算していくという発想に転換しなければならない。そのような出産ケアの質の改善の発想に虚心坦懐に転換すれば、そのような産婦人科医には、たとえば、継続ケア・かかりつけ・見守り(専従)などに加算の点数を付けることの意味が分かって来るであろう。
なお、現在の「療養の給付」には、原則、「混合診療の禁止」というルールが適用されている。ところが、産科の正常分娩においては、それが異常分娩に移行した場合でも、自由診療から保険診療に変化して構わないという特殊なルール(いわば自由診療中心型混合診療。通常言われる混合診療のイメージは「保険診療中心型混合診療」であるので、産科で事実上通用している混合診療は特殊なタイプである)が適用されていると言ってよい。正常分娩の保険化というのは、自由診療を(出産)保険診療に置き換えて、いわゆる「分娩料」と「分娩介助料」の垣根を取り払うという変化をさせたものに過ぎないのである。したがって、「分娩料」の現物給付化が可能なのも当然のことであって、旧来の視点に凝り固まっている産婦人科医の目には不思議だと映ることもあるかも知れないが、いずれ自然に目が慣れてくることと思う。
3.嘱託医療機関受託による助産所への協力
① 連携強化による搬送数・転送数増への取り組み
「多子化戦略」に最も威力を発揮するのが「助産所」である。そうすると、「助産所」との連携を強化することによって、助産所からの搬送数や転送数を増加させることが、患者増加の早道であろう。つまり、今まで以上に、嘱託医療機関や嘱託医となることを積極化すべきなのである。
なお、正常分娩が保険化されたとしたら、そもそも保険指定された助産所が嘱託医療機関がないために分娩できないなどという事態は、保険制度としてナンセンスというほかない。そこで、保険化と同時に、嘱託医療機関・嘱託医受託に妊婦等のための応招義務を課すべきである。具体的には、医師法第19条第1項後段に、「正常分娩に関する産婦人科診療に従事する医師は、助産所での分娩(妊婦等の自宅等に出張して助産師が助産を行う分娩も含む)の助産を行うために、助産を担当する当該助産所又は助産師の嘱託を妊婦等より求められた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」という規定を挿入するのがよい。
以下、次号では嘱託医療機関・嘱託医の嘱託料の創設のほか、経費削減を鑑みた私案を紹介する。


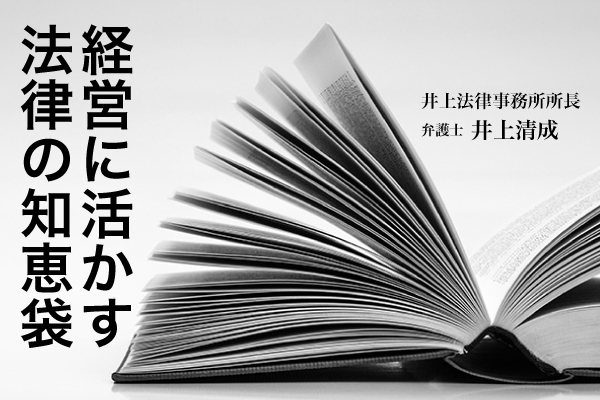
-250x154.jpg)


LEAVE A REPLY