
金沢医科大学(石川県河北郡内灘町)
整形外科特任教授
兼氏 歩/㊦
2017年、51歳で経験した大病は、進行性の大腸がんだった。5年を無事に過ごし、専門とする股関節の診療に心置きなく打ち込める日を取り戻した。天命を知る一方で、生かされた命で仕事や家庭に尽くし、がん啓発にも力を入れる。
術後化学療法を断念し免疫細胞療法
勤務先の金沢医科大学病院で手術を受け、がんが浸潤していた腸の右半分をほぼ切除した。患者にメスを入れるのは日常茶飯事だが、切られた箇所はこんなにも痛いのだと思い知らされた。
まだ術後の治療が控えていたが、発症から手術に至るまでの経験だけでも、得難いものだった。数え切れないほど行き来した病室の風景も、ベッドから見上げると、全く違って見えた。そこで思い至ったことを記録しておきたいと、病室に持ち込んだノートパソコンで、一気にメモを作った。
「手術患者になった経験から伝えたいこと」、そして「がんになった経験から伝えたいこと」。前者には、痛みの除去、安静の改善、安心感の醸成、早期の自宅復帰の実現、スピード感のある対応……など、患者として医療や医師に望む項目が7つ盛り込まれた。後者は、病から得た教訓で、過信の戒め、早期発見の重要性、社会的役割の再認識、生活習慣の是正などの5項目だ。これらのメモは職場復帰後、医局の若手医師らに配った。
術前に、ステージⅢA(3カ所以下の転移)と診断されていたが、病理検査で6カ所の転移が見つかり、最終的に「ステージⅢB」となった。主治医として執刀してくれたのは、母校・金沢大学の後輩で、事前に細かい説明をしてくれた。
ステージが進むにつれて、5年生存率はどんどんと低下していく。当初の治療計画通り、再発予防のためには、術後の補助化学療法は避けられないようだ。外来で、ゼローダの内服と、オキサリプラチンの静注を組み合わせた薬物療法を受けることになった。7クール、約6カ月の長丁場だ。
兼氏に手術してもらうことを望む患者は多かった。手術から7日後に退院すると、12日後には職場に復帰し、2週間後には執刀を再開した。
並行して化学療法を受けていたが、3クール目が終わる頃から、副作用として手のひらや足裏に痛みや腫れが現れた。痺れも激しく、次の治療までに回復しなかった。大柄な兼氏は、体重に応じて計算した抗がん剤の投与量が多めになる。これでは、自分がする手術に支障が出ると、悩ましかった。さらに食欲不振や黄疸も生じてきた。
主治医に相談したところ、このまま最後まで続けると、手足の後遺症が消えない可能性があるという。再発予防リスクと外科医としての医師生命を天秤にかけ、化学療法は打ち切る決断を下した。大がかりな世界的研究では3クールまででもかなり有望との結果が出ており、後押しする材料になった。薬をやめてしばらくすると、徐々に手足の正常な感覚が戻ってきて、安堵した。
標準治療を断念したことで、別の治療を模索した。当時金沢大学内には、かつて整形外科教授で兼氏の上司だった富田勝郎が理事長を務めていた先進医療を推進する金沢先進医学センターがあり、がんに対する免疫細胞療法を提供していた。患者の血液中のリンパ球を体外で増殖させ免疫細胞を増強した上で再び体内に戻し、がん細胞を攻撃させる治療を受けた。自費診療で合計250万円ほどかかったが、がん保険で治療費が賄えた。
学会の締めに実体験からがんを語る
兼氏の家族はいつも支え合っており、闘病の面では、妻が先輩だ。脊髄の病気で後遺症が残ったが、障害を物ともせず、車椅子でしなやかに飛び回っており、訪問看護ステーションを経営し、障害のある子どもの自立支援のために放課後のデイサービスも運営している。兼氏の助言で、リハビリテーションも提供するようになった。3人の子どもたちと共に、がんと闘う兼氏を応援してくれたのは、何より励みとなった。一方、郷里の愛知に暮らす高齢の両親には心配をかけまいと、職場復帰した後に闘病を伝えた。
大腸がんは、日本で2番目に死亡者数の多いがんである。身近な友人の配偶者も40代で命を落とすことになったと知った。働き盛りを襲うがん。「幸い自分は仕事にも復帰を果たしたが、早期発見や予防で救える命があるはずだ」。
股関節の治療のエキスパートである兼氏は、医師向けに講演する機会が多い。その場を使って、ささやかな啓蒙活動をすることにした。講演の最後に数枚のスライドを用意して、自分の闘病体験を包み隠さず話す。手術後、ICUに戻った際に妻に撮ってもらった写真に続いて、「手術患者になった経験から伝えたいこと」「がんになった経験から伝えたいこと」を切々と説く。特に、自分より一世代若い医師たちに知ってもらいたいと考えている。兼氏に触発されて、大腸内視鏡検査を受けた仲間のうち、数人にポリープが見つかり、感謝されることとなった。
死を恐れることなく仕事に打ち込む
フォローアップの重要性は身に染みている。治療後最初の1〜2年は、3カ月に1回の造影CT、半年に1回のPET、さらに毎月の採血……。負担は大きいが、「他のがんも見つけられる、良い機会だ」と前向きに捉えた。手術から3年、5年と経ち、検査の期間は短くなり、PETの検査や血中の腫瘍マーカー(CEA)にも今のところ問題はない。
食生活は大幅に改善したとは言い難いが、飲酒はほどほどに、コロナ禍が明けると、空き時間で自宅近くのスポーツジム通いも再開した。かつては深夜まで大学に長居することが多かったが、多くの仕事はパソコンがあればできるからと、帰宅して家族とまず食卓を囲む。
3人の子どものうち、2人は社会人となり、長女は妻の訪問看護ステーションで共に働いている。兼氏ががんを発症した当時、小学生だった次男は医学部を目指し猛勉強中だ。看護師の母、そして兼氏の生き方や闘病経験が影響を与えているとしたら、うれしいことだと思う。
がんとの向き合い方は複雑だ。「自分だけは大丈夫」と過信していたことは、大きな反省点だ。大らかな性格の整形外科医の仲間たちには、自分と同じようなスタンスの人が多いと感じる。一方で、がんを恐れる余り慎重になりすぎるのもストレスで、健康にマイナスだ。「笑いは健康のもと。ナチュラルキラー細胞が活性化されるというエビデンスもあり、人生を楽しみたい」。
足裏の違和感もほぼ解消され、便通も正常で腹痛もなく、身体的な欠損はない。がんになったことも、後の人生にプラスが多いと受け止めている。「神様がいるなら、『お前はまだ仕事をせんなん』と言われている気がする。いつ死んでも良いように、やりたいことをやっておこう」。
臨床への全力投球はもちろんのこと、将来の患者のための基礎研究も結実させたい。闘病で慎重になった。大切な人生の時間で、患者や家族、周りの人に精一杯尽くすつもりだ。(敬称略)
〈聞き手•構成〉:ジャーナリスト 塚嵜 朝子


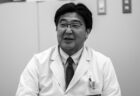

LEAVE A REPLY