
長野原町へき地診療所(群馬県吾妻郡長野原町)
所長
金子 稔/㊦
金子 稔(かねこ・みのる)1984年群馬県生まれ。2011年自治医科大学医学部卒業。群馬大学医学部附属病院初期研修医。13年同救急部。15年から現職。
2022年3月、左手麻痺で群馬大学病院(前橋市)に搬送され脳梗塞と判明。すぐに治療が開始され、脳保護薬と抗血小板が点滴で投与された。モニターにつながれ身動きできず、トイレに行くのもナースコールを押して介助してもらった。気分はどん底だった。
左手握力は5kgに リハビリを経て退院
現実と向き合うのが怖く、予後については主治医に尋ねられずにいた。診療所のことを考える余裕もなかったが、町役場では緊急の会議が開かれていた。年度末で急な代診医師は見つからず、取り敢えず、数日間は休診を余儀なくされた。
金子は小学3年生の時に扁桃腺摘出手術を受けたことがあったが、本格的な入院は初めてだ。3日目にモニターや点滴が外れると、歩くことはできた。左手の握力は40kg以上あったのが5kg以下に落ちていて、愕然とした。リハビリテーションはボールを握ることから始めたが、積み木は全く積めなかった。それでも認知や判断能力には問題がなさそうだった。「内視鏡などの手技はできなくても、医師は続けられるかもしれない」。わずかな光が射してきた。
落ち着きが戻ると、診療所が気がかりだった。コロナワクチン接種は、西吾妻福祉病院の医師が代わってくれたが、代診医師を手当てしなくてはならない。町の防災無線で休診を知り、不安になった住民から問い合わせが多く寄せられているという。幸い、母校の自治医科大学の後輩で群馬大学に勤める医師が、代診を快諾してくれた。
救急医をしていた頃、脳卒中患者を多く受け入れていた。脳梗塞でも、リハビリの末に回復していく患者にも数多く遭遇した。自分もきっと回復すると信じ、翌朝から、いつも通り午前5時に起床。軽く体操をして、気分を上向かせた。リハビリ以外は時間を持て余し、高校野球の中継に見入る毎日で、食事は最大の楽しみとなった。
初期臨床研修と救急医の研修、3年を過ごした古巣の群馬大学病院では、コロナ禍ながら、大勢の医師たちが見舞ってくれた。真っ先に病室を訪れたのが、救命医学の教授だった。救急医療の研修を受け博士号も取得しながら、地域医療に転進した金子は、大いに恐縮した。研修医時代の同期、救急科の同僚たち、さらには自治医大の同窓の仲間たち……口々に「働き過ぎだから、休んだほうがいい」と、励ましの声を掛けてくれた。
日頃、医師にとって最も身近で頼りになるのは看護師だが、患者になってみると、その存在感は別格だった。「声を掛けてもらうと、本当に安心する。“天使”という言葉は、大げさではない」。1週間入院し、翌週金曜日に退院した。左手の麻痺はだいぶ改善し、7割方戻っていた。自宅療養1週間を経て職場復帰することになった。
ダイエットで肥満解消も不養生を反省
最終的な診断は、アテローム血栓性脳梗塞だ。危険因子は、脂質異常症、糖尿病、喫煙、家族歴、座りがちの生活、肥満……などが知られている。生活習慣のツケと言ってもいい。
金子は、1日1箱のたばこを吸う。飲酒も好きで、状態の悪い患者の往診が控えていなければ1日2〜3合を飲む。体重は学生時代には80kg台だったが、研修医となって不規則な生活の末、1年目の終わりには96kgにまで増加した。定期健康診断で、中性脂肪が1000mg/dLを超えたこともあった。長野原町の診療所に赴任する頃から、本気で痩せたいと考えた。細かな食事制限は自分には向かない。本を読み漁った末、16時間飢餓状態に置くことが効果的と分かり、昼食を食べないことにした。少し体が軽くなると、ランニングにも精を出し、12カ月で70kg台の体重を取り戻した。
「肥満」のリスクが消えていたことはプラスだが、脳梗塞は起きた。「医者の不養生」そのものだ。軽症で職場復帰も叶ったが、再発予防のために自省。休肝日として、アルコールを飲まない日を設けることにした。
肩の力を抜いて優先順位を付ける
休職から2週間、4月初めに職場に戻った。本調子とは言えない中で、仕事は山積していた。いつも以上に気合いを入れ、自分を奮い立たせた。患者にも伝わったようで、「頑張り過ぎないで」と声を掛けられた。励ましや感謝を伝える手紙を手渡されることもある。患者にとって自分が大きな存在になっていたと改めて認識すると共に、自分にとっても、かけがえのない場所だと痛感した。
入院中も、患者家族から在宅での看取り希望があった。復帰後で間に合いそうだと、引き受けたが、金子の退院を待たずに患者は施設で亡くなった。「自分が病気にならなければ、自宅で最期を迎えられたのではないか」。家族に電話すると、入所していた施設でコロナ感染者が出て自宅に戻れなかったと判明したが、一抹の後悔が残った。
病気発症前の金子は、「頼まれた仕事は断らない」がモットーだった。町の診療所の医師には、母子保健、学校医、介護保険事業など、日常診療以外にも様々な依頼がある。加えて、自治医大の学生の実習や群馬県内の高校生の診療所見学にも対応。突発的な新型コロナも襲った。「優先順位を付けて少し肩の力を抜かないと、自分の健康が冒され、へき地医療の継続が揺らぎかねない」。
研修医向けウェブサイトで毎月の連載を執筆し、一時は並行して地元の上毛新聞にも寄稿していた。「へき地医療に関心を持つ人を増やす一助に」と考えるからだ。種は着実に芽吹いている。連載を読んだ東京の高校生が、はるばる見学に来た。高校生向けに、へき地医療のオンライン講演も実現した。
1日に外来で診る患者は約50人。着任前は年間5000人程度だったが、4年目には7000人を超えた。訪問診療や在宅での看取りも増えた。看護師は当初2人だったが、3人にしてもらった。患者はなお増え、年間8000人を超えた。うち、35%は15歳以下の子どもたちだ。
小児や皮膚疾患の患者も多いため、日々知識を蓄えている。プライマリ・ケア認定医の資格をはじめ、認知症サポーター養成講座、かかりつけ医機能研修(日本医師会)を受け、介護支援専門員の資格も取得した。専門を問われれば、胸を張って「長野原町」と答える。自治医大の義務年限を果たすといったスタンスから、今は天職と考え、定年の70歳まで勤め上げる決意を固めている。
闘病から2年半を経て、麻痺は完全に消え、野球をするのにも支障がない。気力・体力とも充実している。定期的な経過観察でも異常はなく、医師と相談して抗血小板薬を中止することにした。
25年春には、廃校になった町の小学校に診療所を移転する計画を進めている。今までなかった内視鏡室を作り、診察室も2つにする。教育にも力を入れ、家庭医療の専門医のプログラムにも参画したい。介護と円滑に連携する青写真もある。
病を得たことで、スタッフ、家族、町民たちのありがたさが身に染みた。完全復活して願うことは、全人生を賭けて「医者になる」ことだ。「信頼されて拠り所となる人間となり、良い医者だったと振り返ってくれる人がいれば本望だ」。(敬称略)



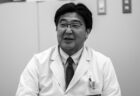
LEAVE A REPLY