北村 聖(きたむら・きよし)
公益社団法人地域医療振興協会 顧問、東京大学 名誉教授
留学先: Stanford University(1984年3月〜86年6月)
卒業から研究まで
1978年に東京大学を卒業し、すぐに内科の臨床研修を始めた。その当時は、内科は卒業して2年間の内科研修を終えた後に入局先を決めるので、私は、1年目の前半を東京大学医学部附属病院第3内科で、後半を第2内科で研修した。それぞれ大講座制で、疾患の偏りもなく広く患者を診ることができ、研修2年目は、大久保にあった社会保険中央総合病院(当時)の内科でより実践的な研修をした。
研修が終わり、第3内科の血液グループに入局したが、卒後3年目、今でいう専攻医の初年は国立病院医療センター(当時)の血液内科に出された。骨髄腫の我が国の第一人者の今村幸雄先生が部長で、ここでは、ほとんどの時間は血液内科医として診療にあたったが、少しだけ研究というものの一端を垣間見ることができた。市中病院と雖も、今村先生は極めて研究熱心で、ご自分が今まで受け持った骨髄腫の患者血清をすべて保存して、M蛋白の解析を考えておられた。今村先生からは多くのことを学んだが、研究についていえば、第1に医師の行う研究は患者に基づいていなければならないということ、言い換えれば臨床研究を目指すこと、第2に今まで血液内科ではあまり注目されていなかった免疫担当細胞がこれから面白くなるということを学んだ。
国立医療センターには1年半いて、その後東大第3内科血液研究室(第6研究室)で診療と研究の二足の草鞋生活が始まった。当時の第6研究室は森眞由美先生と浅野茂隆先生が主宰されて、その後、浦部晶夫先生が研究室を運営された。第3内科の研究は自主性に任されていたが、なかなか最先端の知識や技術を取り入れるまでにはいかない状況であった。1学年下に平井久丸先生(後の東京大学血液・腫瘍内科教授)が入局して当時の最先端の遺伝子操作技術を取り入れたことで、研究が活発になった。私も免疫分野の最先端に触れてみたいと思い、着任されたばかりの髙久史麿教授にお願いして、東大免疫学教室に国内留学を許可してもらった。
免疫学教室 多田研究室
多田富雄教授の研究室は、奥村康講師と2人の助手と多くの大学院生がいる、極めて若い研究室であった。私の仕事は研究生として大学院生の研究を手伝うことから始まった。私がついたのは烏山一先生(現:東京医科歯科大学高等研究院特別栄誉教授)で、右も左もわからない私に一から教えてくださった。多田研究室は基本的に自主性というものはなく、サプレッサーT細胞の解析が目的で、すべての人が1つの方向を向いていた。当時の大学院生では、中内啓光先生(東京医科歯科大学特別栄誉教授)、山本一彦先生(東京大学名誉教授)、安部良先生(帝京大学教授)などがおられ、公式の研究室会議(英語)の時だけでなく、四六時中、世界の免疫学の動向について口角泡を飛ばして議論した。そんな中、中内先生は米スタンフォードへ、山本先生はドイツへ、烏山先生はスイス・バーゼルへと留学が決まり、自分もいずれは留学したいと切に願うようになった。多田研で学んだことは、いわゆる「梁山泊効果」「イモ洗い効果」で、学修とは意識の高い学生が議論することで最も有効に行われることを知った。このことは生涯を通じて貫く信念のようなものとなり、「教育とは議論である」と伝えている。
スタンフォード大学での留学
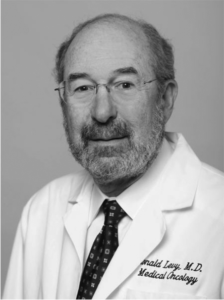

学位を取得し、1つの論文を仕上げることができたのを機に、留学することを決断した。奥村講師、中内博士のご尽力により、84年3月にスタンフォード大学腫瘍学教室Ronald Levy教授のもとに留学することができた。教室が取り組んでいたのはモノクローナル抗体mAbによるリンパ腫の治療であり、私に与えられたテーマはマウスのリンパ腫細胞株を用いて、細胞株をワクチンのように接種することにより特異的抗腫瘍免疫を誘導することであった。
米国に到着して右も左も英語もわからない自分に最初に与えられた仕事はグラントの獲得であった。手伝ってもらって米国血液学会のグラントに応募する書類を書き上げ、その結果、自分の給料分程度の研究費を得ることができた。同僚がこれで研究者として自立できたようなことを言ってくれて、ちょっと誇らしい気がしたことを覚えている。
Levy研究室に初めて来た日本人留学生は札幌医科大学から藤本純一郎博士(国立成育医療センター病理部長)で、そのあとに私と、札幌医大から今信一郎博士が同時に2代目として来たことになる。私はがん免疫の誘導の研究で、今先生はその当時、猛烈な勢いで流行りだした遺伝子を用いた研究だった。
研究に関して、最も記憶に残っているのは、留学してほぼ1年がたったころ、スタンフォード大学の免疫関係の研究室の若手研究者(院生やポスドク)の共同研究発表会が近くのモントレー半島のロッジで開かれたことである。1年間の研究成果を発表し、怒涛のような質問に答え、同僚に「よかった」と言われたことが強く印象に残っている。崖から突き落とすような教育であるが、強烈なインパクトがある教育方法である。
スタンフォードの研究システムは、多田研の時と同様、先輩研究者とペアで研究するスタイルで、私の直接の指導に当たってくれたのは腫瘍内科医師のMark Kaminski先生で、週1日程度の大学での外来と、夜の当直などをしながら、研究をしていた。日本と同じで、臨床と基礎研究の二足の草鞋は、基礎科学者から見て研究がどうしても雑になるように思う。Markの奥さんは、大学病院の看護師で、家族ぐるみのお付き合いをした。
スタンフォード時代の楽しみ
半年遅れで、2歳の長女を連れて、妻もスタンフォードにやってきた。幸い神経免疫の教室でポスドクの採用があり、朝、長女を保育園に預けて、2人で研究者として過ごすことができた。週末は日帰りドライブでサンフランシスコ、モントレー・カーメル、ナパバレーなどに行った。夏休みやクリスマス休暇は数泊して西海岸をドライブした。南は最南端のサンディエゴ、北はオレゴン州まで、西海岸を移動した。東大第3内科での先輩の留学報告会では、ほとんどが東海岸の大学で、西海岸の留学者はいなかったと思う。たぶん私が初めてであり、気候の良いシリコンバレーは天国に一番近い半島と思えた。
帰国後
2年半の留学を終え86年夏に帰国し、東大第3内科の助手になった。髙久教授の計らいで、血液免疫研究室を作っていただき、そこで研究を続けることができた。日本で最初のマウスmAbを用いたリンパ腫の治療を行ったのもこの頃である。教室の壁を越えて、物量内科の若手たちと研究会を開催したりして、血液内科医と免疫研究者とを目指していた。その後、検査部への移動があり、自分の興味も医学教育のほうに移ったが、留学を挟んでの免疫研究者としての経験は何物にも代えられない貴重な体験であり、医学教育者としても大いに役立っている。





LEAVE A REPLY