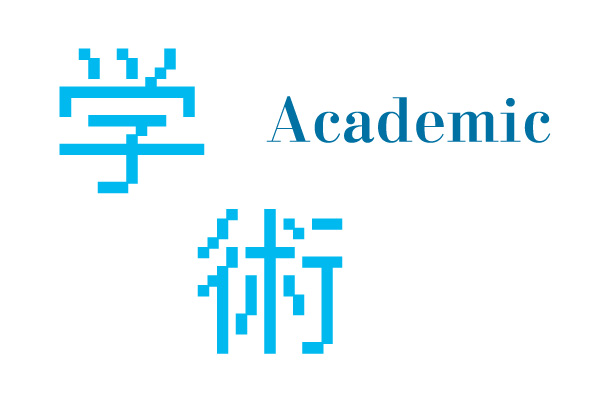
妊婦や家族に寄り添い支える検査を目指して
出生前診断を受ける妊婦が増加している。血液から染色体異常の有無やリスクを判定するNIPT(無侵襲的出生前遺伝学的検査)の普及によって検査が受け易くなった事や、高齢の妊婦の増加等が要因だが、女性自身が自分の身体を知りたいと考える様になった事も一因にある。
一方で、染色体異常の有無の判定を目的とした検査は「命の選別」に繋がるとの批判もある。日本医学会等はNIPTの検査前に遺伝カウンセリングの実施を義務付ける医療施設の認証制度を運用しているが、カウンセリングを実施しない非認証施設が増えているのも事実だ。こうした中、遺伝カウンセリングに携わる医師やカウンセラーはどの様に妊婦や家族、生まれて来る命に向き合うのかが問われている。2023年7月7日から9日まで長野県松本市で開かれた「第47回日本遺伝カウンセリング学会学術集会」では、遺伝カウンセリングの現状や課題について活発な議論が交わされた。
出生前診断の受検者数を集計した正確なデータは無いが、18年に国立成育医療研究センター等のチームが発表した調査結果によると、16年に行われた出生前診断は約7万件、10年前に比べて約2.4倍に増えたという。16年以降、日本医学会等の認定を受けていない施設が増加しており、年間の受検者は更に増えていると予測される。妊婦の数が減少している事を考えると、受検者の割合も高くなっている筈だ。
危険性が無く確度も高いNIPT
出生前診断というと、多くの場合18トリソミーや13トリソミー、ダウン症候群といった染色体疾患が想定される。従来行われて来た絨毛検査や羊水検査はこれらの疾患の確定診断の為に用いられるが、他の染色体疾患全般についても検査が出来る。但し、腹部に針を刺して羊水や絨毛を採取する為、僅かだが流産の可能性が有る。
一方、流産の危険性が無いのが超音波ソフトマーカー検査やオスカー検査、クアトロテスト、そして最近増えているNIPTだ。超音波検査やオスカー検査も精度がかなり高くなっており、ダウン症であれば90%以上検出出来る様になった。これに対し、NIPTは羊水検査等に近い確度でダウン症を検出する。他の染色体疾患も検出が可能だが、ダウン症候群等の3疾患に比べ、羊水検査程の確度が無いのが限界とされる。
海外では「リプロダクツライト」を最優先
NIPTは妊婦から採取した血液に含まれる胎盤(胎児と同じDNAを持つ)のDNAの断片を分析し、18トリソミーや13トリソミー、ダウン症候群といった染色体異常の有無やリスクを判定する。特にダウン症の検出率が高く、陰性的中率は99.99%となっている。
一般に「新型出生前診断」とも呼ばれるが、厚生労働省の「NIPT等の出生前検査に関する専門委員会」は2021年の報告書で「検査法が確立されてから年月が経っているにも拘わらず新型と形容する事は適当ではない。又、当該検査は確定的検査ではない事から、新型出生前診断との名称は不適当である」との見解を示している。
NIPTの現状だが、日本の受検者数が増えたといっても欧米と比較すると雲泥の差がある。海外先進国では全妊婦に選択肢が提供されるべきとの考えが前提であり、日本の様に妊婦不在での議論は無い。オランダでは出生前検査の第一選択として実施されている他、イギリスやスウェーデン等では検査費用の公的補助も受けられる。
ドイツでは検査後の相談支援体制が制度化されており、妊婦は陽性結果が出た場合の選択等について無料で相談出来る他、イギリスでも民間のチャリティ組織が妊婦のサポートを行っている。
日本では13年からNIPTの検査が始まったが、検査が優生思想に繋がり兼ねないとの懸念や、妊娠を継続するかどうかの自己決定を支援する体制が必要だとの考えから、日本医学会や日本産科婦人科学会等の関係5団体は検査に先立ち、認定制度を設けた。同制度では遺伝子カウンセリングや妊婦への情報提供等に関するルールを定め、それに基づいて検査を行う医療機関を認定施設とした。その後、22年に認定制度に代わる「出生前検査認証制度」が発足したが、全国で僅か400程の医療機関や検査分析機関しか認証を受けていない。患者満足度が低い理由が見える。
妊婦に対するフォロー不足が課題に
日本の医学界はNIPTの厳格な運用を求めているが、16年頃から非認定施設でも検査を行う様になり、認証制度に代わった今も非認証施設は増えている。非認証施設といっても医療機関である訳で、認証施設と変わらない精度の検査が受けられる。即ち、施設が信頼出来る検査会社を利用している事が重要なのだ。例えばベルギーのGENDIA社は、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア等に遺伝子研究所を置き、検査の信頼度は世界一と目されているが、日本から検査を委託しているクリニックは残念な事に僅かだ。
検査の早さや申し込みの手軽さ等をアピールし、受検者を増やしている施設も有る。又、18トリソミーや13トリソミー、ダウン症候群の他、性染色体異常や微小欠失症候群の検査、全ゲノム検査、単一遺伝子疾患等の検査にも対応し、独自性を打ち出している施設も多い。
しかし、産婦人科医や小児科医が常駐していない施設も存在し、十分な遺伝カウンセリングや情報提供が行われていないケースも見られる。そうした施設では、胎児の疾患が判明した後に適切な対応が取られない可能性が有るとの指摘もなされている。日本産科婦人科学会の「周産期遺伝に関する小委員会」が行ったアンケートによると、ターナー症候群が陽性となった妊婦に「羊水検査の必要はありません」と誤った説明をした例や、13トリソミーや18トリソミー以外の異常を示す結果について十分な説明が行われなかった例が見られた。
又、ダウン症候群で陽性判定が出た妊婦に対する適切なフォローが行われなかった為、妊婦が混乱し精神科を受診しなければならなくなった症例も有ったという。同委員会は「適切な説明、その後の管理と心理的なケアを包括的に行える体制で検査を実施する事が重要だ」と指摘している。
意思決定を支える関係構築が重要
今回の学会の大会長を務めた信州大学の古庄知己教授は03年から信州大学で遺伝カウンセリングを軸に遺伝医療や遺伝学教育等に取り組んで来た。
古庄教授は1993年に大学を卒業した後、新生児医療を目指し、18トリソミーの子供を受け持つ様になったが、当時は積極的な治療は行われず、「看取りの医療」が主だったという。しかし97年に長野県立こども病院で研修を受けた際、18トリソミーの子供に対して新生児集中治療が行われている事を知り、2003年に信州大学に赴任した後、積極的治療を受けた子供の追跡調査を行い論文にまとめた。論文はAJMGAに掲載され、内容は家族の日常生活や親の思い等が中心だった。子供を育てる事に前向きな親と、その愛情に応える子供という、ごく普通の幸せな家庭の日常を紹介した事で、「18トリソミーの有る子供に対して積極的治療を行う事で何が起こるのかを世界で初めて示した」と高い評価を受けた。
こうした事から、古庄教授は13トリソミーや18トリソミーといった遺伝性疾患を持って生まれて来る子供に対する積極的治療を提唱している。
遺伝カウンセリングで古庄教授が大切にしているのは「よりそい支える」姿勢だと言う。そして、自分の子供に遺伝性疾患がある事を受け入れ、決断し、再起している家族の姿から、人間の優しさやしなやかさ、強さ、家族の温かみを学んで来たと振り返る。
大会長講演で古庄教授は、遺伝カウンセリングについて、ダウン症候群等の遺伝性疾患の有る子供が地域でどの様な支援を受けられるのか、具体的で詳細な情報を提供する事の重要性を強調した。ダウン症の事は理解しているという出生前診断希望の夫婦でも、実際にダウン症の子供が地域でどの様な医療や療育、教育、福祉的支援を得られるのか迄は知らない事が多いと言う。そして、遺伝性疾患が判明した時にしっかり意思決定をして貰える様、関係性を築く事が大切だと指摘。受検者の態度も見ながら、考え方や事情に合わせて臨機応変に対応する事も必要だとした。
更に古庄教授は遺伝学的検査の意義についても述べ、正しい検査で遺伝性・先天性疾患が明らかになり、依頼元のドクターやチームが安心して診療を進められる様になれば、患者や家族の健康・安心にも貢献出来るとした。
優生思想への傾斜を防ぐのは倫理観
学会では、日本の遺伝カウンセリングの歴史に詳しいクリフム出生前診断クリニック副院長の千代豪昭氏が「わが国の遺伝カウンセリングの歴史—実現された夢とこれからに託す夢」と題して特別講演を行い、反優生思想と結び付いた「羊水検査反対運動」と遺伝カウンセリングの関わりや、臨床遺伝専門医制度や認定遺伝カウンセラー制度発足の経緯について振り返った。
千代氏によると、現在の遺伝カウンセリングに繋がる「遺伝相談」は1956年に日本遺伝学会から分離独立した日本人類遺伝学会で始まった。しかし、羊水検査が日本でも行われる様になった65年頃から、羊水検査は優生思想に繋がり兼ねないとの懸念から学会内で意見が分かれ、社会的にも羊水検査に反対する声が高まって行った。そして75年、兵庫県の「不幸な子どもの生まれない運動」事件を受けて、羊水検査反対運動が全国的に広がり、日本人類遺伝学会から日本臨床遺伝学会が分離独立する切っ掛けともなった。
「不幸な子どもの生まれない運動」事件は、兵庫県に設置された「不幸な子どもの生まれない対策室」を巡る混乱の事で、当初、県では「不幸な子ども」について、遺伝性疾患の子供や障害児だけでなく、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶児や死産の胎児、生まれて直ぐに死亡する新生児などを想定していた。ところが、県が75年に羊水検査費用の公的援助の方針を打ち出した所、批判が殺到。公的援助の方針の撤回だけでなく、同対策室は廃止に迄追い込まれた。更に81年、大阪府立母子保健総合医療センター(現・大阪母子医療センター)が開設された際には、出生前診断に反対する府民らが開所式に集まり、駅から病院の玄関まで車椅子で埋め尽くされるという出来事も起きた。これにより、新病院に設置される予定だった羊水検査室が封鎖されるという事態にもなった。
この事件以降、特に関西では、遺伝学は出生前診断に繋がる「差別の学問」という認識が浸透し、遺伝学にとって暗黒の様な時代となったという。
こうした状況は、遺伝子研究の高まりを受け、ヒトゲノムや遺伝子解析研究に関する倫理指針が議論された事で一変した。この指針において遺伝子提供者への遺伝カウンセリングが義務付けられ、2001年に国立循環器病研究センターに遺伝カウンセリング室が開設された。これによって遺伝カウンセリングは患者の権利を守る医療の一種と見なされ、遺伝学を差別の学問と見る風潮は薄れて行った。
こうした歴史的背景を踏まえ、千代氏はリベラル優生主義の観点から、クライエント(相談者)中心のカウンセリングにビーチャムとチルドレスの医療倫理の4原則を加味する事で、嘗ての優生思想の拡大を阻止すべきではないかと指摘。科学技術や先端技術の発達が「善」となるのは医療従事者の倫理観が前提であり、研究者の不適切な功名心や商業主義と結び付くと、患者の不利益だけでなく「社会悪」になる場合が有るとの持論を述べ、優生論への傾斜を防ぐには研究者や医師の倫理観が重要になるとの考えを示した。又、現代生命論の知識も遺伝カウンセリングに積極的に活用すべきだとした。
遺伝カウンセリングは人生が懸かった局面
「NIPT最前線:新たな出生前検査認証制度が始まって: NIPTを含む出生前診断に真摯に取り組むCGCたち」と題したシンポジウムでは、3名の認定遺伝カウンセラーが遺伝カウンセリングの実情や検査を受ける両親の苦悩とどう向き合うか等について講演した他、畑谷史代・信濃毎日新聞論説委員が取材を通じて感じたNIPTの在り方や課題について語った。
最初に講演した黄瀬恵美子・認定遺伝カウンセラーは、自身が所属する信州大学医学部附属病院の遺伝カウンセリングの体制と実情について報告した。
同病院では、検査を希望する夫婦らに対し、認定遺伝カウンセラーが検査を希望する理由や経緯を聞き、検査内容について説明しながら約1時間のカウンセリングを行っている。更に臨床遺伝専門医と共に、受検後の選択肢や染色体異常が有る子供を育てて行く場合の医療福祉制度等を説明し、検査を希望するか再度確認している。
この結果、実際に受検するのは、最初から受検を悩んでいた夫婦らを含めて半数程度だという。又、妊娠継続を断念した妊婦に対しては必要に応じて精神科医がフォローしているが、精神科の助けを必要とする妊婦も多い。
そうした実情を踏まえ、「遺伝カウンセリングは胎児の命とカップルの人生が懸かった重大な局面」と指摘。カウンセリングでは時間を掛けた傾聴や正確な情報提供、信頼関係の構築が必要不可欠で、検査後も産婦人科、遺伝子医療部門、精神科等が長期的、包括的に支援して行く事が大切だと述べた。
順天堂大学医学部附属順天堂医院の渡辺基子・認定遺伝カウンセラーは、ドイツの出生前検査に関する遺伝カウンセリングについて紹介した。ドイツでは遺伝カウンセリングが法制化されており、NIPT等の非侵襲的検査は保険でカバーされる。又、ドイツには病院とは別に妊娠カウンセリング施設が有り、妊娠中絶前には必ず妊娠カウンセリングを受けて、最終的に妊娠を継続するかどうかを決める事になっている。出生前検査後のカウンセリングもこの施設で行われるという。
妊娠中絶前のカウンセリングは「妊娠葛藤カウンセリング」と呼ばれ、妊娠中絶を希望する理由を聞き、出産した場合に受けられる支援について説明する等、様々な情報を提供する。妊娠を継続するか断念するかは妊婦の自律的決定が尊重され、カウンセリングに当たる医師やカウンセラーは非指示的で中立的な言動が求められる。
東京女子医科大学病院ゲノム診療科の浦野真理氏は、同病院が1990年代から実施している、デュシェンヌ型筋ジストロフィーや福山型筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症といった単一遺伝性疾患の出生前診断について述べた。この場合の出生前診断は、既にこれらの疾患に罹患した子供を持つ妊婦が対象で、これ迄検査を実施した胎児の約25%が陽性判定となった。病気が確定した場合、多くの親は妊娠中絶を選択するが、中絶への苦悩や、健康な子供を妊娠出来ない事の悲しみ、絶望感等が見られると言い、検査後のフォローアップの重要性を強調した。
出産の自己決定には支援体制が不可欠
信濃毎日新聞の畑谷史代・論説委員は、女性が他者から強要されずに産む・産まないを自己決定する「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の中にNIPTをどう位置付けるかが今後の課題になって行くとした上で、「その前提として、夫婦が熟慮するプロセスの保障と、十分な情報提供とリテラシーの確保が重要」と指摘。「妊婦に提供される情報が一面的では、自己決定が保障されているとは言えない」と述べた。
又、NIPTには出産後の生育環境を準備する意味合いが有る以上、「疾患や障害の有る子供の支援の在り方について社会的な議論が起きて然るべきだ。最善の医療や福祉教育が提供され、成人になった後も地域の一員として暮らせる環境が十分に整っていないと、選択の幅が最初から狭められる事になる」として、遺伝性疾患の有る子供とその親の支援体制の充実に注力する必要性を訴えた。
会場との意見交換では、出生前診断によって様々な染色体異常がかなりの精度で把握出来る様になった現状を踏まえ、「ゲノム検査の進歩で遺伝カウンセリングが今後更に難しくなって行く」と指摘した上で、「胎児は既に人間であるという観点から胎児の医療を進めると共に、妊婦の自己決定権を保障する体制も必要ではないか」との意見も出された。
最後に、座長を務めた産科医の金井誠・信州大学医学部教授は「妊婦健診は本来、妊娠や胎児の成長を喜ぶ妊婦と、それを支える医療者にとって楽しい時間だった筈だが、NIPTの情報提供を間違えると、何の悩みも無かった女性が妊娠によって悩みを抱えてしまう事になり兼ねない。又、現場の医療者も、検査結果を全て伝えなければ訴えられるのではないかと懸念する恐れが有る。そうした社会にならない様、我々も専門家として正しい情報を発信して行く必要が有るのではないか」と議論をまとめた。



LEAVE A REPLY