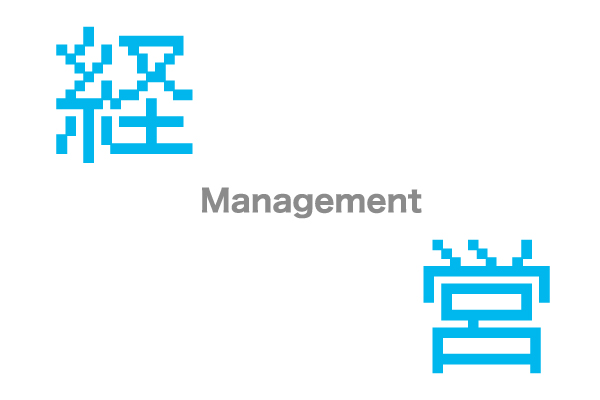
身体拘束解除は医療における倫理的課題
2022年度診療報酬改定の議論も大詰めだ。次期改定は、新型コロナウイルス感染症への対応に加え、団塊の世代が後期高齢者入りする25年、更に現役世代が劇的に減少する40年を見据えた改革が焦点になっている。
医療機関は、先ず25年の波を乗り切らなくてはならない。高齢者の急増につれ、右肩上がりに増加しているのが認知症患者だ。当然ながら、感染症や外傷を始めとして、身体疾患を併発する認知症患者も増加する。精神科や慢性期の病院だけでなく、急性期病院でも、認知症患者への対応は避けて通れない課題である。
15年に厚生労働省が策定した「認知症施策推進総合戦略〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜(新オレンジプラン)」においては、認知症患者が身体疾患に罹患しても適切な診療を受けられるよう、急性期病院には認知症患者の対応力を、又、精神科病院には身体疾患診療の対応力を高める事が謳われている。翌16年度の診療報酬改定では、「認知症ケア加算」が新設された。
身体拘束をしない医療・ケアへの取り組み
認知症の高齢患者は、入院によってせん妄や転倒等のリスクが高まる。この為、安全管理を目的として看護師が身体拘束(抑制)をする事が多くなる。
認知症患者と最前線で向き合う医療職と言えば、やはり看護師だ。日本老年看護学会は16年、「急性期病院において認知症高齢者を擁護する立場表明」を発表。その中では、「身体拘束を当たり前としない医療・ケア」が掲げられている。急性期病院においても、ICU等を含めて、全ての病棟で身体拘束の解除が命題となっている。
身体拘束を最小化する為の政策の流れを振り返ってみる。
厚生労働省は01年に『身体拘束ゼロへの手引き』を策定し、介護保険法により高齢者施設での身体拘束は原則禁止とされた。病院においては、16年の「認知症ケア加算」では、身体拘束を行った当該日は診療報酬の減算対象とされた。18年度改定では、看護補助者の配置で加算を算定する場合の要件に、身体拘束等の行動制限の最小化が求められるようになった。認知症ケア加算は20度年改定で更なる見直しが加えられ、要件が強化された。
認知症患者は、何重もの困難を抱えている。自身の身体状況を把握し、症状や苦痛を訴える事が難しい為、病状の発見が遅れがちになる。また診療の同意や協力も得にくく、入院時には病状が悪化している事が多い。更に退院出来たとしても、その後の健康管理が十分でない為に再入院となる事も少なくない。
そして、認知症患者の最大の問題は、入院に伴って行動・心理症状(BPSD)が引き起こされる事で、これが病棟でトラブルになりかねない。また、患者自身のリスクも高まり、ルート抜去が高頻度で起こり、睡眠障害や易怒性等も生じかねない。
病院ではこのBPSDに対処する為、入院時に患者家族から、身体拘束と、必要時には向精神薬を使用する許可を得る事になる。それでも人員の少ない深夜に患者が行動的になり、易怒性が高いといった場合、当直医や看護師が対応出来ず、家族に引き取りに来てもらうケースもあるという。身体拘束を行うと、患者のADLが低下し、入院日数が長くなるという悪循環も生じてくる。
そうした中で、先駆的な病院の取り組みが広がっている。例えば、金沢大学附属病院(石川県金沢市、830床)は高度急性期病院であるが、14年から看護管理者が中心となり、「身体拘束をしない看護」への挑戦を実践しており、他院から注目されている。
慢性期病院で、身体拘束の解除に熱心なのは、大誠会グループ(本部・群馬県沼田市)である。同グループにおける認知症ケアは、「認知症の人の立場に立って考え、ケアを行う」というパーソン・センタード・ケアの考えをベースとしており、身体拘束はしない。そして、「脳活性化リハ5 原則」として、①快刺激②ほめ合い③コミュニケーション④役割⑤エラーレスを基本にした関わりを持つように努めている。これによりBPSDが軽減されて、適切な場所への退院や退所へと繋がっている。
もちろん認知症サポートチーム(DST)も組織されており、看護管理者、病棟リンクナース、理学療法士、作業療法士、薬剤師、精神保健福祉士、相談員、認知症看護認定看護師らが参加している。回診では、内服薬を調整したり、リハビリテーションやケアについての問題を共有したりして、ケアの負担を減らす事を重視している。
先進国では人権侵害に当たる、認知症患者の抑制

認知症ケアは、多職種で当たる時代である。医師にも積極的な参加が求められる。DSTに参加する医師には、主に3つの役割が求められている。先ず医学面では、入院患者の認知症の診断、認知症の危険因子のチェック、認知症悪化やせん妄の原因になり得る薬剤のチェック等だ。次に教育面で、病棟スタッフとの議論や院内研修を企画して講師を務める事だ。そして経営面では、経営への貢献をアピールし、他業種のチームへの協力依頼や業務の調整を図る。
近年、ケアの現場で「ユマニチュード」が注目されている。これはフランス発祥のケア技法で、主に認知症のケアに有効とされている。知覚・感情・言語による包括的コミュニケーションに基づき、相手を大切に思っていると伝える事を重視した手法で、患者がケアする人を“いい人”と認識し、受け入れてもらえるようになる。
開発したのは、体育学の専門家イヴ・ジネスト氏とロゼット・マレスコッティ氏である。これを日本に紹介したのは、医師で国立病院機構東京医療センター総合内科医長の本田美和子氏(現・日本ユマニチュード学会代表理事)である。11年に渡仏して研修に参加し、日本での普及を始めており、介護現場を皮切りに、医療機関でも徐々に浸透しつつある。正しく学んで実践すると、激しい認知症症状やアパシーを抱えた人に自発性が芽生え、劇的に変化する事がある。
さて、組織的な対応としては、「責められる文化」の弊害が有り、こうした文化を持つ施設が、身体拘束を助長する傾向が指摘されている。これは、インシデントの発生や、発生させた職員を責める傾向にある施設の事だ。周りから責められると思えば、やむを得ず身体拘束が選択される。出来なかった事を責めるのでなく、肯定的に認め合う中で学び合い、連帯感を持って協働出来るポジティブなマネジメントを進めていかなくてはならない。
日本の急性期医療の現場では、「身体拘束はやむを得ないもの」という認識が根強い。しかし、諸外国に目を転じれば、欧米やオーストラリアなど多くの国では、認知症が進行した人に身体拘束して医療を提供するのは、明確な人権侵害と位置付けられている。フランスは欧州諸国の中では身体拘束率が高いが、患者の覚醒時と鎮静時に身体拘束を行う行為はしないと言う。
身体拘束は、高齢者の人権擁護に関わる倫理的な問題で、医療機関は正面から向き合う必要が有る。


LEAVE A REPLY