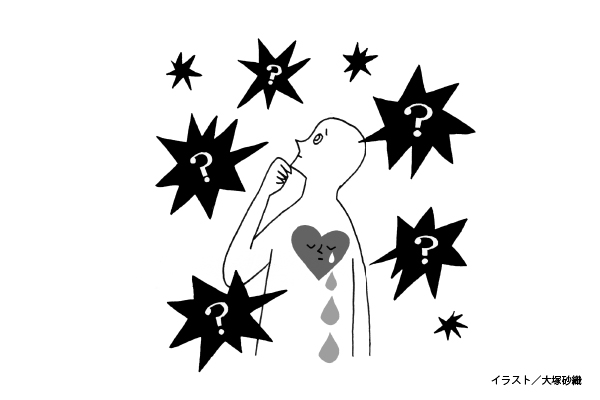
私の専門は精神科だが、思うところがあって数年前から大学病院の総合診療科外来で身体診察や診断の勉強をさせてもらっている。今回はそこで気づいたことを書いてみたい。
その外来には、地域のクリニックからたくさんの患者さんが紹介されてくる。多くはそこで診断が決まらなかったり服薬してもなかなか症状が消えなかったりして、「ご精査お願いします」という診療情報提供書を携えて受診する。
もちろんその中には、きわめてレアな疾患やわかりにくい悪性腫瘍、感染が潜んでいるケースもある。そうなると総合診療歴が短い私にはお手上げで、プロブレムリストや検査所見を示しつつ、そこに長くいるドクターに相談することになる。ときには「では、これからはこちらの医師が引き継ぎますので」と“選手交代”となることもある。
一方で、原因不明の不調の背景に心因が絡んでいるケースも少なくない。そうなった場合、数回でなんとかなりそうと見越したときは、そのまま私が担当して「総合診療科外来での精神療法」を行わせてもらう場合もある。ただ、明らかな統合失調症やうつ病、発達障害が不調の大きな原因と思われるときは、ためらわずに院内のメンタル科に紹介する。
こういう話をすると、地域の非精神科開業医である読者の中には、「診断不明の患者さんを脳神経内科、膠原病科、総合診療科など詳しい検査をしてくれる専門の科に紹介すべきか、それともメンタル科なのか、どうやって見分ければよいかわからない」と思う人もいるかもしれない。そこでひとつ、簡単で有益な方法をお伝えしたいと思う。
「大きい出来事」の有無をきいてみる
それは、もしその患者さんが以前からのかかりつけではなく、最近、受診した人であれば、「昨年や今年、何か大きな出来事はありませんでしたか」ときいてみることだ。意外なことにこれをしていない、という内科医などがけっこういるのだ。
たとえば、こんなケースがあった(プライバシーに配慮して細部は変更してある)。ひどい立ちくらみとめまいで学校の体育や行事になると必ず倒れる、という中学1年生の女子が父親とやって来た。地元のクリニックからは、「起立性調節障害、貧血、不整脈、内耳や脳内疾患、甲状腺機能異常、月経前緊張症候群などを疑い、いろいろ検査してみましたが、いずれにもあてはまりませんでした」と詳しい検査所見が記された診療情報提供書が送られてきていた。とても熱心なドクターのようだ。
患者さんは父親とともに入室したが、ふたりとも聡明な印象で、父子仲も良さそう。父親は「元気だけが取り柄だったのに、どうしてこうなっちゃったかなあ!」とおどけた口調で場をなごませようとした。
ただ、症状は比較的深刻なのに、本人、親とも笑顔で明るい雰囲気を作ろうとしているのが、精神科医の私からはどことなく不自然に見えた。
それから、「学校では好きな勉強がありますか」など身近な話題から、家族のことや少し過去の出来事などを聞こうと考えて質問を始めて、すぐにこの父子を襲った大きな問題がわかった。
1年前、本人の母親が内臓疾患で亡くなっていたのだ。それからは父親と本人、3つ上の兄と3人で協力してなんとか家事をこなしてきたという。しかも、この春に本人は中学受験をし、母親も進学を望んでいた学校に合格することができたとのことだ。
私は驚き、心からこう言った。
「それはあなたもお父さまも大変な1年でしたね。しかも、中学受験の勉強を続けて合格しただなんて、すごいですね。気を張ってずっと生活してきて、今になって体の疲れがドッと出ても少しも不思議じゃないですよ」
結局、その中学生には2週間ほど学校を休み、父方の祖母に来てもらって食事の支度などをやってもらい、家でとにかくゆっくり体を休める、という生活を送ってもらった。すると、10日ほどでめまいなどはすっかり消え、また元気に登校できるようになったのだ。
50年前のストレス研究が与える重要な示唆
アメリカの心理学者であるHolmesとRaheは、シビアな症状で内科を受診した5000人の患者を対象に、過去10年間にわたる生活上の重大な出来事(ライフイベント)について調査を行った。この調査ではまず「結婚のストレスを50」と定めて、患者への予備調査から各ライフイベントで生じるストレスを点数化した。たとえば、「配偶者との死別…100点」「離婚…73点」「自分の病気あるいは障害…53点」「解雇…47点」「退職…45点」「経済状況の変化…38点」などだ。
そうしたところ、1年間に経験した出来事の点数の合計点が300点を越えた人の約8割が、翌年に何らかの疾患を発症しているということがわかった。逆の方向で言えば、「大きな出来事があった次の年は要注意」となる。出来事の項目は40以上あり、「レクリエショーンが減った…19点」「睡眠の変化…15点」といった細かい項目までチェックしていくと、意外にすぐに200点を超えてしまう。
これが論文になったのは1967年と今から半世紀以上前で、ある意味で非常にシンプルな研究だ。また、ストレスになるライフイベントやそこから生じるストレスも時代とともに変化している。たとえば、今なら「ネットで悪口を書かれる」という項目が高得点で入る一方、職場や仕事を変えるのは当たり前となっているので、Holmesたちが考えた「転職…36点」という点数は高すぎるだろう。とはいえ、「この1年間、何か大きな変化や経験はありませんでしたか」とさかのぼって尋ねる、という発想は今なおとても大切なのではないかと考える。
もちろん、目の前にいる原因不明の不調を訴える患者さんが、昨年合計300点以上のライフイベントを経験したことがわかったからといって、内科医や耳鼻科医がその人にカウンセリングを行うことはできない。
ただ、「どうしていつまでもめまいがするのか。重篤な疾患の見落としがあるのではないか」という考えから、「昨年、大変なことがあったのですね。だとしたら、多少の不調は当然なのではないでしょうか。まずはご自分を休ませてはどうでしょう」と少し余裕を持ってアドバイスできるだろう。
また、患者さんの中には、「つらい経験をわかってくれた」と思うだけで症状が軽減する、という人も少なくない。
そして、この50年以上前のストレス研究は、日ごろ忙しく働くドクターたちにも重要な示唆を与えてくれる。私たちの心身のエネルギーを枯渇させるのは、長時間労働だけではない。生活上のさまざまな出来事も、時として健康に大きな悪影響を与えるのだ。そしてさらに、Holmesらは、その出来事とは、決してネガティブなものだけではなく、結婚、子どもの誕生、昇進などポジティブなものもそこに含まれることを明らかにした。よく念願のマイホームを建てたりめでたく開業したりして、そのあと重病になったという話も聞くが、それは決して“迷信”ではないのである。
「去年はどんな年でした?」
この問いを、患者さんにもそして自分にも、ときおり投げかけてみてほしい。




LEAVE A REPLY