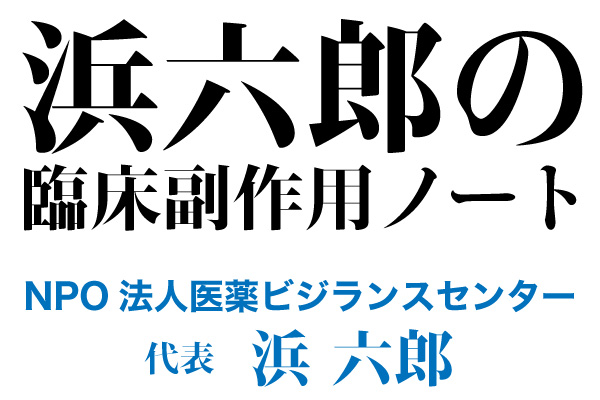
妊娠中の非ステロイド抗炎症剤(NSAIDs)使用は胎児の動脈管閉鎖などのため禁忌である。鎮痛目的では、アセトアミノフェンが安全と考えられているが、重大な害には注意が必要である。今回は、妊娠中のアセトアミノフェン使用によると考えられる動脈管閉鎖または狭窄の報告1)を薬のチェック93号2)で取り上げたので、その概要を紹介する。
動脈管の早期閉鎖または狭窄
動脈管は、胎児期に肺動脈と大動脈をつなぐ血管であり、通常出生後24時間から72時間で閉鎖する。
Allegaertら1)は、妊娠中のアセトアミノフェン使用と胎児または新生児の動脈管閉鎖や狭窄の症例報告のシステマティックレビュー(12文献)で、胎児の動脈管早期閉鎖または動脈管狭窄を25例(うち閉鎖が6例、狭窄が19例)収集し報告した。23例で、動脈管の早期閉鎖または狭窄が出生前に診断され、陣痛誘発または帝王切開による出産につながった例が少なくとも12例あった。
出生時点で、12人の新生児にチアノーゼや呼吸困難、右室肥大、肺高血圧症、肺動脈閉鎖、肺動脈狭窄、三尖弁逆流などの症状や解剖学的異常が認められた。
異常は14例で消失し、そのうち9例では出生前に、 アセトアミノフェンを中止後1週間以内で消失した。
アセトアミノフェンの使用期間がわかっていた例では4日以内が多く、妊娠24〜38週に使用した例が多かった。用量が分かった例では、1日1500mg以上がほとんどであったが、2例では1500mg未満であった。
プロスタグランジン阻害作用による可能性あり
動脈管開存症の症状のある早産児には、動脈管の閉鎖を誘発するために、イブプロフェンやインドメタシンが用いられる。動脈管開存症にはプロスタグランジンの役割が大きく、NSAIDsにはシクロオキシゲナーゼ阻害作用があるためである(日本で動脈管開存症に適応が承認されている薬剤はインドメタシン静注用のみ)。
動脈管開存症に対してイブプロフェンとアセトアミノフェンを比較した4件の臨床試験のメタ解析結果では、両部の動脈管閉鎖効果は同等であった。また、プラセボまたは無治療を対照としたアセトアミノフェンの2件の臨床試験の結果では対照よりも閉鎖効果が強かった。アセトアミノフェンは、シクロオキシゲナーゼに対する弱い阻害作用があり、プロスタグランジン合成を阻害する。また、動物実験でも動脈管閉鎖との関連が示されている。
日本のアセトアミノフェンの添付文書にも、「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項に、「妊娠後期の婦人への投与により胎児に動脈管収縮を起こすことがある」と記載されている。
実地診療では
妊娠後期にアセトアミノフェンを使用すると、動脈管早期閉鎖あるいは狭窄の原因となりうる。特に1500mg/日以上でリスクが大きい。妊婦に痛みがあり、非薬物療法では十分に緩和できない場合、 アセトアミノフェンは鎮痛剤の第一選択ではあるが、新しいデータに基づくと、 アセトアミノフェン使用の影響を軽視せず、許容できる程度の緩和作用が得られる最低限の用量を見極めて使用すべきである。


LEAVE A REPLY