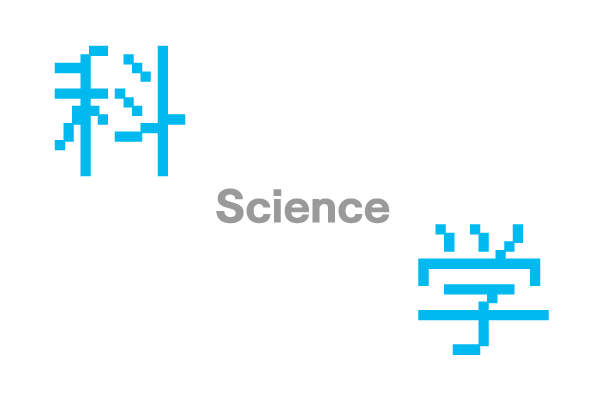
応用面で日本が期待されるゲノム編集技術
2020年のノーベル賞では、残念ながら日本人が3年連続して受賞する事は叶わなかった。生理学・医学賞に加えて、化学賞も医療への応用に対する期待が大きい分野となった。
化学賞では、ゲノム編集技術、「CRISPR-Cas9」を開発したジェニファー・ダウドナ氏(米カリフォルニア大学)、エマニュエル・シャルパンティエ氏(独マックス・プランク感染生物学研究所)の女性科学者2人が選ばれた。
20世紀の終わりに登場したゲノム編集技術は、狙った遺伝子を的確に切り出して繋げるものだ。「CRISPR-Cas9」は、遺伝子を切るハサミの機能を持つ酵素「Cas9」と、遺伝子の狙った場所に運ぶ分子「ガイドRNA」を組み合わせた。これにより、DNAの塩基配列の中から1つだけピンポイントに照準を定め、狙った遺伝子の破壊(ノックアウト)、あるいは挿入(ノックイン)する操作がより容易になった。
1970年代から用いられている遺伝子組み換え技術と比べると、精度の高さに加え、応用範囲が広い事も大きな特長だ。医療分野では疾患を再現する細胞やモデル動物を作製しやすくなり、今や遺伝子治療や創薬等の研究開発になくてはならない技術となっている。
化学賞では開発をアシストした日本人も
「CRISPR-Cas9」には、開発をアシストした日本人もいる。萌芽となった論文は1987年、大阪大微生物病研究所にいた石野良純氏(現・九州大教授)と中田篤男氏(現・名誉教授)らがまとめたものだ。
大腸菌の内部で特定の酵素をつくる遺伝子を探索中、大腸菌遺伝子に特殊な「繰り返し配列」を発見したが、意味は分からないまま報告。これが後の「CRISPR」だった。スウェーデン王立科学アカデミーでは日本発のこの論文をゲノム編集技術に貢献した業績の1つとして引用している。
ゲノム編集技術の研究では日本は大きく出遅れているが、応用面では期待がかかる。東京大学教授の濡木理氏らは立体構造の解析技術により“切らないゲノム編集技”を開発。「Cas9」から遺伝子切断活性を除き、代わりに遺伝子のオン・オフをピンポイントで調節出来るタンパク質(Guide Nucleotide-Directed Modulation:GNDM、通称ガンダム分子)を連結させた。小型化された酵素はアデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターに載せて運ぶ。
これにより目的の遺伝子と異なる遺伝子を切ってしまうリスクを排除出来る。AAVは細胞内に入り込める安全性の高いウイルスで、ガイドRNAとセットで細胞内部の目的場所まで酵素を送り届ける事が出来る。
この独自のゲノム編集技術を核に実用化を窺うのは、8月に東証マザーズに上場したバイオベンチャー、モダリスだ。同社は治療対象として希少疾患に照準を定める。希少疾患は日本では対象患者数が5万人未満の疾患を指し、単一の遺伝子異常が発症と直結する単因子疾患が多く、遺伝子治療が有用と考えられている。それぞれの疾患の患者数が少ないため、薬剤開発に時間と費用がかさみ、製薬大手は手を着けにくい。7000ほどの遺伝子疾患のうち約半数は単因子疾患とされ、モダリスは20ほどを対象に創薬を試みる。
一方、医学・生理学賞は、C型肝炎ウイルスを発見した米国の国立衛生研究所のハーベイ・オルター氏、米ロックフェラー大学のチャールズ・ライス氏、カナダのアルバータ大学のマイケル・ホートン氏の3人に贈られる事になった。
世界保健機関(WHO)によれば、世界全体では今も7000万人以上がC型肝炎に感染しているとされる。対策が進んだ先進国では新規発生者は抑えられてはいるものの、日本でもなお150万〜200万人の感染者がいる。
C型肝炎は、長い経過を経て肝硬変や肝がんへと移行して命を脅かす恐れがあるが、今回の発見により、そうした疾患が根絶出来る可能性が期待されている。受賞者らは初期のウイルス発見から治療薬にまで繋げており、その意義は大きい。
歴史的な経緯を追ってみたい。1960年代、米国では輸血を受けて回復した患者の約3割もが肝炎を発症する事が大問題になっていた。この原因を解明する中で、まず見つかってきたのが、やはり体液を介して感染するB型肝炎ウイルスの存在だ。因果関係が明らかになった事で供血された血液がB型肝炎ウイルスに汚染されていないかをチェックする体制が整えられた。B型肝炎の原因となるウイルスの発見と、後にその診断法とワクチンを開発した米国の2人の科学者には、1976年に生理学・医学賞が送られている。
B型肝炎ウイルスへの対策が進んだ事で、輸血患者が肝炎を発症する割合は激減したものの、輸血を介した肝炎発症を完全になくす事は出来ずにいた。
更なる原因の究明に挑んだオルター氏は、罹患者の血液を徹底的に調べたが、既に知られている経口感染するA型肝炎とB型肝炎のウイルスは見つからなかった。そして1975年、A型でもB型でもないNANBH(non-A non-B hepatitis)の存在を明らかにしたのである。
NANBH患者の血液を実験動物(チンパンジー)に注射してみたところ、肝炎を発症した。NANBHは軽症であるものの、長期的に経過を追うと約20%が肝硬変へと移行する。そこで、原因ウイルスの正体の究明に本腰を入れて取り組んだが、ウイルスの増殖を試みても失敗続きだった。
C型肝炎ワクチン開発の道開いた日本人
一方、ホートン氏は1980年代、原因ウイルスのDNA断片を「ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)法」により増幅させる事を試みた。余談だが、新型コロナウイルスの診断技術として頻用されているPCRは、この当時登場した最新技術である。さて、増幅させた遺伝子をバクテリアに組み込んでタンパク質を生成させたホートン氏らは、目指すウイルスの抗体を含むNANBH患者の血清を用いて原因ウイルスのタンパク質だけを釣り上げる事に成功した。こうして1989年、C型ウイルスタンパク質の同定に至るのだ。
その直後、ライス氏らが、C型肝炎ウイルスが肝炎を発症させる事を証明し、遺伝子技術を駆使してウイルスの働きを実証した。
さて、C型肝炎ワクチン開発の道を開いたのは日本人、国立感染症研究所所長の脇田隆字氏だ。世界で初めてC型肝炎ウイルスの感染性ウイルス粒子を培養細胞で作製する事に成功した脇田氏は、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの座長であり、当初あった専門家会議では議長を務めた。
ノーベル賞の授賞対象となる「人類のために最大の貢献をした人々」という趣旨に鑑み、感染症に関する成果はたびたび受賞対象になっている。世界が新型コロナと闘っているさなかに、ウイルス関連の疾患に対する成果に光が当たった事に勇気付けられる。来年は、世界が落ち着きを取り戻した中で、日本人の受賞を心から期待したい。



LEAVE A REPLY