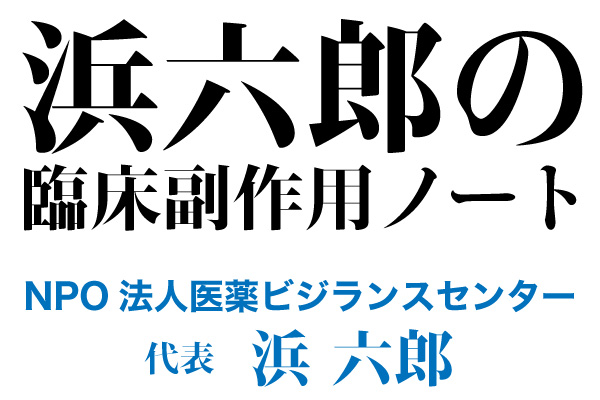
ジアゼパム坐剤(商品名ダイアップ)の添付文書には、熱性けいれんには「37.5℃の発熱を目安に、すみやかに直腸内に挿入する」とある。これは1996年に発行された熱性けいれん懇話会の「熱性けいれんの指導ガイドライン」(旧GL)の趣旨と一致している。
筆者らは2007年、「予防目的の抗けいれん剤の使用は不要」と述べたが1)、米国小児科学会は2011年にガイドラインを改訂し、それを受けて日本小児神経学会も2015年、ガイドラインを改訂(新GL)し、ジアゼパム坐剤の予防使用を「基本的に不要」とした。薬のチェック90号2)では新GLを批判的に吟味し、「進展があったが薬剤性けいれんへの警戒がなお不十分」と結論した。その概略を紹介する。
予防の有無はてんかんへの移行率に影響しない
筆者らが2007年に「不要」と述べた主な根拠は、Knudsenらの長期予後研究3,4)の結果による。
①熱性けいれんは基本的に予後良好である。
②複雑型を含む熱性けいれんで入院した小児を対象に、発熱時にけいれん予防のためにジアゼパムを短期間使用すると、予防には使用せずけいれん時のみに使用した場合よりも、短期的には熱性けいれんの再発を減少させたが、長期予後(2年後および14歳時のてんかん発症)には差がなかった。
その後の研究はいずれも、熱性けいれんを繰り返す人は、そうでない人に比べててんかんのリスクが高いことを述べたに過ぎず、予防によりてんかんへの移行を防止できることを示したものではない。Knudsenらの結果を覆す根拠とはならない。
新GLはなお薬剤性けいれんへの警戒が甘い
薬剤性けいれんへの警告が皆無であった旧GLと比べ、新GLでテオフィリンや鎮静性抗ヒスタミン剤によるけいれんに対して警告していることは評価できる。しかし、熱性けいれんの既往のある子への注意に限られており不十分だ。熱性けいれんの既往の有無にかかわらず、発熱時に抗ヒスタミン剤やテオフィリンを使用すべきでない、とすべきである。
非鎮静性も発熱時には脳中に移行
また、非鎮静性の抗ヒスタミン剤は、p-糖タンパクの基質であり、発熱時(高サイトカイン時)には脳中に移行しけいれんを誘発し得る。したがって安全とはいえないが、その認識が新GLには全くない。
ベンゾジアゼピン剤は感染症を増やす免疫抑制剤
ジアゼパム予防使用による短期の害として、失調や錯乱など精神神経症状の害が4割に達する。これも2007年1)に警告済みだが、ベンゾジアゼピン剤は末梢型受容体を介して免疫を抑制し、感染症を増加させる。実際、けいれん予防に用いたプラセボ対照試験で発熱頻度が26%、有意に増加した(p<0.001)。
結論
熱性けいれんには、薬剤性のけいれんが少なくないため、抗ヒスタミン剤やテオフィリン、解熱剤などけいれん誘発剤が使われていないか、まず点検が重要である。ジアゼパムの予防使用はすべきでない。
参考文献
1) 浜六郎ら、TIP誌2007: 21(12): 1-6.
2) 薬のチェック、2020:20(No90):83-87.
3) Knudsen FU. J Pediatr. 1985 106:487-90.
4) Knudsen FU et al. Arch Dis Child. 1996;74:13-8.
訂正とお詫び:7月号のアビガンの記事のヒト曝露量に誤りがありました。お詫びし訂正します。なお、結論は変わりません。 ヒト曝露量1477→739(μg・h/mL)。動物曝露量との倍率は以下の通り。COVID-19に用いる臨床用量でのヒト曝露量は、動物の無毒性量の2〜5倍、毒性量の約半分(マウス、ラット)ないし、ほぼ同量(イヌ)であり、人によっては致死量に相当する危険な用量である。
https://www.npojip.org/chk_tip/No90-f0.html参照


LEAVE A REPLY