
医師の意見より容疑者の供述を重くみた警察・検察
入院患者の人工呼吸器のチューブを外したとして、殺人罪に問われた元看護助手の女性(40歳)が今年3月、再審(やり直しの裁判)で無罪となった。患者の死亡から17年の月日が流れ、その間に殺人容疑で有罪判決を受けた女性は懲役12年の刑に服した。無実の医療者を殺人という最も重い罪で服役させた一連の経過からは、医療の専門家を軽視し、供述に偏重する日本の司法の↘問題点が覗く。医療者の見立てが正しく捜査に生かされるよう、声を上げる必要がある。
事件の現場となったのは、滋賀県東近江市の「湖東記念病院」。2003年5月22日未明、この病院に入院していた男性患者(当時72歳)が死亡しているのを当直中の看護師が発見した。滋賀県警は、患者が死亡したのは人工呼吸器が外れた事を知らせるアラームが鳴っていたのに看護師らが適切に処置しなかったためとみて、業務上過失致死容疑で捜査。関係者を事情聴取したが、「アラーム音が鳴った」という供述が得られず、捜査は難航した。
突破口となったのは、死亡した患者を発見した看護師と一緒に当直勤務をしていた看護助手の女性の供述だ。事件から約1年が経過した04年5月、この女性が県警の任意の取り調べに「アラーム音が鳴っていたのを聞いた」と供述したのだ。
これ以降、断続的に進められた任意の取り調べで女性は「患者の人工呼吸器からチューブを引き抜き、酸素の供給を止めて患者を殺した」事を認め、警察は同年7月、女性を殺人容疑で逮捕した。女性が病院の待遇に不満を持っていた事が殺人の動機とみられた。
ところが、女性は逮捕された当時から接見に来た弁護士や家族に無↖実を訴えていた。裁判でも起訴事実を否認したが、一審の大津地方裁判所は05年11月、女性の自白は具体性や迫真性に富んでいる」として女性に殺人罪で懲役12年の判決を言い渡す。裁判は最高裁判所まで争われたが、07年に最高裁が上告を棄却し、判決が確定。女性は懲役刑に服する事になった。
服役中も大津地裁に裁判のやり直しを求めたが2度にわたって棄却され、17年8月に刑期を終え出所。その年の12月になってようやく、大阪高等裁判所は再審を決定したのだ。
警察が〝証拠隠し〟をした可能性
全国紙の司法担当記者は「再審を決定するという事は、事実上、最初の裁判の事実関係に〝誤り〟があったのを認めるという事だ」と解説する。今回のケースでは「再審を求める弁護側が医師の意見書を提出し、大阪高裁は確定判決が有罪の根拠とした鑑定に疑いが生じた、つまり患者が自然死であった疑いがあると指摘し、再審を決めた」(同記者)という。検察側はこの決定を不服として最高裁まで争ったが、19年3月に最高裁はこれを棄却し、再審が行われる事が正式に決まった。
「日本の刑事裁判の世界では、再審が開かれる事がとてもハードルが高い」(同)といい、再審開始が認められた事により、女性を有罪とした最初の裁判の判決が覆るのは間違いなくなった。実際に今年2月に始まった大津地裁の再審公判は翌月に「無罪」が言い渡されるスピード決着となったのだ。殺人罪が再審で無罪となるのは極めて珍しい。
無罪の人間が有罪となってしまったのはなぜか。刑事裁判に詳しい弁護士は「この裁判の問題点は医師の意見より容疑者の供述を重くみた警察、検察側にある」と指摘する。再審請求の過程では、患者を解剖した医師が警察の調べに「たんの詰まりにより酸素供給低下状態で心臓停止した事も十分に考えられる」と自然死の可能性を指摘していた事が明らかになった。ところが、警察が検察に渡した同じ医師の鑑定書は自然死の可能性に触れておらず、警察が〝証拠隠し〟をした可能性が高い。
再審を求める弁護側は「患者の死因は不整脈や、たんを詰まらせた事等による自然死だったと考えられる」とする別の医師の意見書を新たに提出。再審判決で裁判所は「男性患者は致死性不整脈、その他の原因で死亡した可能性がある。何者かに殺害されたという事件性は証明されていない」と弁護側の主張を認め女性に無罪を言い渡したが、当初の捜査の段階から自然死の可能性は医療者によって指摘されていたのだ。
捜査当局だけではなく、高い有罪率を支える裁判所にも問題はある。今回のケースでは、女性の供述は任意の取り調べ時から逮捕後に至るまでたびたび変わっていたのに、一審はその供述を「信用性が高い」と認めた。
女性には軽度の知的障害や発達障害があり、取り調べの方法や供述の信用性をよく吟味する必要があった。女性は新しく取り調べの担当になった若い男性刑事から自白を迫られ、恐怖から逃れようと「アラーム音が鳴っていた」と認めたという。すると、刑事の態度が優しくなった。身の上話にも耳を傾けてくれる刑事に恋心を抱いた女性は、相手が喜ぶように「私が殺した」と供述し、殺人容疑で逮捕されたのである。
長く警察を取材してきた全国紙記者は「障害を持つ容疑者が取り調べで相手に迎合するような供述をしてしまう事は別の事件でも起きている」と語る。その上で、「業務上過失致死ではなく殺人で犯人を挙げれば当然、取り調べの刑事の手柄になる。より重い罪で立件しようと刑事は躍起になったのだろう」と刑事に気に入られようとした女性がやってもいない「殺人」を供述した事に理解を示す。
医療者が科学的証拠を示す事が重要
別の全国紙の医療担当記者は「時代背景もある」との見方を示す。「事件が起きた03年といえば、1999年の都立広尾病院の誤投薬事件、横浜市立大学病院の患者取り違え事件後で医療不信が高まっていた時期。刑事、民事で多くの医療裁判が行われ、全国の警察が医療事故を挙げようとしていた」。
04年に発生、06年に医師が逮捕(後に無罪判決)された福島県立大野病院事件により医療崩壊がピークとなり、刑事事件化の動きは下火になっていったが、湖東記念病院の事件はまさに時代の波に乗ってしまった面も否めない。
医療裁判に詳しい弁護士は「医療現場を舞台にした刑事事件では、医療者が団結して科学的な証拠を示す事が重要だ」と話す。同じ医療行為をしても違う結果になる事のある医療の世界では、検察側の証人の医師と弁護側の証人の医師が異なる見立てを示す事はよくある。死亡した患者の「死因」が特定出来ない事も起こり得る。
この弁護士によると、裁判所は専門学会等の権威ある団体からの意見を重視する傾向にあると言い、「不当な医療事故裁判にはアカデミアの意見を積極的に届ける事が大事になる」と言う。
「有罪」か「無罪」かのどちらかしかない刑事裁判の世界。取り返しのつかない冤罪事件を生まないためにも、医療者が積極的に声を上げる事が大切だ。


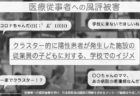

LEAVE A REPLY