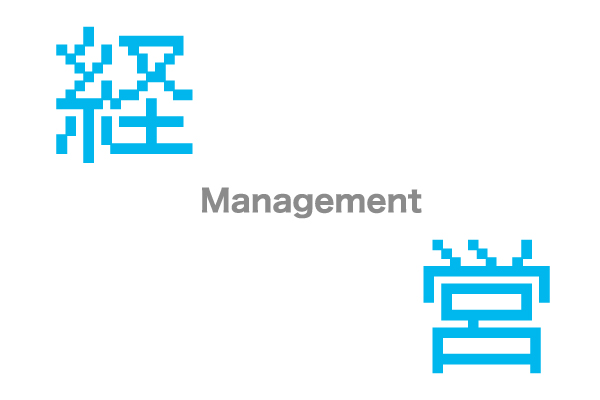
勤務実態の把握や36協定締結、 宿日直許可申請は必須
医師の働き方が大きく変わろうとしているが、課題は多い。そうした中、一般社団法人医療法務研究協会(理事長=小田原良治・日本医療法人協会常務理事)は7月、「『医師の働き方改革』の在り方を問う」をテーマにしたセミナーを都内で開いた。
冒頭の挨拶で、平田二朗・同会副理事長は「医師の働き方と一般の働き方に乖離があり、一般国民の働き方に近づけることがテーマとなっている。議論を進める中で我々なりの結論を出したい」と述べた。
インターバルの義務化には法改正が必要
まず行政の立場から、元厚生労働事務次官の二川一男氏が登壇、医師の働き方改革の全体像について説明した。二川氏は、医師の働き方に関する議論が始まった時期である2015年から17年までの間、厚生労働事務次官を務めた。
二川氏は、「働き方改革の議論が始まったきっかけは、安倍内閣が2015年にアベノミクスの新3本の矢を打ち出したことだった」と振り返った。
新3本の矢では①希望を生み出す強い経済(戦後最大の名目GDP〈国内総生産〉600兆円)②夢を紡ぐ子育て支援(希望出生率1.8)③安心につながる社会保障(介護離職ゼロ)が打ち出された。安倍内閣が16年に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」で、出生率や介護離職の問題を解決するため働き方改革が必要とされた経緯を説明した。
女性と高齢者の労働力化の制約要因を取り除くことが必要とされ、女性では結婚と子育てによる就業率の低下、高齢者では60代後半の労働に関する制度が整備されていない状況の是正が必要だったという。
高齢者については65〜69歳で「収入を伴う仕事をしたい」と回答した人が65.4%だったのに対し、就業率は男性52.9%、女性33.4%と男女でギャップがあった。二川氏は国際比較を引きつつ、年間労働時間が短いほど1人当たりGDPが上昇する傾向が見られると説明し、日本の働き過ぎは問題だったと指摘した。
政府はまず大企業に対し、今年4月から時間外労働の上限を労働基準法で厳格化した。従来は36協定によって、労使合意があれば1日8時間の法定労働時間を超えた仕事をさせることができたが、労基法改正で時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間と定められた。例外として月100時間未満、年720時間が認められた。中小企業は2020年4月から適応される。
適応猶予・除外業種である医師の働き方については、厚労省の「医師の働き方改革に関する検討会」が今年3月、応召義務などの特殊性を踏まえた報告書をまとめた。時間外労働の上限を2024年4月から適用し、一般の医師は年間960時間にした(A水準)。地域医療の維持に不可欠な病院医師(B水準)と技術の向上が必要な研修医ら(C水準)については、年間1860時間を上限とする2035年度までの特例措置とした。
また、「連続勤務28時間以内」「勤務間インターバル9時間以上」を義務化するなど、努力義務とされる一般職とは異なる内容となっている。二川氏は「インターバルや連続勤務時間制限は労基法のどこにも書いていない。義務化するには来年から再来年に医療法か医師法の改正が必要」と説明した。
二川氏は、時間外労働が上限に達しても、医師には応召義務がある他、宿日直や自己研鑽の問題もある。猶予期間の間に、さらなるルール作りが求められると述べた。
宿日直許可基準の見直しが重要
次いで病院経営者の立場から、社会医療法人ペガサス馬場記念病院(大阪府堺市)理事長・院長で日本医療法人協会副会長の馬場武彦氏が登壇した。馬場氏は「医師の働き方改革に関する検討会」の構成員も務めた。まず、「地域医療の継続の視点から説明したい」と現行制度の課題や見直しの方向性を示した。
馬場氏は「病院経営者は、医師法や医療法については詳しいものの、労働法制については通じていなかった」とこれまでの実態について言及。労働法制と医師法や医療法は戦後まもない昭和20年代に成立し、互いに摺り合わせられないまま現代に至っているとして、今後、整合性を取る必要があると述べた。
また、勤務医を労働者としてとらえるよう、病院経営者に認識の転換を促した。医療機関では法人の開設者のみが経営者で、その他の勤務医は労働者と位置付けられる。従来、医師は労働法制のルールに沿わないため、長時間労働が常態化していたのは周知の通り。今後、ルールに則って勤務していくための態勢作りが必要との考えを示した。
特に注目しているのが宿直の取り扱いだという。医療の現場では夜間の勤務を「当直」と捉えるが、法的には「宿直」であり労働基準監督署長の許可を受ける必要がある。
そもそも宿日直は、一般的に外来診療を行っていない時間帯に入院患者の急変に備えて待機するもの。従って、実態としては当直として通常の診療を行っているケースは多いが、本来は通常の診療を行うことはできない。
そのために受けるべき許可基準も、「特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時間の業務」に限るなどとされ、労働基準局の通知を参考にすれば、1時間程度しか働いていないはずのものだ。許可を受けることで、寝ているような時間と見なされて労働時間規制の適応から除外されるのだが、実際にはそうなっていない問題がある。
馬場氏は、夜間当直と呼ばれる勤務実態を考えると、慢性期病床はほぼ診療がないので宿直と考えられるが、2次救急や3次救急などでは診療が一定の頻度で行われていたり、日中と同程度に診療が発生したりしていると説明。結果として、従来の基準からは逸脱していると見る。3次救急ならば宿日直とせずに時間外労働を適用できるとしても、2次救急のように断続的に診療が発生している場合、宿日直許可基準から見れば限りなく黒に近いグレーとなる。
馬場氏は「元々、宿日直許可基準は看護師を含めた勤務を前提に考えられており、医師の勤務の現状と実態が合ってはいなかったので、見直しが必要だった」との考えを示した。そして、2次救急などを担う一般病院は宿日直許可を取って、時間外労働の上限が年960時間のA水準を目指すべきではないかと述べた。
馬場氏は2次救急の医療機関の夜間当直について、宿日直扱いで大体対応できるとの見方を示した。
厚労省が7月に出した宿日直に関する通知に盛り込まれた「十分な睡眠」に関しては、「医師の働き方改革に関する検討会」の研究成果を踏まえ、「6時間ぐらいと考えている」と述べた。
また、厚労省通知に基づき、「患者に直接、接する行為は労働」で、それ以外の行為は①「上司等から、明示的、あるいは黙示的な指示がない」、②「①を医師本人および上司等が認めており、それが書類として残っている」という要件を満たす場合、自己研鑽とされ、労働時間から外れると説明した。
四病院団体協議会のアンケートによると、特別条項ありの36協定を締結している病院は半数。特別条項なしの36協定を結んでいるところが約35%。約15%が36協定を結んでいない状況となっていた。さらに、宿日直許可申請を行わずに宿日直として取り扱っているところも約20%に上った。勤務実態を把握している施設も3分の1にとどまっていた。
馬場氏は医師の働き方改革に関する検討会での提言を紹介し、特に重要な施策としてタイムカードやICカードなどで医師の労働実態の客観的な把握をすることと、36協定などを含めた時間外労働の実態把握が大事だと強調した。
最後に、医療法務研究協会の顧問弁護士を務める井上清成氏が法的観点から医師の働き方の論点を示した。
井上氏は、医師の働き方改革について「人権問題である」と指摘した。従来、医療界が一般の法律とは隔絶された世界であるかのように、労働法のルールに沿わない勤務実態が野放しにされたと説明。今後は、労働法制に従う必要性は強まると予測した。
過労死裁判は病院側が負ける流れに
井上氏は、勤務医が過労死した場合、医療機関は損害賠償責任を負うことになるのではないかと問い掛け、地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンターの医師過労死裁判を例に挙げた。
長崎地裁は今年5月、損害賠償や未払いの時間外手当として1億6700万円の支払いを命じ、裁判長は「病院が医師の残業時間を把握せず、負担軽減策も取らなかったのは違法」とした。これに対し、井上氏は「労務管理をするのが当たり前で、やらないのはそれ自体失格」と述べた。
また、これまでの過労死裁判では遺族側が労働時間を把握するのが難しかったが、働き方改革が進めば病院側の責任も立証しやすくなるとの見通しも示した。そうした点から、特別条項ありの36協定を結ばない、宿日直許可を取っていない、医師の労働実態のデータを取っていないという状況は危ういという見方を示した。
講演後のシンポジウムでは、参加者から大学病院からの派遣医に関する質問が挙がった。時間外労働などの管理について、二川氏は「大学病院が兼業・副業先も含めて時間を管理しなければいけない」と述べた。
また、一般病院の夜間・休日勤務が宿日直扱いなら大学病院側は労働時間に含めずに済み、インターバルを設ける必要がないことから、馬場氏は「大学病院側は宿日直許可を取らない病院への医師派遣を敬遠するのでは」との考えを示した。



LEAVE A REPLY