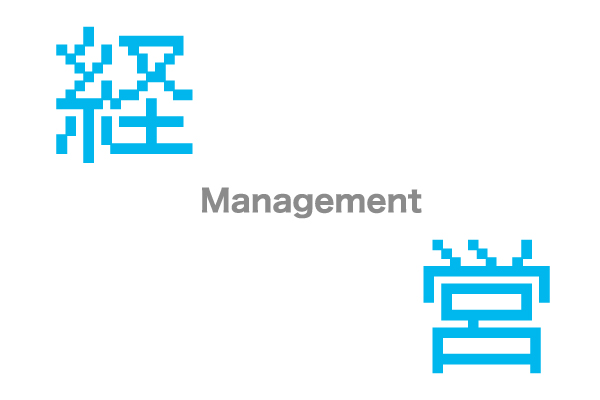
期間限定の加算で駆け込み転換ブームの予測
病院、病床の削減の施策が明確に打ち出される中で、2030年には死亡者160万人のうち47万人が、いわゆる“看取り難民”になると警鐘が鳴らされている。こうした“死に場所”の定まらない問題の救済策として、介護保険法改正により、2018年に「介護医療院」という新たな施設が創設されている。
介護医療院は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者も受け皿となることを目的として創設されており、住まいの機能を持った長期療養施設として、場合によっては看取りまで行う。施設基準により、機能強化型介護療養病床に相当する「I型」と、介護療養型老人保健施設(転換型老健施設)相当以上の「II型」の2通りに類型化される。人員配置は、Ⅰ型が入所者48人に医師1人で、24時間の医学的管理や看取りに備えて当直医が必要となっている。これに対してⅡ型は、入所者100人に医師1人で、容態が比較的安定している入所者の日常的医学管理とオンコール看取りで対応する。
基本報酬を見ると、I型介護医療院のサービス費は、同等の機能を持つ介護療養病床より1日25単位引き上げられた。ただし、生活施設としての質の向上を図るため、1人当たりの床面積は、従来の6.4㎡以上から、原則として老健施設並の8.0㎡以上としなくてはらならず、基準に満たない場合には1日25単位の減算対象になる。
介護保険料増額で転換に消極的自治体も
介護医療院は、病院ではないことから、介護施設と表現されてはいるものの、実態としては、病床(病棟)と理解するのがふさわしいようだ。
廃止が決まっている介護療養型医療施設(2024年3月末まで移行期間)、医療療養病床、転換型老健施設から、介護医療院への転換が可能である。新設ないし、一般病床を廃止して介護医療院にしたいという場合は、都道府県・政令市・中核市ごとに定められている介護保険事業計画における介護医療院の必要入所定員総数(整備量)の範囲内であるかを確認しなくてはならない。自治体は各地域のニーズに基づいて整備量を定め上限を設けていることから、開設の可否を問い合わせる必要がある。
2019年3月末時点において、150施設に介護院が設置されており、入居定員数は1万床を超え、合計1万28床となった。2018年6月末時点では、21施設、1400床で、施設・病床数とも7倍強に増加している。類型による内訳は、Ⅰ型が92施設(6858床)、Ⅱ型が55施設(3170床)。I型とII型は同一フロア内で混在させることはできないが、両方とも設置している施設も3施設ある。
転換元の内訳では、介護療養病床から91施設、介護療養型老健から31施設が転換。また、医療療養からの転換は41施設(2665床)である。医療療養から介護医療院への転換は、介護保険制度における地域の総量規制の枠外ではあるが、医療療養(医療保険適用)から介護医療院(介護保険適用)となった場合、介護費が増大するため、小規模な自治体は、介護保険料を大幅に増額せざるを得なくなることを敬遠し、転換に消極的であるとされる。
有床診療所からの転換も、4施設(34床)ある。大型施設の事例もあり、例えば、医療法人新生十全会では、2002年になごみの里病院(京都市)開設以来運営していた介護療養型医療施設(466床)を、全てⅠ型の介護医療院に転換した。また、医療法人社団一心会初富保健病院(千葉県鎌ケ谷市)でも、Ⅰ型の介護医療院(320床)を開設している。施設数が最も多いのは北海道で、病床数では福岡が最多である。
病院の中の介護施設であり、療養病床との最も大きな違いは、診療報酬上の「自宅等」に含まれることだ。一方、医療病床と異なるのは、医療保険から介護保険へと変わるため、要介護認定が必要になってくることなどがある。
介護医療院の入居者は長期入居が想定されているが、利用者の状況に合わせてリハビリテーションを提供するなどして、在宅復帰を目指すことも可能だ。患者には、今までと同じ病棟にいながら、そのまま介護医療院になることも、利点となるだろう
初富保健病院の例では、個室の他、4人室があり、4人室には家具調の仕切りが設置されており、プライバシーへの配慮がなされている。介護医療院は療養病床とは異なり、生活の場であることを重視し、入居者の尊厳を保障しなくてはならない。生活施設として楽しみのある生活や、家庭的で温かい空間が求められる。
抑制を行うことはせず、人生の最終段階における医療やケアについてあらかじめ話し合ってACP(アドバンス・ケア・プランニング)を立てておくなどすべきである。これらについて、職員の意識改革も必要なことから、日本介護医療院協会(会長=鈴木龍太・鶴巻温泉病院理事長)では研修を計画中だという。
病床削減という国策の中で、自宅に近い充実した生活環境の中で看取りまでできる施設として、活用を期待する声は大きいものの、介護医療院への転換には二の足を踏むという声もある。背景には、病院でなくなる不安、看護師・介護士確保の困難さ、移行手続きの煩雑さなどが指摘されている。
それでも、介護報酬改定による移行のための支援策は大きい。例えば、移行定着支援加算は、全入所者に対して1日93単位を算定できる。もし、50床を転換し満床となれば、これだけで年間約1700万円の増収になり、療養室の改装などに充てることもできる。
この加算は、転換の届け出日から1年間限定で、2021年度末までしか算定できない。1年分を算定するには、2020年4月1日までの転換が必要なこともあり、この半年余りで、駆け込みの転換ブームが予測されている。
在宅復帰としてカウントできるメリット
また、急性期病床などほぼ全ての病床からの退院例が、在宅復帰としてカウントできることもメリットが大きい。在宅復帰率を算出する際、従来の介護療養病床や医療療養病床への転院とは異なり、介護医療院への転院は在宅復帰の実績になる。今後、転院先の候補として、地域の介護医療院の位置付けは高まっていくはずだ。
医療・介護トータルで見れば、医療療養病床から介護医療院への転換は「費用の適正化」に繋がる。病棟機能を時代に合わせて変化させれば、患者はもちろんのこと、職員の満足度が上がり、地域への貢献度も増すはずだ。




LEAVE A REPLY