がん免疫薬で命に値段が付く日がやってくる?
2018年のノーベル医学生理学賞が、免疫を抑制するタンパク質の発見で新たながん治療の道を切り開いた京都大学特別教授、氏(76歳)に決まった。この発見ががん免疫治療薬「オプジーボ」の開発に繋がったことは有名な話で、今や世界の製薬企業はがん免疫薬の開発にしのぎを削る。ノーベル賞有力候補だった本庶氏の満を持しての受賞はめでたいが、一方でそれはオプジーボのような高額薬が次々と誕生する未来が来ていることの裏返しでもある。本庶氏の受賞は、日本の皆保険制度崩壊に繋がる「悪夢のシナリオ」の序章なのか。
10月1日夜、ノーベル賞の先陣を切って発表された医学生理学賞は、米テキサス大学のジェームズ・アリソン教授(70歳)と本庶氏に決まった。「日本人の医学生理学賞の受賞は2年ぶり。本庶氏は毎年、有力候補として名前が挙がっていた大本命だから、報道各社は事前に取材を済ませて発表に備えていた」(全国紙科学部記者)。受賞理由は「免疫抑制の阻害によるがん治療法の発見」で、日本が伝統的に強い「お家芸」の免疫学分野での受賞となった。
各社が予想の範囲内だったという本庶氏の功績は一体どういうものか。
人間の体には風邪のウイルスやがん細胞などの異物を攻撃する「免疫細胞」が備わっている。健康な人間の体内では生まれたがん細胞は免疫によって排除され、がん細胞が増えていくには免疫細胞の監視や攻撃をかいくぐる必要がある。ということは、免疫力を高めれば、がん細胞を攻撃できるのではないか。これががんの「免疫療法」の考え方だ。
謎の分子と腰を据えて付き合ってきた
ところが、この考えに基づく有効な治療法はなかなか現れなかった。長らくがんの免疫療法といえばインチキとまで言えないまでも不確実な効果の自由診療というイメージが強かったのも、メカニズムの分かりやすさとは裏腹に効果的な治療法が現れなかったことにある。この免疫療法を一転、実現可能な治療へ繋げたのが本庶氏と共同受賞者であるアリソン氏がそれぞれ発見した分子なのである。
本庶氏が見つけた「PD‒1」という分子は、免疫の司令塔となるリンパ球の一種「T細胞」の表面にあり、当初は細胞が自ら死を選ぶ現象「アポトーシス」に関連する分子だと考えられていた。PD‒1という名前は、予定(プログラム)された細胞死(デス)の頭文字という。
ところが、細胞死に繋がる現象はなかなか現れない。本庶氏はこの謎の分子と腰を据えて付き合い、PD‒1に免疫の機能を抑える働きがあることを突き止めた。がん細胞にはPD‒1と結び付くPD‒L1という分子があり、二つが結合すると、がん細胞への攻撃を控えるよう求める指令が出て、免疫にブレーキがかかるのだ。
免疫を活性化させても効果が現れにくかった過去の免疫療法の多くは、PD‒1をがん細胞に悪用されて免疫機能を抑えられていたためと考えられる。ブレーキを解除すれば免疫は活性化する。この新たなメカニズムを利用して、小野薬品工業が2014年9月に発売したのが、がん治療薬「オプジーボ」(一般名・ニボルマブ)というわけだ。PD‒1と同様の働きを持つ分子は他にもあり、共同受賞したアリソン氏が発見した「CTLA‒4」は同様のがん免疫治療薬「ヤーボイ」(一般名・イピリムマブ)として日の目を見ている。
日本人27人目(うち3人は外国籍、医学生理学賞は5人目)となる本庶氏の快挙を「ペニシリンの発明に匹敵する」と讃えたのは、12年にiPS細胞(人工多能性幹細胞)の発見により同賞を受けた同じ京都大の山中伸弥氏(56歳)だ。今や免疫療法は、外科治療、抗がん剤、放射線に次ぐがん治療の第4の選択肢となった。
「夢のがん治療薬」と誤解されかねない
ただ、本庶氏のノーベル賞受賞を喜んでばかりもいられない。「ノーベル賞効果」が誤ったメッセージとなることを危惧する声も聞かれるからだ。その一つが、図らずもiPS細胞がそうだったように、日本のがん研究が免疫療法一辺倒になってしまうことへの懸念だ。
ある若手研究者は「山中先生の受賞によって、日本はiPS細胞の研究に予算が付きやすくなるなど『iPSバブル』と呼ばれる状態に陥った。欧州ではES細胞(胚性幹細胞)の研究が主流なのに、倫理的な問題もあり、日本はiPS研究ばかり先行してしまった」と指摘する。
受賞後の記者会見で「教科書に書いてあることを信じないことが大切」と訴えた本庶氏だが、ダイヤの原石を磨き上げて輝かせるような地道な研究は、現在の日本では支援が得られにくい環境にある。ダイヤの原石を支援しなければ、「第5の道」「第6の道」に繋がる大発見は生まれない。
「オプジーボ」の優れた効果にばかりとらわれるのも危険だ。がんができる臓器ごとに異なる従来の抗がん剤と異なり、免疫のメカニズムに働き掛けるオプジーボはメラノーマ(悪性黒色腫)に始まり、肺がん、胃がん、腎臓がんと多様ながんに適応を拡大している。当初の年3500万円という高額な価格は薬価見直しにより約3分の1に下がったものの、続々と登場するがん免疫薬はいずれも高価になることが見込まれる。オプジーボは適応のあるがん患者の2割程度にしか効果がないとされ、効果の有無を事前に調べることはできない。ところが、ノーベル賞であたかも「夢のがん治療薬」と誤認されてしまい、患者が安易に使用を求めることも考えられる。
日本の皆保険制度の下では、患者はかかった費用の3割(原則)を負担するが、月額上限以上の医療費は高額療養費制度(医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その分が払い戻される制度)により負担しなくて良い。健康保険組合の多くは赤字なのに、次々に現れる高額薬が保険適用され使用する患者が増えれば、保険制度そのものが破綻しかねない。
「現行の薬価の決め方は不透明。改革が必要だ」(薬価制度に詳しい大学教授)との指摘は多いが、新薬開発の現場では研究から製造までのコストが高額化しており、安い薬価しか付かなければ製薬企業が日本での発売をやめる可能性もある。ようやく解消された「ドラッグラグ」(海外で使える薬が日本で使えない状態)が再び起きることも考えられる。
英国では、効果の割に高い薬剤に保険適用を認めないなどの策で薬価高騰に対抗する。日本でも議論は始まったが、1年間延命できる薬に公的医療保険からいくらまで支払っていいかを尋ねた厚生労働省のアンケートは、「命に値段を付けるのか」とけちを付けられ中止になった。
「オプジーボが効いた著名人といえば、米国のカーター元大統領や森喜朗元首相が有名だが、皆保険制度が崩れれば、こうした治療は一部の金持ちのものになってしまう」(全国紙記者)。高額薬剤問題から目を逸らして本庶氏の受賞に浮かれているだけでは、命に値段が付く最悪のシナリオを防ぐことはできない。


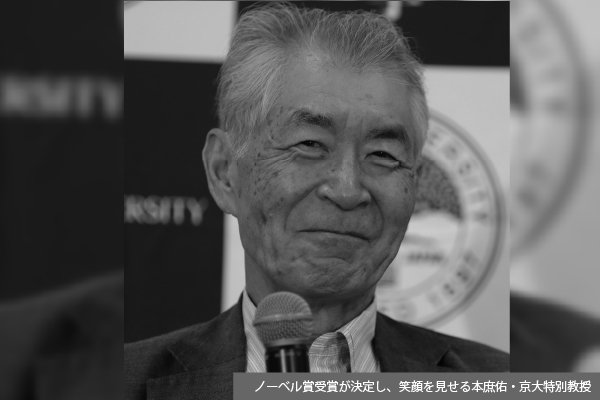
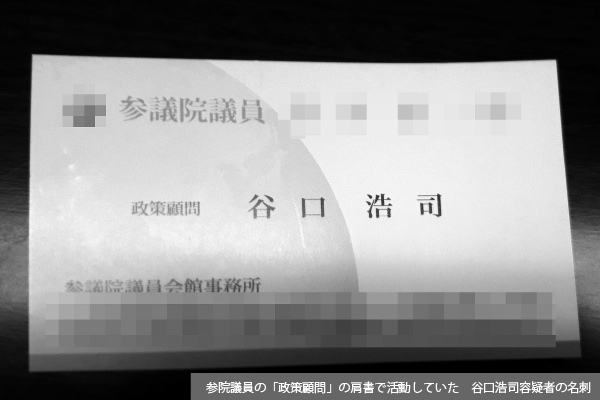

LEAVE A REPLY