
髙橋 修(たかはし・おさむ)1953年東京都生まれ。千葉大医学部卒業。同学部附属病院第一外科、住友重機健保組合浦賀病院外科医長、平和病院外科医長、同病院理事・副院長などを経て、2000年同病院理事長・院長(17年名誉院長)。16年横浜市立大学臨床教授。
医療法人平和会
平和病院(神奈川県横浜市)理事長
髙橋修/㊦
やはり、がんだった──。2004年5月、CT検査で肺に見つかった不気味な陰影の正体は、生検をしても分からず、手術中の迅速病理診断は機械の故障でかなわなかったが、その3日後、平和病院の理事長・院長だった髙橋修は、厳然たる事実を突き付けられたのだった。もっとも、執刀医が「取り切れた」と判断したので、仕事に復帰出来るだろう。となると、次には、体力が衰えるのではないかという不安が襲ってきた。
管理業務は多忙だったが、肝胆膵を専門とする現役の外科医でもあり、月に10件ほど、自ら麻酔をかけて執刀し、外来診療もこなしていた。療養のための休暇は2週間もらっていた。
そこで、退院して1週間過ぎた頃から、体力維持のためにウォーキングをすることにした。自宅からほど近い日産スタジアムには、全週1kmほどの周回コースがある。そこを妻と2人、「回復しなくてはいけない」という執念を込めて、ひたすら歩いた。健康になった今から振り返っても「きつい」というぐらいの苦行で、無理がたたって胸水が貯まるという落ちが付いた。
患者になったからこその得難い経験
外科医として当たり前のように患者を切っていたが、自分の傷の痛みは予想以上に強くて閉口した。オピオイド(麻薬性鎮痛薬)を服用すると、「消しゴムで『痛み』という字をこすったように痛みが消えた」。患者となったからこその得難い経験だ。勤務先でない病院で治療を受けたからこそ、苦痛を感じれば弱音を吐くことも出来た。
そして、復職の日がやって来た。
元々は医局人事で入職した病院ではあるが、病院経営に心血を注いでいた。平和病院は、東芝社長や経団連会長などを務めた故・土光敏夫が、戦後間もない1946年に自社の寮を転用し設立した伝統ある病院で、地域に根付いていた。反面、例えば、感染対策の徹底などが求められる現代にあっては、時流にそぐわない面も出てきていた。建物自体も老朽化していた。
2000年、髙橋は47歳と比較的若くしてトップに就任すると、地域であるべき病院の姿を模索し、まず病院機能評価機構の認証を受けることを計画した。看護部長と二人三脚で、病院の規約を作り直すところからのスタート。当時は病院のロゴマークもなかったが、イニシャルである「H」を図案化して人が人を支えるようなマークの素案も髙橋が作った。それ以外にも病院の基本方針を作成するなど、細かい仕事に追われた。
思い起こすと相当量の仕事量をこなし、プレッシャーやストレスはそれなりにあったが、それががん発症に影響を与えたとも思えない。退院後、05年3月に無事認証を受けることが出来た。
そして、がん闘病を大きなきっかけとして、髙橋は自分の診療スタイルを見直していた。父と同じ消化器外科の道を選んだのは、「自分で悪い所を切り取って治せる」という単純な理由だ。手術後は充実感があったが、長らく続けていると、手術では救えない患者がいるとの現実にも直面した。
平和病院は150床規模のケアミックス病院で小回りが利くことから、再発したがん患者も受け入れていた。手を尽くしても治療法がない場合には緩和ケアを提供し、最期を看取ることも少なくなかった。3人に1人ががんで亡くなる時代にあっては、それもまた病院に求められる機能だ。髙橋は、少しずつ軸足を緩和医療に移し始めていた。
退院後の大仕事の一つが、病院の新築移転だった。病院機能評価の受審以上にハードな仕事だったが、「病院新築時に院長でいられることは恵まれている」と、こちらも全力投球をした。
幸い、元の病院があった高台の下の土地を取得出来、11年6月に新病院に移転した。最大の目玉は、「緩和ケア科」の病床を新設したことだ。07年に近隣の済生会横浜市東部病院が開院したことで、平和病院の手術数は減少していたが、地域の基幹病院と診療を繋ぐ要の病院となることがより一層求められていた。
一口に「緩和ケア」と言っても様々で、担い手の思いが色濃く反映される。平和病院の緩和ケア病棟の売りは、「コンビニ緩和」と「バリアフリー緩和」だ。24時間365日、時には一般病棟も使って患者の受け入れ要請を断らない。そして、一般病棟との垣根をなくす。「緩和ケア病棟を限られた人の理想郷にしてはならない。目の前の患者にいつでも向き合えるように」と、終末期についてのスタッフ教育を含めて力を入れている。
紹介で来院する再発がんの患者は、罹患者数が多いこともあって、肺がん患者が半数以上を占めている。かつての自分と同じステージ1aでも、それが再発したという患者も少なからずいる。同じ病気になったことに親近感を寄せてくれる人もいれば、髙橋のがんを知らない患者もいる。
「たまたま私は治療がうまく行って、今まで生き続けているが、目の前の患者は、もしかしたらちょっと何かが違った時の自分かもしれない」
患者を診るたびに何が分かれ目なのだろうと、問い続ける。その答えは見つからないが、目の前の人達の最期を、少しでもつらいものでないようにしたいという強い思いが沸き上がってくる。
65歳を目前にして、今も週4回、計5コマの外来診療を担当するだけでなく、毎週土曜の晩は宿直を務めている。診療のない日曜日に、患者を見てから帰宅出来るのは好都合だと考えるからだ。
院内コンサートなどで人生応援歌を披露
歳と共に段々と運動に縁遠くなった分、サックスやギターに打ち込み、作詞や作曲も手掛ける。月1回は都内のスタジオでバンド活動を行う他、院内コンサートや講演会で披露、拍手喝采を浴びる。
「学生時代は失恋の歌ばかり作っていたが、最近は周りに小さな幸せがあるという人生応援歌が増えた」
横浜市鶴見区や川崎市の診療所の間から、患者を安心して任せられると評判が立ち、連携先が増えている。在宅部門の強化など、まだ課題も残っているが、16年に定年より少し前に院長職を次代に禅譲して舵取りを委ね、自らは理事長と緩和ケアに専念している。65歳となる節目、今年6月の理事会では理事長も辞し、がんでない患者も含めて地域の緩和ケア力を向上させるための支援センターを立ち上げることを計画している。
「『がんになってハッピー』ということはあり得ない。ただ痛い目にあって、気が付かなかったことに気付けたことは幸いだった」。13年前、まだ小学生で、父ががんと知って泣きじゃくった子供達。娘が臨床心理士の道へ進み、息子は医学部に通っているのは、髙橋の病気とも無縁でない。
4年前に心臓にカテーテルを入れ、長年の職業病のような腰痛を抱えている以外は健康体。年1回は全身のCTを撮っているが、がん再発の兆しはない。母は85歳まで勤務医として、職務を全うした。がんに打ち勝った人生は、なお他者のためにも永らえていくつもりだ。(敬称略)
【聞き手・構成/ジャーナリスト・塚崎朝子】


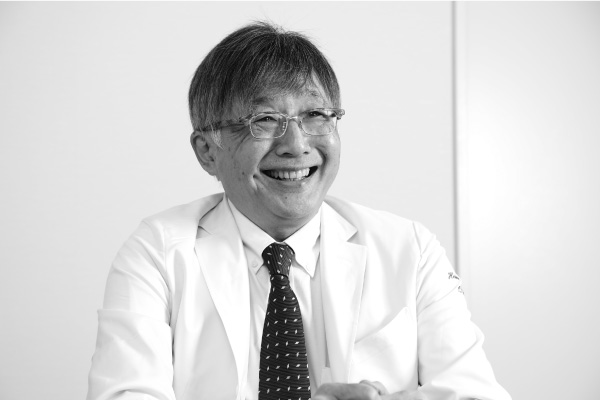
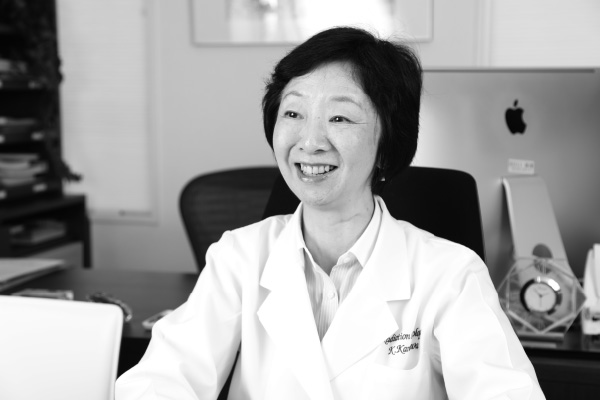
LEAVE A REPLY