
日本企業が抱える労働力損失の実情、
および、 メンタルヘルス不調の労災に関する労働基準監督署の動向
講義採録
精神障害の労災認定による
新たな法的リスクと企業の事前防止策
精神障害の労災認定制度について社会的に注目される契機となったのは、電通に新卒入社した女性社員の痛ましい過労自殺事案です。労災認定後の臨検監督・強制捜査・略式請求・公判を経て有罪判決が確定しました。
その理由として、申告労働時間と実際の在社時間とのギャップ(自己研鑽のためでなく業務での在社だったことが後に判明)、急激な労働時間の増加(100時間超残業)、上司などからのハラスメント的な発言が挙げられます。これはどんな企業にも起こり得る事案として、各社の人事担当者に問題意識を投げ掛けました。
業務中の事故などに対しては、戦前から労災認定の枠組みがありましたが、精神障害については個別事案でしかなく、制度として確立したのは平成になってからです。
特に平成23年12月に基準が改訂されてから申請・認定件数自体が急激に増加、平成28年度の最新の数字では申請1586件、認定498件と、認定基準改正前との比較でそれぞれ1.3倍、1.6倍となっています。
ここで認識すべきは、同申請件数の約87%、支給決定件数の約83%が被災労働者本人による療養補償給付・休業補償給付であり、長期化する傾向もあるという重要な事実です。このことは精神障害の労災認定とメンタルヘルス休職・復職問題が地続きであることを意味しています。
メンタル不調による私傷病休職社員は増加していますが、休職中、または休職期間満了前後に自分のメンタル不調は過重労働やパワハラによるものであると主張、遡って労災申請・認定されるケースも稀ではありません。「業務上疾病を理由とした療養期間中の解雇」を禁じる労働基準法19条が適用された裁判例もあり、企業実務への影響は多大なものがあります。
個体側の要因、脆弱性客観化の困難
さて、精神障害の労災認定は①業務によるストレス②業務外によるストレス③個体側の既往歴、アルコール依存状況などストレスに対する脆弱性、この三つの要素を複合的に判断する「ストレス−脆弱性理論」という考え方が軸になっています。
まず、精神障害の発病は個体側の脆弱性が一定の役割を果たすことがありますが、現状の精神医学ではその脆弱性を客観的に評価することが容易ではありません。このため精神障害の労災認定では、主に業務によるストレスがどの程度過重であったかが、認定判断において重視される運用が見られます。
「業務による心理的負荷評価表」で判断
厚労省は精神障害の労災認定に際して、「認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること」を求めますが、同判断のために「業務による心理的負荷評価表」が策定されています。
同評価表の通り、業務過重性判断では、1カ月あたりの時間外労働が160時間超のような長時間労働の有無が極めて重要な考慮要素となっています。詳細については同評価表をご覧ください。
いくつかの認定事例を検証すると、慢性的な時間外労働以外でも、例えば新規システム開発に従事したSE職が納期の切迫や予想外のバグなどによって強いられた急激な仕事量の増加などは明確な認定の対象と分かります。
また、サービス残業問題を念頭に、企業側の勤怠管理が本当に正しいか、労基署は慎重に見極めています。平成13年4月6日付「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」、いわゆる46通達の「自己申告により把握した労働時間と合致しているか否か、必要に応じた調査」が重要なのは言わずもがなです。
その他、在社時間は長いが昼寝などしている場合について、厚労省では「〜労働密度が特に低い場合は〜単純に時間外労働時間数のみで判断すべきではない」としているものの、裁判例の傾向を見ると、緩やかに労働時間性を判断している傾向が見られます。
また、同労災認定の対象は一般職だけではなく、管理者も含まれる点に注意が必要です。
質疑応答
尾尻佳津典・「日本の医療と医薬品の未来を考える会」代表(集中出版代表):「素朴な疑問ですが、講演中に何度か出てきた『裁判』という言葉は、労働者が企業を訴えた裁判という意味ですか。『判決』についても教えてください」
北岡:「本日お話しした事例は、主に国側が労災不支給と決定した事案について、労働者が労災支給決定をなすよう訴えた裁判であり、その判決です」
井垣剛太郎・日本経営部長:「労災認定には様々な判断基準があることが分かりましたが、端的に理解するとすれば、心理的負担が強となる出来事がなく、実質的な残業時間が少なければ、全ては個人的な素質によるとの判断がなされると理解してよろしいですか」
北岡:「『個人的な素質』によるものか否かは、医師ではない裁判所、そして労基署も踏み込んで判断することが一般に難しいものですが、ご質問のとおり『業務過重性』が認められない場合には、不支給決定になるものと思われます」
児玉政彦・キノシタ・マネージメント人事部労務課課長:「精神疾患で休職した従業員が就業規則に基づく休職期間満了で退職、その後に労災認定された場合、給与補償は退職時まででよいのでしょうか。それ以降も継続することがあるのでしょうか」
北岡「私傷病休職で退職された方が労災認定された、つまり私傷病ではなかったということになると、会社側の建て付けとしては就業規則に基づく自動退職なのですが、その前提が全て崩れてしまいます。労働契約関係は遡及して復活する。つまり継続していることになるので、労働者本人が就労可能となり、かつ労務提供の意志を示しているにもかかわらず、会社側がこれを受領しない場合には、賃金請求が認められる可能性はあります。労災ですから一定の所得補償はされるのですが、その差額の請求は可能性として大いにあると言えます」



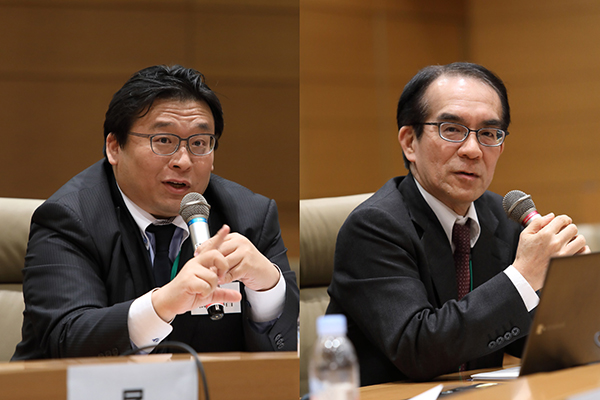
LEAVE A REPLY