
橋爪鈴男(はしづめ・すずお)1953年神奈川県生まれ。聖マリアンナ医科大学医学部卒業。同学部皮膚科助教授、2007年社会福祉法人桑の実会入職。介護老人保健施設ケアステーション所沢施設長・管理医師を経て、08年くわのみクリニック院長。
社会福祉法人桑の実会
くわのみクリニック(埼玉県所沢市)院長㊤
30代最後の年に、パーキンソン病の初期兆候を認めてから12年が経過。橋爪は急速な病の進行で、一時は生きる望みを失いかけていたが、2004年に脳深部刺激療法(DBS)という脳外科治療を受けたことで症状は軽快、車椅子から解放され、歩いて外出も出来るようになった。
とは言っても、発症前の健康体に戻ったわけではないし、障害は残っていた。服薬も欠かせず、その副作用もある。かつて大学助教授だったような第一線の皮膚科医に復帰出来るわけでなく、一旦見失った目標や仕事を取り戻せなかった。
人生設計を建て直そうと思うほどには、気分は上向いてはこなかった。医師の国家資格は一生のもので、医師であることに変わりはなかったが、日本皮膚科学会の専門医資格は、もう必要がないと失効させてしまった。学会の年会費や5年に1度の専門医更新の費用を払い続けるのは経済的に負担になっていた。
患者会を立ち上げて代表世話人に
それでも、自分の経験を活かす道は残っていた。パーキンソン病の患者会を立ち上げて、代表世話人となった。名称のHOPEは、「最新治療に関心のあるパーキンソン病患者と不随意運動症患者と家族の会」の英語名の略称である。日本だけで10万人以上の患者がいるとされるパーキンソン病にはいくつも患者会があるが、HOPEは、DBSを受けた人及びその家族、あるいはDBSをこれから受けようとするパーキンソン病患者と家族を中心にした会であることが特徴だ。
年1〜2回、治療や闘病に関する講演会を開催し、会報も発行する。橋爪自身も登壇して、治療を受けてある程度まで運動機能を取り戻した経験を語ることに、やり甲斐を見出していた。
医師が健康体では、病の人を慮るには限界がある。パーキンソン病を専門とする神経内科医であっても、患者の心までは理解しにくい。橋爪に向かって、「自分の主治医になってほしい」と申し出てくる患者さえいた。
07年初め、「桑原哲也」と名乗る人物から連絡があった。社会福祉法人の理事長を務めており、数年前に面識があったことは覚えていた。橋爪の連絡先を探り出し、電話越しに折り入って頼み事があると切り出してきた。
「こんな自分に何を」といぶかしく思ったが、聞けば、経営する介護老人保健施設の施設長兼管理医師が急に退職してしまって困っており、後任として、ぜひ橋爪を招き入れたいという。
大学病院を退職したことは、自分には医師を辞めたに等しかった。それから5年、再び医師として、それも専門外の内科の仕事が出来るとは思えず、むしろ戸惑う気持ちが大きかった。手足の震えは軽くなり、移動もしやすくなっても、構音障害などは残っていた。発声に力が入らず明瞭な発語が出来ないため、すぐに言葉を返しづらい。
2月の凍えるような日、待ち合わせをしたファミリーレストランに向かった。天気の悪い日は体調も悪く、足を引きずりながら、とぼとぼと頼りなげな足取りだった。熟考を重ねた末、答えは決まっていた。「健康でない人達を、“不健康”な自分が診るのは失礼ですから、とても出来ません」——そう返事をするつもりだった。
老健施設長からクリニック院長へ
果たして、ドアを開けた橋爪に、「お久しぶりです」と手が差し伸べられた。その手と同様に語り口も温かだった。よくよく聞けば、かつて皮膚科に入院し、自分が主治医として担当していた患者であった。治療は、今も外来で続けているという。
「私も皮膚の難病を持っています。一緒に頑張りましょうよ」。同世代の理事長の言葉に、頑なだった心が氷解していった。申し出を有り難く受け入れた。施設に住み込めば、通勤で生じる不自由さはない。自分も障害を抱えた身であれば、入居者達の気持ちは多少なりとも分かるはずだ。
こうして07年、54歳の年、埼玉県所沢市の老健で、橋爪の第2のキャリアがスタートした。入居者には、高齢で骨折や脳卒中などの障害を負った人が多い。急に体調を崩した時などは対応しなくてはならなかった。夜中に薬の作用が切れていると歩きにくいことがあるが、何とか医師として的確な指示を出せた。やがて入居者達に「どんな小さくても良いから、もう1回人生の花を咲かせてください」と、声を掛けて回るほど前向きになっていた。医療とはひと味違った福祉の世界ではあったが、医師の仕事に復帰出来たのだ。
そして1年半後、さらなる転機が訪れた。法人が開設する市内の通所リハビリテーション施設にクリニックが併設され、橋爪は院長となって、皮膚科の診療を受け持つことになった。所沢市内には、障害者や高齢者向けの入居施設が多い。一方で、クリニックのある地区では皮膚科が不足しており、地域のニーズを受け止めた形だ。
橋爪はクリニックの2階に住み込んで、週5回の外来を担当し、毎日30人以上の患者を診た。構音に難があるため、看護師が“通訳”してくれることもあった。専門医資格こそ返上してしまってはいたが、皮膚科医として十分な実力を発揮出来た。
しかし、病状は、容赦なく進展していった。DBSは根治手術ではない。脳内で神経に電気刺激を与えるペースメーカーを埋め込むような対症的な治療で、治療を受けたからといって、病気の進行が緩やかになるわけではない。12年からは、車椅子を再び必要とするようになり、発語もますます不明瞭になった。
16年は脳内の電池の入れ替えやそれに伴う感染症、夏にはS上結腸軸捻転(イレウス)を起こし、その手術などで3カ月の入院生活を余儀なくされた。その後、9月には職場復帰し、今も週3回は外来に出て、週に100人以上の患者を診ている。白衣は着ない代わりに、オレンジやピンクなど、時として沈みがちな自分の心を奮い立たせるような鮮やかな色のポロシャツを仕事着として身に着ける。
診療を減らして空いた時間には、地区の医師会誌などに投稿するためのエッセイを書く。毎日、歩行器を使って歩くための訓練も怠らない。パーキンソン病では、階段は昇り降りするより横の移動が難しい。構音障害は悪化しており、もどかしいことばかりだが、不満を言えば切りがない。
「理事長やスタッフはもちろん、患者さんにも自分の病気を理解してもらっている。本当に良い人達に恵まれて、診療を続けられている」
2人の娘は医師にはならなかったが、1人は保育士に、1人は障害者施設で働き、人を支えることを仕事としている。
振り返ってみると、医師になるまでに25年、大学病院勤務中にパーキンソン病を得て手術を受けるまでに25年、その後、失意から復活の道を歩み始めての日々で、63歳になった。
「この病気は甘やかしちゃいけないんです。75歳まで診療を続けられればいいね」
(敬称略)
【聞き手・構成/ジャーナリスト・塚崎朝子】



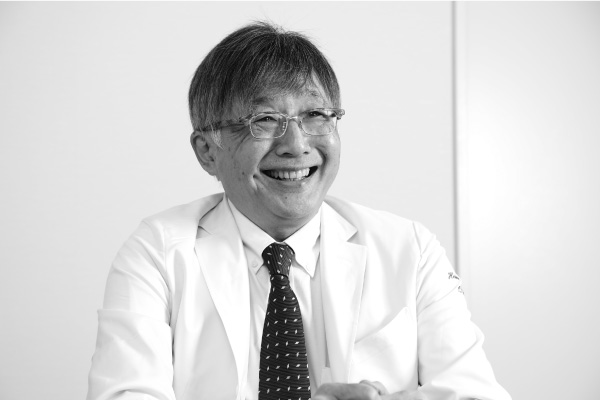
LEAVE A REPLY