医療現場での活用から企業の最新サービスの中身まで
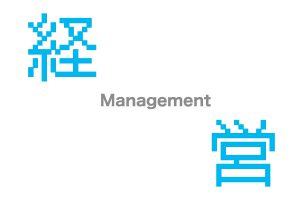 医師不足・偏在の下でも離島や僻地で診療可能、重症化予防・医療費抑制に繋がると遠隔医療が注目される中、「『遠隔医療』の“今”をつかみ“未来”をつくる」をテーマにしたシンポジウムが9月2日、医師専用サイトを運営するメドピアの主催で都内で開かれた。
医師不足・偏在の下でも離島や僻地で診療可能、重症化予防・医療費抑制に繋がると遠隔医療が注目される中、「『遠隔医療』の“今”をつかみ“未来”をつくる」をテーマにしたシンポジウムが9月2日、医師専用サイトを運営するメドピアの主催で都内で開かれた。
まず、「遠隔診療の最新動向と活用の可能性」と題し、日本遠隔医療学会遠隔診療モデル分科会長の加藤浩晃・京都府立医科大学特任助教が登壇。遠隔医療には①臨床医と患者を繋ぐ D to P ②臨床医と専門医を繋ぐD to D ③臨床医と患者の間を看護師などの医療・介護従事者が繋ぐ D to N to Pがあり、遠隔診療は一般的にはD to Pを指し、D to P遠隔診療はさらに保険診療・自由診療の「遠隔診療」と自費負担の「遠隔医療相談」に分かれると説明した。
医師法は20条(医師の無診察治療等の禁止)によって、医師と患者の対面診療を原則と定めているが、旧厚生省は1997年に、遠隔医療は直ちに医師法に抵触するものではないと通知。その後、計9種類の適用症例を例示、僻地など直接対面診療が困難な場合以外でも遠隔診療が可能であるとした。2015年には、遠隔医療の対象を離島や僻地、9種類の適用症例に限定しないこと、対面診療と適切に組み合わせて行うのであれば、初診を遠隔診療で行うことを可能とした。ただし、保険診療では初診料は算定出来ず、自由診療となる。
成長戦略の司令塔「未来投資会議」で議長の安倍晋三首相が遠隔診療を促進する意向を示し、来年度の次期診療報酬改定で評価すると表明している。加藤氏は診療報酬改定に関し①生活習慣病のモニタリング管理料②初診③在宅医療領域④精神科領域──で議論されていると話した。加藤氏は、遠隔医療が外来診療の合間や診療時間外でも出来る点を挙げ、医療機関側に経営的なメリットがある点を指摘。患者にとっても外来で来院する場合と比べて待ち時間や交通費が削減されたり、来院の面倒臭さによる治療の中断を防げたり出来る点を挙げた。
患者の「安心感」を得られる対応が必要
次に登壇したのは、都内に365日年中無休の五つの内科・小児科クリニックを展開している医療法人社団ナイズ理事長兼キャップスクリニック総院長の白岡亮平氏。「地域医療からみた遠隔医療の需要と問題点」をテーマに、開業医が遠隔医療を活用するには何が必要かを述べた。白岡氏はまず、対面診療と遠隔診療のメリットとデメリットを比較。メリットとして、対面診療は医師側には患者に関する情報量が多く、患者側には安心感がある。遠隔診療は医師側には待合スペースや待ち時間のマネジメントが省け、患者側には通院の手間が省け、診療コストが安い点を指摘した。一方、デメリットとして、対面診療は医師側には待ち時間のクレーム対応、患者側には継続診療の中断などを挙げた。遠隔診療は医師側にはオペレーションが確立されておらず、責任範囲の問題もあり、患者側には安心感が得にくく、薬を受け取るまで時間がかかると指摘。現状はデメリットが上回っているが、この先、医療現場における問題が解決されれば、非常に有用なツールとなり得るという。
遠隔医療の実践上で整理すべきポイントとして①対象者②対象疾患③提供者④提供場所⑤提供手段⑥保険診療か自費診療か⑦医師法の問題の7点を列挙。遠隔医療に適した疾患などに慢性疾患、セカンドオピニオン、健康相談を挙げ、ナイズのクリニックで行っている具体例として、禁煙外来、気管支喘息、生活習慣病などを例示した。白岡氏は「安心感を得られる医療従事者のコミュニケーション能力、特に視聴覚情報である非言語コミュニケーションのスキルが重要」と述べた。
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室専任講師の岸本泰士郎氏は「本邦における精神科遠隔医療の展望」を演題に話をした。精神疾患の患者数はうつ病、統合失調症、不安症を中心に320万人、認知症は402万人で、社会費用はうつ病が2.7兆円、認知症は14.5兆円と最も克服が求められている領域だ。精神科薬の治験で患者にインタビューして効果を点数化する際、同じ薬なのに治験によって結果が異なることがある。患者の気持ちが安定しない状態で質問したり、患者の組み込み基準を満たそうと評価者の点数がシフトしやすかったりするためだ。その結果、治験は失敗し、製薬会社が精神科薬の開発から撤退する事態を招いている。そこで欧米では、テレビ会議システムを活用し、中立的な評価者が患者にインタビューするシステムが導入され始めている。
海外では精神科領域の遠隔診療が行われている。日本では75歳以上の運転者を対象にした認知機能検査が始まったが、認知症専門医が不足している上、かかりつけ医では正しい認知検査を行うことが難しい。岸本氏は認知機能検査で遠隔医療が役立つのではないかと考える。また、強迫性障害の遠隔診療での治療例として、患者の自宅でも心理治療が出来るようにiPadやテレビ電話を使って指導したところ、症状が改善したという。
日本医療研究開発機構(AMED)が精神科遠隔医療の臨床研究として「J-INTEREST」を1月にスタート、岸本氏が研究責任者に就いている。このプロジェクトでは①精神科遠隔診療の診断信頼性などの検証②データベースモデルの構築・運用③ガイドライン暫定版の策定に取り組んでいる。岸本氏は「うまく仕組みを作ればビッグデータを国民の健康に役立てることが出来る。この大きな流れの中で遠隔医療が生かせれば」と話す。
遠隔医療相談ではAIを活用して解析
最後にメドピアグループに属するMediplatの企画・運営に携わる眞鍋歩氏(医師)が「医療相談の有用性」をテーマに登壇、チャットとテレビ電話で医師への相談が出来る同社の遠隔医療サービス「first call」について説明した。ほぼ全ての診療科を網羅、約50人の医師が実名で医療相談に応じるサービスで、チャット形式とテレビ電話形式の2タイプがあり、月額540円で何度でも利用出来る。サービスのために募集してきたモニター利用によって、現時点で3万件以上の症例を蓄積している。
テキストベースの医療相談に対しては、AI(人工知能)を使い、病名や薬剤名など固有名詞を抽出してグルーピング化、相談内容の意図を解析している。相談疾患・症状は男女とも腰痛、頭痛、アトピー関連、うつ病が多い。受診前の相談が8割を占め、特に症状の原因やセルフケアの方法を聞く相談が多いという。うつ病に関する相談では、治療中の悩みや不安に関するものが多いが、精神科疾患は一度発症すると経過が長くなる傾向がある。テキストデータの解析からうつ病などの前駆症状を早期に見つけることが可能なので、眞鍋氏は「健康経営が注目される中、発症リスクを予測したり、抑制したりするプログラムを作っていきたい」と話した。


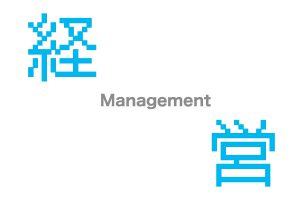
LEAVE A REPLY