認知症理解を通じて、一般市民も暮らしやすい社会の実現を目指す
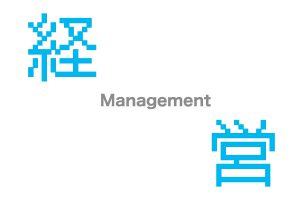 先頃、囲碁AI(人工知能)と人類最強棋士の三番勝負がAIの完全勝利に終わり話題を呼んだが、より複雑で精緻な技術の質量が要求される医療の世界でも、特に認知症ケアの現場でAIの活用が期待されている。
先頃、囲碁AI(人工知能)と人類最強棋士の三番勝負がAIの完全勝利に終わり話題を呼んだが、より複雑で精緻な技術の質量が要求される医療の世界でも、特に認知症ケアの現場でAIの活用が期待されている。
そんな中、メディカルマネジメントサポート事業を手掛けるJSHの主催で、第3回「地域包括ケアにおける認知症対応講座」が5月21日、「エビデンスを生み出す認知症とAI〜医療×人工知能最前線〜」をテーマに、都内で開かれた。
まず、静岡大学創造科学技術大学院特任教授で、同大発のベンチャー企業「デジタルセンセーション」会長を務める竹林洋一氏(工学博士)が登壇した。竹林氏は米国マサチューセッツ工科大学(MIT)のMITメディアラボ客員研究員として、「AIの父」と呼ばれた故マービン・ミンスキー博士らと1980年代から交流・研究を続けてきた。
竹林氏は「介護現場はほとんどが閉鎖的で、認知症ケアは主観的になりがち。そのため、エビデンスは不足し、技術の伝授や改善が難しい」と指摘。その上で、「認知症は病名ではなく、正常に発達した知的能力が持続的に低下して日常生活に支障を来すようになった状態。認知症は個性だ。認知症になっても自分らしく生き生きと暮らし続けることが出来る生活環境を作り出すことが重要」という考え方を述べた。
AIで認知症ケアを〝見える化〟
これらの課題解決のキーワードとして竹林氏が示したのが、AIなどの情報技術を活用して、認知症の人の意図や感情を理解したり、コミュニケーションしたりする「認知症情報学」だ。
認知症情報学は①多様な認知症の人の心的状態の記述②複雑なコミュニケーションのモデル化③多職種連携ツールによる各種データの収集・分析④医療やケアの質の客観的な評価改善⑤地域包括ケアの高度化や脳内処理情報の研究に貢献──とその効用を説明する。
具体的には、認知症ケアの新しい技法として注目される「ユマニチュード」をデジタルやAIで高度化することで、ケアの“見える化”や高齢社会を巡る課題の解決を目指している。
ユマニチュードはフランス発祥で、「人とは何か」という哲学に基づく150を超える実践技術からなる。被介護者目線の「見る」「話す」「触れる」「立つ」という四つの柱と、①出会いの準備②ケアの準備③知覚の連結④感情の固定⑤再会の約束という「心をつかむ五つのステップ」は分かりやすく、第三者に伝えやすい点も特徴だ。
ただ、基本技術を習得するだけでも3年程度必要な上、技術が正しく身に付いているかを自身で判断することが難しい。そこで、竹林氏は認知症情報学の立場から、ケア技術の質の客観的評価と習得の効率を上げることで、ユマニチュードのケアの質向上と普及に貢献しようと考えた。
ユマニチュード開発者の一人、イヴ・ジネスト氏と、日本でユマニチュード導入の先鞭を付けた本田美和子医師(国立病院機構東京医療センター総合内科医長)らの指導の下、国立病院機構東京医療センターと郡山市医療介護病院(福島県)の協力を得て静岡大のチームが開発したのが、ケア映像を多面的に可視化出来る「マルチモーダル評価ツール」だ。「見る」「話す」「触れる」など複数のセンサー、様式(モダリティ)を同時に使って介入するのが特徴で、これを情報学では「マルチモーダル」と呼ぶ。
竹林氏は、認知症へのAI活用により、従来の身体介護中心の支援から、QOL(生活の質)を高めるコミュニケーション支援の研究へ重心が移ると予測。「自立重視のコミュニケーション環境デザイン」「適用型居住空間デザイン」「地域包括ケアシステムの情報化」といった高齢社会全体に関わるテーマを示した。
「見立て知」の充実でエビデンスを創出
より具体的なエビデンスの作り方・使い方についての講義は、竹林氏の共同研究者で静岡大学情報学部助教の石川翔吾氏(博士〈情報学〉)が担当した。石川氏は認知症を、脳細胞の死滅による記憶力・理解力の低下などの中核症状と、徘徊、興奮、妄想などの周辺症状に区別して考える必要があり、中核症状は防げないが、周辺症状はケア支援により環境・心理を変えることで改善出来ることが分かってきたという。身体の種々の感覚細胞から情報が感情の状態を引き起こし、その情報が意思決定に影響を与え、認知症の心理や行動をも変えるのがユマニチュードのケアなのだ。
「見る」一つを例にとっても、認知的距離が短くなっている認知症の人には「距離は20cm以内で」「正面から」「水平の高さで」見ると、評価ツールのケア分析は細やかだ。「見る」に加え、ネガティブな言葉を使わずに「話す」、親指を使わずに掌以上の面積でゆっくり「触る」を二つ以上同時に行うなどの要素が評価される。認知症の人が介護者を敵ではないと認識し、笑顔で再会を望めば、コストパフォーマンスも向上する。
AIを駆使した評価ツールの活用で、研修者は映像を通した「振り返り」により効果的にスキルを向上出来る上、属人的で無く再現性のあるインストラクターとのコミュニケーションが、病棟全体に学ぶ雰囲気を醸成する効果も期待出来る。ある研修では、修了者のアイコンタクトの時間が研修前と比べて20倍超も増えたそうだ。
良いこと尽くめのユマニチュードだが、薬で寝ている高齢者相手ではさすがに成果は出ない。まず検討すべきは、約70種類もある認知症の原因疾患の「見立て」である。
例えば、薬剤の副作用やうつなどの場合は、医療的な介入で改善可能だ。重要なのは介護現場と学びの場を結ぶ医師、家族、介護従事者が共に学習し、共有する「見立て知(識)」を創り充実させ、エビデンスの創出を図ることだ。
会場では実際の評価ツール映像が流され、ケアの空白時間の多い初心者と、前半にしっかりアイコンタクトを取って触れ、全ての時間帯にわたり断続的に話し掛け、手早くケアを行うインストラクターとの対比が鮮やかに映し出されていく。ユマニチュードの中心技術であり、複数の感覚器に働き掛けるマルチモーダル介入の何たるかが一目瞭然だ。認知症の人はその刺激を受け感情を「快」にすることで、脳の多様な部位が活性化され、表情や行動をポジティブに変え、心身の良好な状態を保てるという。
認知症の人とのコミュニケーションで重要なのは相手の性質・特徴や情動・感情を考慮することであり、人工知能「Tay」を開発した米マイクロソフトのサティア・ナデラCEO(最高経営責任者)は「AIが普及した社会で最も大切になるのは、他者に共感する力を持つ人間だ。IT業界だけではなく、多様な人々の関与が必要」と発言している。
竹林氏らは今夏、一般社団法人「みんなの認知症情報学会」を設立する。同学会は市民主体で異分野連携を進め、多様な人が心豊
かに暮らせる社会の実現を目指すと語った。


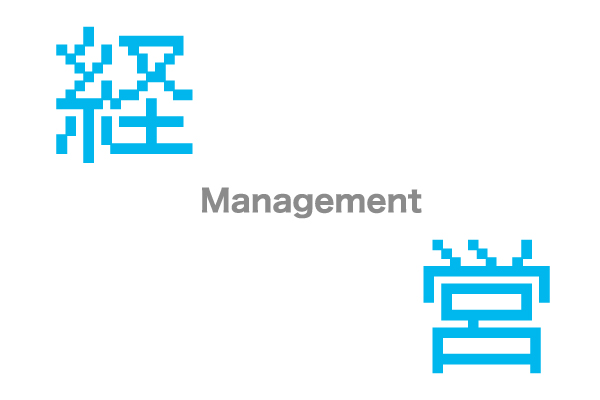
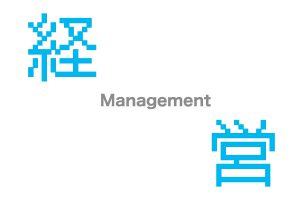
LEAVE A REPLY