求められるのはEBMとNBMの調和
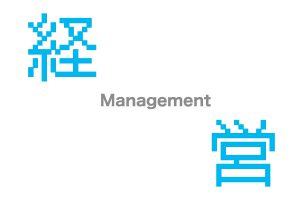 NBMという言葉がある。Narrative Based Medicine(物語と対話による医療)のことで、その対極にあるのがEBM(Evidence Based Medicine:科学的根拠に基づく医療)だ。現在の医療現場では技術の進化、システム化が進み、EBMのガイドラインが作られ、それに沿った診療行為が流れるように進められている。そこでは医師が患者の上に立ち、医療を施す形なので、心の交流は持ちにくい。一方のNBMはお互いの間に共通した物語を紡ぎながら治療効果につなごうというものだ。改めてNBMについて考える医療政策勉強会が都内で開かれた。
NBMという言葉がある。Narrative Based Medicine(物語と対話による医療)のことで、その対極にあるのがEBM(Evidence Based Medicine:科学的根拠に基づく医療)だ。現在の医療現場では技術の進化、システム化が進み、EBMのガイドラインが作られ、それに沿った診療行為が流れるように進められている。そこでは医師が患者の上に立ち、医療を施す形なので、心の交流は持ちにくい。一方のNBMはお互いの間に共通した物語を紡ぎながら治療効果につなごうというものだ。改めてNBMについて考える医療政策勉強会が都内で開かれた。
主催したのは日本医療機能評価機構で、「医療・ケアにおけるコミュニケーションを考える〜周産期の医療・ケアの経験をモデルとして〜」と題された講演に登壇したのは聖マリアンナ医科大学小児科学教室の堀内勁名誉教授。堀内氏は専門の新生児医療の経験を基に、コミュケーションの本質、ナラティブとエビデンス、患者と医療者の対等性などについて話した。
コミュニケーションの本質として、まず触れたのが「間主観性」。「人々は、心は自分のもので、他人には通じないと思っているが、心とは自分と他者の間にあるもの。それを間主観性という。自分と他者の関係が腑に落ちる瞬間があるということで、それは共感や反感、葛藤も含む。一人で生きていたら“心”に気付かないかもしれないが、心はコミュニケーションで生まれてくる」。そして、新生児と母親の例を引いた。「親子で見つめ合い、親からの語り掛けがあり、新生児からの手の動作などがあって、お互いに分かり合い、心と心のコミュニケーションが成り立つ。これは新生児にとって機械的な安全性とは別の次元のものだ」。
ナラティブなアプローチの必要性
堀内氏は、病気になった人は身体の変化により自分自身の捉え方を組み直さなければならないという。「自己の組み直しにより、疾患像を持ち、病者像を受け入れ、治療に挑んでいくことができる。アイデンティティが変容し、疾患と向き合って、戦い、人間として生きていくのだ。その過程で病気は対象として外在化する。これからどう生きるかが、中核自己感の課題となる」。
堀内氏は、物事を進める際の考え方として、アポロ型とディオニソス型を提示。アポロ型は、理性的でいつも冷静。ディオニソス型は個人的体験や自分を超えて新しい心の状態を求める。
これを医療に当てはめると、アポロ型は「自分を失わず、破目を外さない」エビデンス型、ディオニソス型は「ケア提供者は、ケア対象者とともにあり続ける」ナラティブ型になるという。
「以前はアポロ型がもてはやされた。理性と冷静さを発揮し、つぶれない医師が良いとされた。しかし、自分が新生児医療の専門家としての知識や技能という鎧を捨てたら1人の人間としてどうなのかなと考えた時、鎧を脱いだ後にはナメクジみたいにぐにゃぐにゃの自分がいた。鎧をまとっている時はアポロ的アプローチだけだった。脱いだら、ようやく人間として患者と触れ合うことが出来た。それがディオニソス型。聴診、視診、会話を束縛から離れて行う。ディオニソス型は相手の世界に巻き込まれていい。しかし、アポロ的な部分も大切なので、専門家としてのアプローチと心の中のディオニソス型とをどのように調和させるかが課題となる」
堀内氏は、治療を打ち切ったり、患者を見捨てたりするのではなくて、今はできないけれど見捨てないよというメッセージを医師として出し続けるのがアポロ型とディオニソス型の調和になるという。「診療はエビデンスに基づくが、臨床という目の前の患者とのやり取りになると患者の個性を浮かび上がらせる。医師は医療倫理と照らし合わせながら一人一人のことを考えていくもの」。
エビデンスについては「常に過去の患者集団についての情報であり、時間の流れを持たない情報」だとし、一方でナラティブは物語なので起承転結の時間経過がある。臨床のプロセスという時間の経過の中に位置付けられているという。
「結果として死亡してしまうことは同じでも、その過程は本人や医療提供者にとって一人一人違う。お互いに相容れないものの多様性を容認し合いながら、意味付けることが求められる。患者は病気になってしまうことで非日常に突入している。それに向き合うこと。医師は患者の生活情報をどれだけ受け入れられるか。医師が患者に指示を押し付けると生活を壊すことがある。それを医学的な行為とどう同調させるかが課題」
堀内氏は、三つ子を出産した母親の例を挙げた。長くつらい不妊治療を経て妊娠したのが三つ子と分かり、切迫早産のため23週から入院して絶対安静となった。希望した妊娠を悔やむほどだったが、「三つ子を素肌のまま同時に抱くことで、早産というネガティブ体験がポジティブ体験に変わった。医療者も1人の人間として共感できるかどうかが大事」と話す。
堀内氏は看取りにも触れた。「どういう死に方をしようが、誰と最期を迎えるかが大事となる。本人も周りも、生き切ったと思えるかどうか」。
個人を大事にした心の世界を考える
会場からは「生命と“いのち”があるが、医師は身体的なことばかりを見て、心に寄り添ってこなかった」という反省の声も上がった。
堀内氏は「昔は患者の心という観点が全くなかった。医師は思い通りにならないと、患者が悪いと思い込んできた。日本人は甘えの世界に生きている。相手は自分を分かってくれるし、自分も分かっているのが当たり前と思っている。これはエゴの世界。心は自分と相手の間にある間主観性であると定義したが、この醸成には日本人が優れている。日本人は間にあるものを大事にしてきた。日本的なスピリチュアルとは何か。個人を大事にした心の世界を考えると、同時に間にある心をどうするかだと思っている」と答えた。
堀内氏は多職種による協働も掲げた。
「看護師や心理士など職種によって、状況の見方が違う。子供が死亡したら家族へのグリーフケアが必要になる。たくさんの物の見方をまとめ上げる努力が医療現場に必要だし、医療の研究にも必要。1人の思い込みは患者を傷付ける。社会的使命として、医療側のおごりは許されない。患者から学ぶことは多い」
「ナラティブとエビデンスのアプローチの両方を備えた人材を育成するためには何が必要か」という質問も挙がった。堀内氏は「自分の感性をつぶさないと医師としての専門性を発揮できないことはあるが、患者側に立った時に鎧を脱いだナメクジが葉っぱを食べられるようになることもある。弱さを鍛えて強くならずに、弱い方が相手の立場に立てることもある。それには、患者と接するときの対話が大事。そして、医師と看護師は社会心理学などの視点を身に付けていかないと先が見えてこないのではないか。最新技術だけでは人は扱いきれない。人間性をいのちの視点で見ることが必要だ」と述べた。


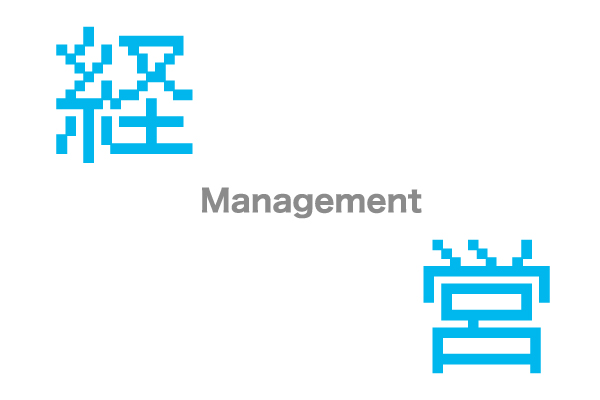
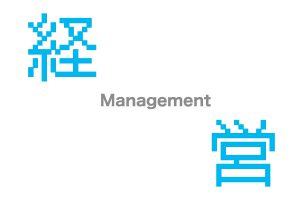
LEAVE A REPLY